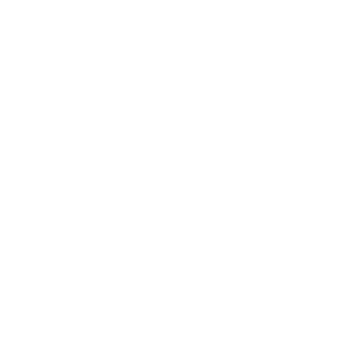生物多様性保全と農林水産業の役割
2010年12月14日
農学部バイオセラピー学科 教授 林 良博
「名古屋議定書」の意味するもの
COP10(国連生物多様性条約第10回締約国会議)の最終日(10月29日)にすべての参加国・地域が、松本龍環境大臣の議長案に同意し、名古屋議定書が採択された。また、会議の先陣を切って10月11日に始まったカルタヘナ議定書第5回締約国会議(MOP5)は、開幕の翌日には遺伝子組み換え生物による生態系被害が起きた際の補償に関する「名古屋・クアラルンプール補足議定書」に各国が合意するなど、今回は生物多様性にとって歴史的な会合となった。
厳しい制約下、日本外交の勝利
思い起こすと、1992年に生物多様性条約が採択されてから8年、遺伝資源の利用と利益分配に関する国際ルールづくりは遅々として進まなかった。生物多様性条約に加盟しているのは193カ国・地域、その8割を占める途上国には「先進国に遺伝資源を持ち出され、利益を奪われてきた」という不満がつよく、先進国との対立が激しかったからである。1カ国でも反対すると成立しないという厳しい制約下での名古屋議定書採択は、日本外交の成果といえる。
採択された二つの議定書は、先住民の伝統的知識も含めた遺伝資源の利用によってもたらされた利益を衡平に分配すること、また遺伝子組み換え生物によっての生じた被害を開発者が補償することを規定しており、先進国にとってきわめて厳しいものであるが、土壇場までもつれたのは、途上国が利益配分を議定書発効以前や植民地時代までさかのぼるべきだと主張したからである。さすがにこの要求は先進国にとって到底飲めるものではなく、代替措置として途上国に多国間で資金支援する仕組みを設けることで、ようやく妥協にこぎつけることができた。
環境NGOや自治体の活動
前述したように、COP10で採択された内容は、一言でいえば、生物資源に関する利益配分と損害補償をどうするのかという経済戦争の妥協産物であって、決して絶滅の危機にある生き物を救おうという高邁な論議の産物ではない。たしかに「赤とんぼでは飯が食えない」と農業者が嘆くように、減農薬・無農薬で手間をかけ、赤とんぼを蘇らせた農作業に報いる仕組みがないと、生物多様性保全はきれいごとに終わってしまう。その点では、COP10の開催期間中にWWF(世界自然保護基金)などの環境NGOや地方自治体がくりひろげた活動は、高い理念の下に生物多様性と経済を結び付けようとする意味で、優れたものが少なくなかった。
たとえばCOP10終了の翌日、10月30日から兵庫県豊岡市で開催された第4回「コウノトリ未来・国際かいぎ」がある。この会議には、初日の全体会議に960名が参加したのをはじめ、2日間で延べ2,950名が参加した。
わたしは実行委員長として開会宣言をおこない、秋篠宮・同妃・両殿下のお言葉の後、「生態系と生物多様性の経済学」と題した基調講演をドイツ銀行理事のパバン・スクデフ氏が行った。同氏は、生物多様性の経済的価値を明らかにするために2007年に立ち上げられたTEEB(The Economics of Ecosystems & Biodiversity)プロジェクトのリーダーであり、3年間の調査をもとに、日本における「コウノトリを育むお米」などの取り組みが、生物多様性保全と地域の経済活動がいかに調和的に行われているかを紹介した。開催地に対する外交辞令がふくまれているとしても、生物多様性を保全することによって、あらたな経済価値を創造することができるというスクデフ氏の指摘は、今後の生物多様性保全に大きな励ましをあたえた。
続いて基調講演を行った豊岡市の中貝宗治市長は、「環境を良くする取り組みと経済活動が、刺激し合いながら高まっていく。環境と経済が共鳴するような地域を創りあげる」という豊岡市の取り組みを紹介した。生物多様性を脅かす危機して知られているのは、人間活動や開発による「第1の危機」、また第1の危機とは逆に、耕作放棄など人間活動の縮小による「第2の危機」、さらに人間が持ち込んだ外来種などによる「第3の危機」であるが、豊岡市はコウノトリに「第2の危機」を克服する象徴としての役割を託し、みごとに成功しつつある。
「責任ある農業投資の促進」宣言
ところでAPEC(アジア太平洋経済協力会議)は、「責任ある農業投資の促進」宣言を10月17日に採択している。将来の食料不足の懸念から、一部の国(たとえば中国や韓国)による途上国での農地確保が過熱している。その結果、地元住民との摩擦がおき、乱開発が進行する危険性を国際的に監視する必要性が生じた。APECの宣言は、アジアにおける新植民地主義を避け、土地と生物資源に関する既存の権利を尊重することによって、環境劣化も最小限にとどめることができるという一石三鳥の宣言ではあるが、各国が競って「国家利益」を最優先させている現状を食い止めることは、困難というよりも不可能にちかいというべきかもしれない。
事実、2年前にドイツで開催されたCOP9では、67カ国の大臣をはじめとする閣僚級の代表が、2020年までに森林減少正味ゼロ(ZEDD)を達成するというWWFの提言に賛同した。にもかかわらず、森林の消失と劣化は驚くべき速さ──毎年1,300万ヘクタール(毎分サッカー場36面分)で続いている。わたしはWWFジャパンの自然保護委員長として、常に無力感を感じることのひとつにこうした現状がある。
生きものへの真摯なまなざし
森林だけでなく、農地や海洋なども悲惨な状況にある。生物多様性保全のために各生態域の10%を保護区にするという目標があるが、全陸域の55%でしか目標が達成されていない。陸域の13%、沿岸の5%が保護されているだけで、公海についてはほとんど保護区になっていない。前述したTEEBは、各国が行っている漁業、農業、エネルギー分野での補助金の多くは、生物多様性を損なうことに貢献していると報告しており、補助金を抜本的に改革して環境保全型農業や省エネルギー政策を推進することが、すべての国にとって緊急を要する課題である。
生物資源の過剰な消費が、生物多様性損失の大きな根本原因となっていることは言うまでもない。農林水産省が設置した生物多様性戦略検討会は、農林水産生物多様性戦略(案)を作成した。同案は平成19年7月6日、新基本法農政推進本部において正式に決定され公表され、農水省のホームページに全文が掲載されているので是非とも一読されたい。わたしは検討会の座長を務めたので実感として理解できるが、「戦略」はどうしても硬い文章になってしまう。そこで検討会は、より多くの国民に読んでもらうために、平成21年10月「農林水産分野における生物多様性戦略の強化」を公表した。「生きものへの真摯なまなざしをとりもどそう」という副題をもつこの提案は、平易な文章で書かれているが、きわめて深い内容をもっている。
この提案は、消費者、農林漁業者、農水省の3者に向けたものであるが、とくに消費者に向けての提案は、食料自給率が40%でしかない日本が、穀物生産量の2倍にあたる1,900万トンもの食品を廃棄している現状を認識して、食行動を大胆に変革することを求めたものである。
WWFジャパンが発表したように、世界の人びとが日本人と同じような暮らしをしたら、地球が2.3個必要になるほど、日本人はぜいたくな暮らしをしている。こうした暮らしを急に変えることはできなくとも、田んぼや畑、森や海辺にでかけて生き物たちを育んでいる環境に触れることはできる。そうした環境を保っている農林水産業の営みに触れることによって、分断された食と農の関係が見えてくるはずだ。その結果、食育や地産地消など、言葉だけで理解していた事柄が自分のものになるのではないかと期待される。