国際食農科学科 上岡 美保 教授と農芸化学科 山本 祐司 教授が、ニッポンの食の未来を考えるイベント「食と生きる」のシンポジウムに登壇
2025年2月5日
教育・学術
国際食農科学科 上岡 美保 教授と農芸化学科 山本 祐司 教授が1月17日(金)、東京ミッドタウン日比谷で開催されたニッポンの食の未来を考えるイベント「食と生きる」のシンポジウムに登壇しました。
「食品ロスの過去と未来」をテーマにした公演には上岡教授が登壇。
会場の聴講者に国内の食品ロスの現況を共有しながら、食品安全保障の観点から食料自給率を高めるためには食品ロスを低減することが大切で、 そのためには地産地消や適正な価格で食品を購入し、食のおかれた現状を理解して食品を美味しく食べるための食育・食農教育が大切になると伝えました。
さらに、日本料理料理人で江戸料理研究家のうすい はなこさん、株式会社榮太樓總本鋪 細田 将己 代表取締役社長とのクロストークでは、食品ロスの原因としてメーカーや料理人、小売業者、消費者それぞれの立場から利益を求めすぎてしまう事が結果的に食品を作り過ぎたり、必要以上に流通させたり、余らせてしまっている事に言及。
根本の問題解決には個々人が食のリテラシーを高め、食品を美味しく味わって食べることが必要だという認識を共有しました。
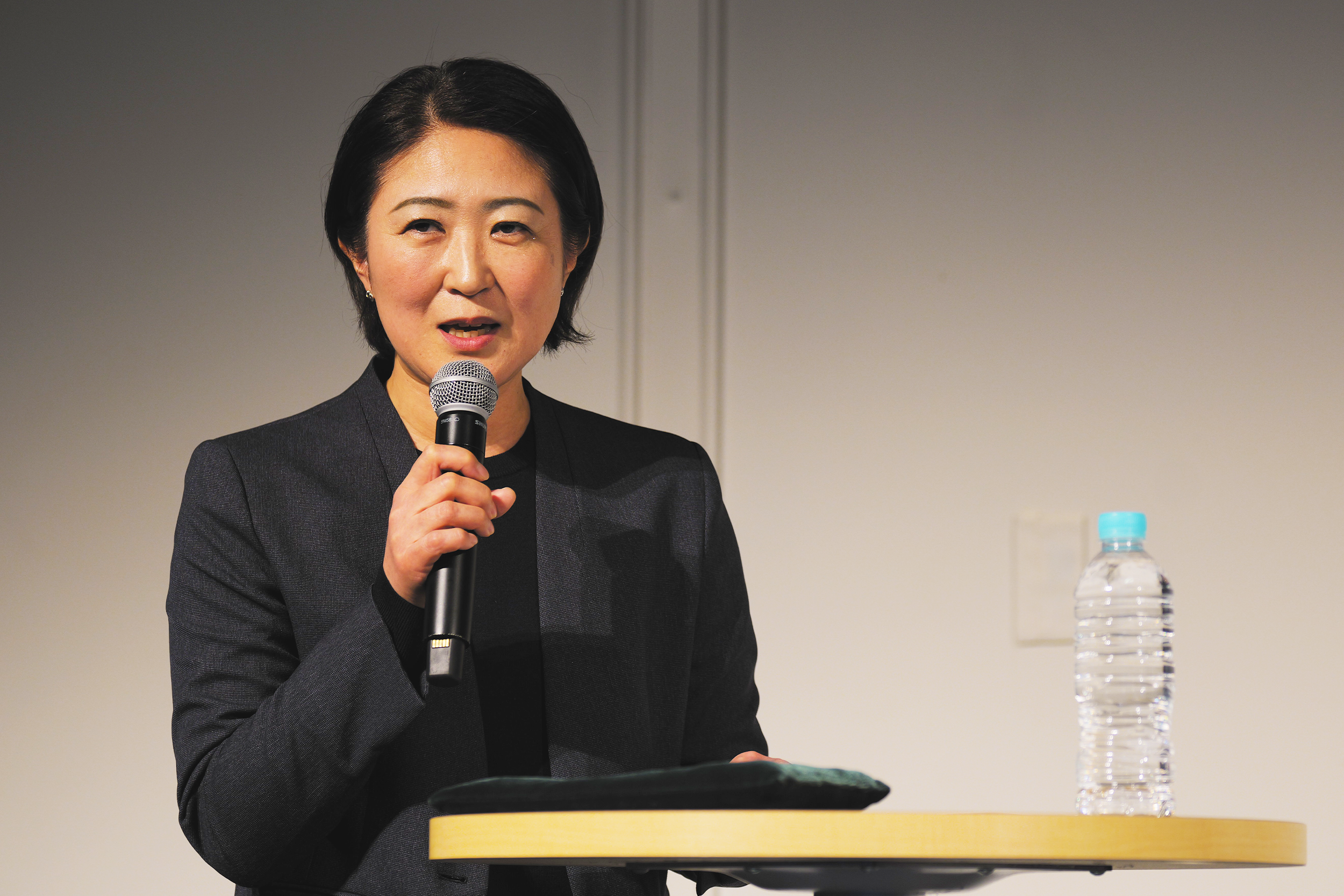

また、「拡がるお米のポテンシャル」をテーマにした公演では山本教授が登壇。
現在、健康診断を受診した成人の3割ほどが脂肪肝と診断されている事に触れながら、ラット実験において玄米がレイノチン酸を正常化し脂肪肝を抑制する事が確認できた事等、東京農業大学が取り組むお米に関する研究成果を発表しました。
そして、にぎりびと・フードプロデューサーの神谷 よしえさん、株式会社ヤマタネ 河原田 岩夫 代表取締役社長とのクロストークでは、値上がりを続けるお米の価値についてそれぞれ文化な観点、生産者の観点、研究者の観点から確認。
産業の未来については、これまでに東京農業大学の学生による柔軟な発想をベースにしたお米の新しい活用方法の提案があったことに触れながら、「既存の概念を変えていく様にチャレンジすることで、産業の発展に繋がっていく事に期待したい」と述べました。
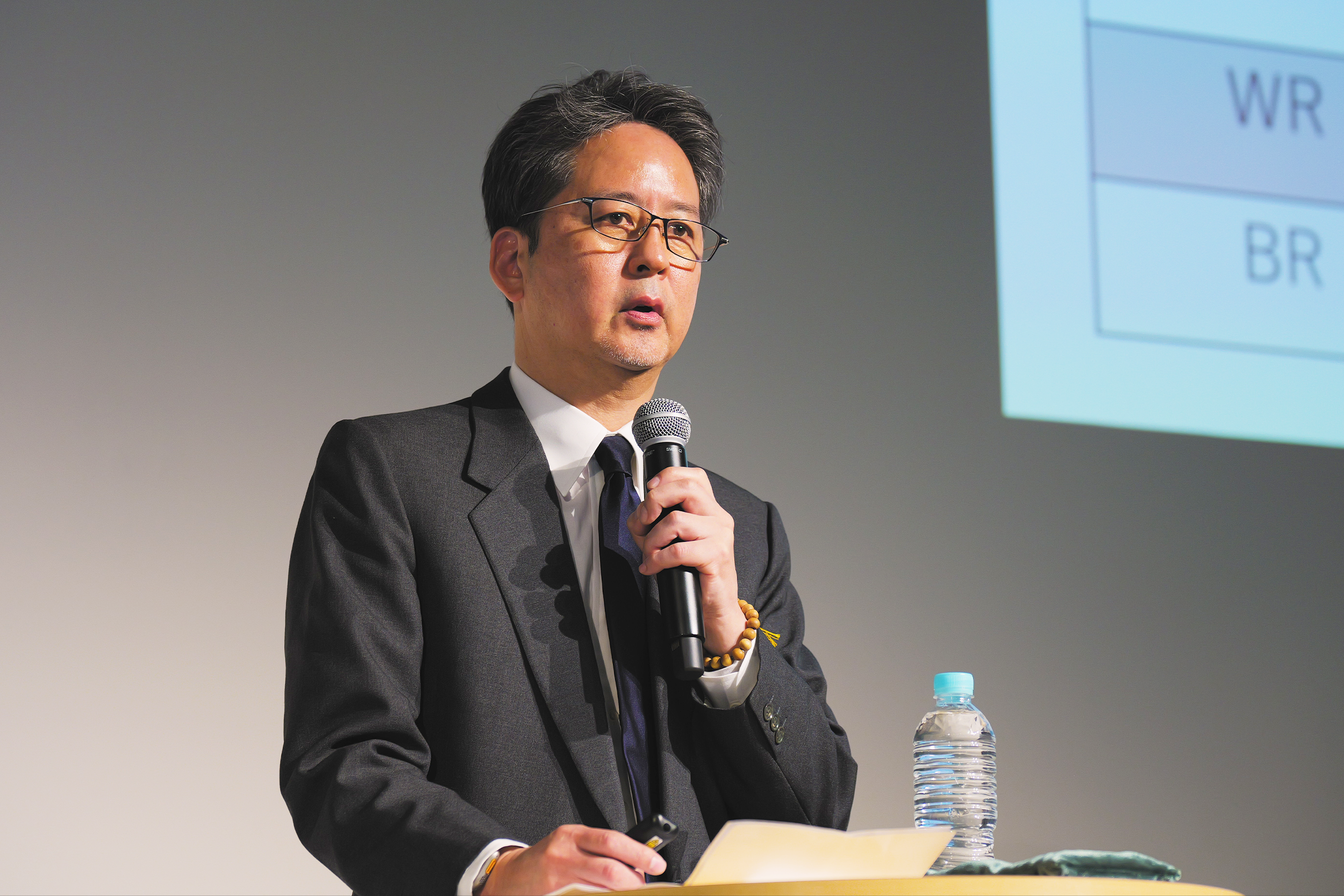

東京農業大学は今後も、総合農学の学術研究により得られた知見を社会的な課題解決に繋げていきます。
