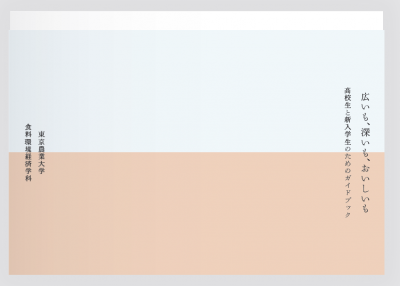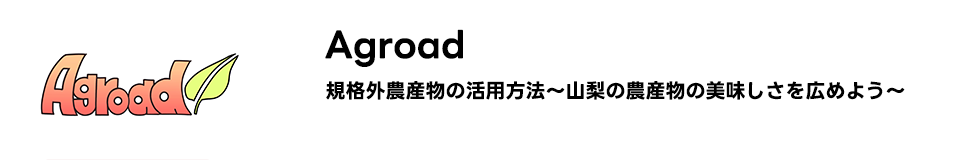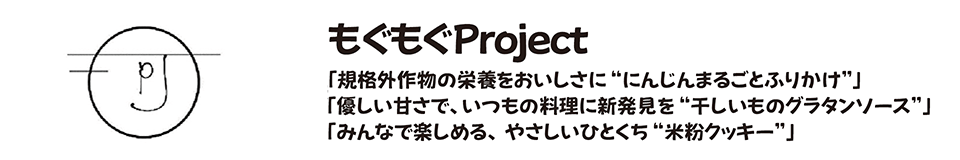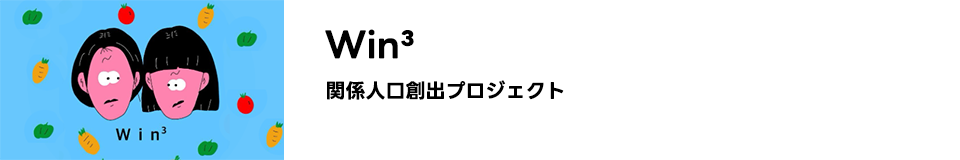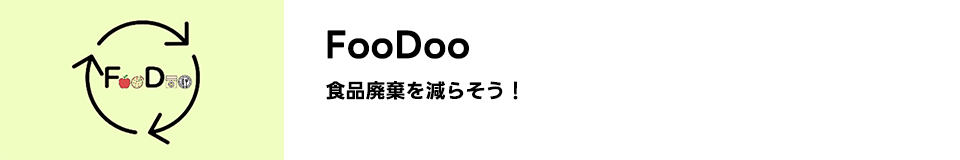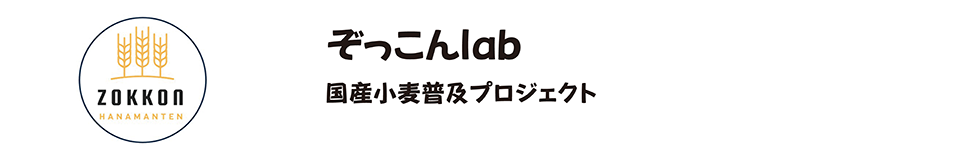食料環境経済学科
世田谷キャンパス
私たちの毎日の「食」は、農業生産者はもちろん食品企業や政府など、様々な社会の仕組みに支えられています。またその仕組みは、農業、地域、環境まで広く考え、持続可能であることが求められます。本学科は、豊かな食を支える社会を創ることを目指し、食を通じてより良い社会を実現する能力をもつ人=「食のディレクター」を育成します。
学科ニュース
学科基本情報
食料環境経済学科のカリキュラムでは、英語、情報基礎、経済学などの基礎科目と「食」について多様な専門科目を学びます。特に専門科目については、2年次から各自の興味やキャリアプランあるいは将来像に合わせて、ブランディングコースとサスティナビリティコースの1つを選択し、より重点を絞った学習を行います。
◎ブランディングコース
地域に埋もれた食材など地域資源の掘り起こしとブランド化、食品メーカーや流通業者による新商品開発や既存商品のリブランディングの手法、消費行動を分析することによって多様なニーズを把握し、生産から消費に至るブランディングについて体系的に学びます。
◎サステイナビリティコース
持続可能な開発目標(SDGs)への取組みとして、食品ロスの削減や資源循環・リサイクルの推進に加えて、安全・安心な食の確保、これらを支援する政策など、社会や環境などに配慮した持続可能で望ましい「食」のあり方=サステイナビリティについて学びます。
高校生と新入学生のための 食料環境経済学科ガイドブック
広いも、深いも、おいしいも 高校生と新入学生のための 食料環境経済学科ガイドブック
(PDFファイルをダウンロードできます。)
教員・研究室紹介
食料経済分野
農業経済分野
環境経済分野
学生研究室活動(1~4年次)1年生から研究室活動に参加できます!
学生研活動では、各地の視察や食料・環境・農業・農村に関する調査・分析などを行っています。そして秋の収穫祭(大学祭)では、文化学術展において、その研究成果を発表しています。研究室によっては、日頃お世話になっている農村地域の特産物を販売する即売店を開いています。
参加するには、研究意欲・やる気・責任感を持っていることが第一条件ですが、1年次から参加することができます。1~4年次までの学生と複数の教員により共同研究を進めることで、調査や分析手法等の専門的な能力を身につけます。1人では行いにくい、現地調査やデータ収集、分析ができます。また、共同研究や学科行事への参加を通じて、学年を超えた交流が行われます。

研究室活動におけるディスカッション
PICK UP!教員
食料環境経済学科をリードする教育・研究者
『実学』研修&プロジェクト
『実学』研修&プロジェクト ~どこよりも『実学』を!~
1. 『実学』研修 …3段階の現場体験で問題意識を育み学習・研究を深めていきます。
1年次
(1)『基礎ゼミ実習』
問題解決の現場を視察・体験
食料・農業・環境の直面する問題の解決に取り組んでいる現場に足を踏み入れ、視察や体験を通じて、今日の姿を理解する学習プロセスを学びます。専門的学習に進む前に、各自が問題関心を育む「気づきの場」となります。ゼミの仲間と交流を深める場でもあります。
2年次
3年次
2. 『実学』プロジェクト
(1) 食品企業連携プロジェクト(通称:食プロ)
食料環境経済学科では、「農業」や「農村」だけでなく、「食品企業」に関する実学プロジェクトを実施しています!日本を代表する大手食品メーカーであるキユーピー株式会社にご協力頂き、食品企業連携プロジェクトをスタートさせました。
実際に食品企業が直面する課題を検討して解決案を提案し、企業側からフィードバックをもらい、解決へのプロセスを実践的に学びます。食品企業の本社が多数立地している東京の立地を活かした食料環境経済学科独自のプログラムです。
(2) 1~4年次 山村再生プロジェクト
耕作放棄地と伝統文化の再生を通した過疎地活性化プロジェクトです。学生の “自主的な” 参加・活動によって運営されていることが大きな特徴です。毎週の勉強会に加え、月に一度は長野県長和町を舞台に実学研修を実施しています。学生・地域住民・行政による協働で地域再生・活性化を担う人材育成をめざします。
(3) 1~4年次 学生×社会 共創プロジェクトBridge(ブリッジ)
食料環境経済学科は、学生×社会 共創プロジェクト『Bridge』をスタートしました。『Bridge』は、学生が社会(企業、行政、地域、農業者、農業団体等)と共に新しい価値を創造しようとするプロジェクトです。
学生達が自主的に企画したプロジェクト案は学科教員によって審査され、採択されれば必要な経費を含め、そのプロジェクトを学科が支援します。『Bridge』は学生の自主性を重視し、企画力やコミュニケーション能力などの涵養を図ることを目的としています。また、プロジェクトの成果 を出すことで、農村地域や食品業界などにおける課題解決に貢献することを目指します。
2025年度 Bridge採択事業
学生×社会 共創プロジェクトBridge&山村再生プロジェクト
卒業後の進路
農・食の業界を中心に多数のOBOGが活躍!
食品メーカー、食料品卸売・小売、食料品商社、JAグループ(農業協同組合及び連合会)等の農業団体、公務員(国家公務員、地方公務員など)、教員など、専門を活かした分野には多数のOBOGが活躍しています!また、銀行など金融機関など、一般的な業種に就職する人もいます。きめ細やかな指導、毎年、満足度の高い就職実績につながっています。
食料環境経済学科では、高校の地理歴史、公民、農業、中学の社会という幅広い教員免許が取得可能です。また、教職課程を履修している学生、実際に就職している学生が多いのも本学科の特徴です!
卒業生Interview
大学院との連携
農業経済学専攻 博士前期・後期課程
農業経済学専攻は、農業及び食料、環境の諸分野において、経済・経営・社会・地理・歴史等の社会科学の多面的な知識をもち、変化する社会・経済情勢に的確に対応のできる分析能力と論理的思考能力を有する研究者および高度専門家の養成を目的とします。