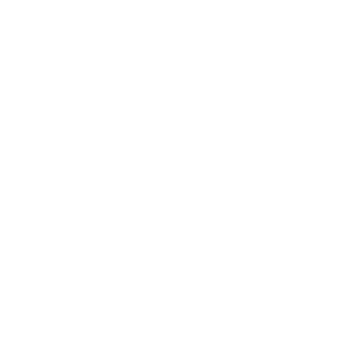ツキノワグマはなぜ人里に出てきてしまうのか?その出没メカニズムに迫る
2016年12月1日
地域環境科学部森林総合科学科 教授 山崎晃司
人との軋轢
2000年代以降、人里へのクマの出没が常態化している。最近は、隔年周期で繰り返され、農畜産物に深刻な被害を与えることに加え、そのような年には100人を超える人々がクマと遭遇して負傷をしている。クマの側も、2,000~4,000頭以上が捕殺される結果となり、看過できない社会問題として捉えられる。今年は、秋田県鹿角市の人里で、短期間に4人もの方がクマに襲われ死亡する未曾有の事件までが起きてしまった。こうした大量出没頻発の背景には、この数十年の間に、里山と呼ばれる部分の森林利用率が低くなり、クマの住める広葉樹林二次林が増加してきたことがある。そのためクマの分布域が広がり、人の生活空間と近接あるいは重複を起こしている。
ここまで単にクマと書いてきたが、実は日本には2種類のクマ類が生息している。北海道にヒグマ、本州と四国にはツキノワグマがそれぞれ生息する。冒頭で述べた、大量出没を繰り返しているのはツキノワグマである。
日本に分布するツキノワグマは、西はイランから東は極東までアジアに帯状に分布するアジアクロクマの一亜種である。アジア全体で見れば、生息環境の減少と断片化、さらには胆嚢や熊掌目当ての密猟などにより、個体数を激減させている。IUCNのレッドリストには希少種として掲載されている。日本にはまだ数万頭が残るが、これはアジアの中では奇跡的であり、おそらく面積あたりの密度では世界一である。世界有数の大都市を抱える国として、世界に誇れる部分ではある。
生態を調べる
私自身は、野生のシカやライオンの研究に関わった後、1991年から本格的にツキノワグマの研究に取り組んでいる。フィールドは奥多摩山地と日光足尾山地で、今回は触れないが、最近はロシア沿海州でもツキノワグマとヒグマの種間競争についての研究に着手した。また、クマ関係のNPOに立ち上げから参加して、いくつかの外部資金を得て、アジアや日本全体でのクマ類の現況に関する調査研究も進めてきた。
国内での研究の目的は大きくは二つあり、ひとつはツキノワグマ(以下、クマ)の生き様を知りたいという純粋な部分であり、いまひとつはクマの適切な保護と管理を実現するための生態情報を蓄積することである。本誌は実学雑誌であるので、今回はその後者について紹介したい。
実学としての研究の大きなテーマは、食物資源の年変動に対して、どのようにクマが生理や行動で応答し、そのことがどのように人里への出没に結びついているかを調べることである。その機序が明らかになれば、出没を予測することが可能になり、さらには生息環境を適切に整備することにより、出没の抑制も出来るかもしれない。
そこで、国内外のいくつもの研究機関と協働するプロジェクトを立ち上げ、外部資金を継続的に確保しながら研究を進めている。研究内容は、クマの学術捕獲(生け捕り後にその場で再放逐する)による各種データの取得と、クマの生息環境の解析の二つに大別できる。前者では、捕獲したクマの外部計測、インピーダンス計を用いた体脂肪量推定に加え、血縁などの遺伝子分析、繁殖生理把握のための性ホルモン分析、窒素・炭素安定同位体比による過去の食性分析などのための血液や体毛などを採取している。歯牙による年齢査定も行う。
また、皮下や体腔内への心拍や深部体温を計測するための各種ロガーの挿入を行い、適当な体格のクマには人工衛星経由で位置情報や活動量などをセミリアルタイムでダウンロード可能な活動量センサーを内蔵した衛星テレメトリー首輪も装着する。試しに数えてみたところ、これまでに私自身が学術目的で捕獲したクマは延べ304頭に及んでいる。生息環境解析では、衛星画像などの複数のソースを用いて調査地の10m精度のクマの食物分布の観点からの植生図を作成すると共に、実際にクマの利用地点に突入して、食痕や糞を回収して利用食物や環境の解析を行っている。同時に、クマの主要な食物の結実量を簡便に計測する方法を開発して、年ごとの食物の量と分布の変動(カロリーマップという)の把握も試みている。
研究から見えてきたこと
このようなさまざまな手法を複合的に用いることによって、調査地のひとつである日光足尾山地では、同地の秋期のクマの主要食物であるミズナラの凶作に連動して、クマが8月頃から行動圏を大きく広げて低標高地に長距離移動する行動が確かめられた。また、凶作年には、普段は保守的であるメスでさえも、オスと同等に大胆な移動を行うことも示された。当然、低標高地への下降は、人間生活空間への接近を意味することになる。移動先で選択した代替え食物はクリやコナラであったが、それら樹種の林分パッチは小さく、環境省などで公表しているスケールの植生図では把握できないサイズであることも明らかになった。ここまでの研究結果は、主要食物の多寡が、クマの大量出没の直接的な引き金になることを示している。
ただし、実際の行動圏の拡大は、堅果結実期以前である8月に起こっている点が悩ましい。そこで、春から夏期のクマの行動や生理の解明が次の課題にとなっている。具体的には、冬眠明けのクマは春から夏にかけて、新葉、花、果実、社会性昆虫などを順次利用することが知られるが、それらをクマがどのように利用し、栄養状態にどのように貢献しているかは不明な点が多い。そこで、クマの直接観察や利用食物の栄養分析などを行ってみた。すると、クマは春先の新葉を、繊維質が低く、タンパク質が高いタイミングでうまく利用するものの、その利用可能期間はせいぜい2週間程度と短いことが分かった。
また、社会性昆虫(アリ類)の利用は顕著であるものの、摂取エネルギー的には基礎代謝量にも足りない可能性が示唆された。さらに、心拍計、体温計、活動量センサーの値は、ほとんどのクマが晩夏期に活動量を極端に低下させることを示した。従来の理解とは異なり、春から夏期はクマにとってもっとも厳しい時期であり、”夏眠”のような状態で動かずに乗り切りたい季節である可能性が見えてきた。ただし、前年の秋に十分な脂肪蓄積が出来ていないクマにとっては、基礎代謝もまかなえない状態になり、生存の確保のために動かざるを得ないことも想像された。これらの新しい知見からは、夏にはじまる大量出没の機序解明のヒントが見えてきたところである。
主要食物の不作年には、前述したような自然の代替え食物の他に、人間由来の食物(残飯、農作物、養魚場など)に依存する事例も記録された。人間由来の食物の多くはエネルギー量が高く、一度味を覚えたクマは多少の障害があろうとも強い執着を示すようになる。調査地で堅果不作年に通常の行動圏から利用標高を下げて移動したオス成獣は、養魚場に執着するようになった。当該養魚場周囲の狭い範囲に1カ月間にわたり居座り、活動時間帯を本来の昼間から夜間にスイッチして死魚や養殖魚用ペレットをむさぼり、体重を急激に増加させた。おそらく、人の存在がクマの心理に働き、活動時間帯を人の影響が少なく、また暗さを有利に利用できる夜間に行動を変化させたのだろう。
以上の研究成果は、国内外の学術誌に掲載(農大ぐるぐる研究室参照)されていると共に、必要なタイミングで行政にも還元されている。今後も研究成果を、クマの適切な管理や保全のための基盤情報として行政などに提供を続けていきたいと考えている。そのための拠点として、またクマにとどまらず野生生物管理や保全に貢献できる人材の育成の場として、農大の役割が期待される。