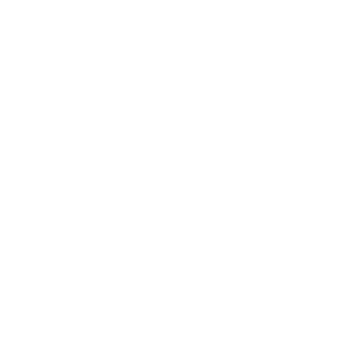国際競争力を失った日本農業
2010年10月15日
国際食料情報学部食料環境経済学科 教授 應和 邦昭
食料自給率低下の根本原因を問う
日本の食料自給率低下について、その主たる原因は「食生活の変化」「食の洋風化」であるという見解が農林水産省はじめ、マスコミ、さらには一部の著名な研究者の間に聞かれる。それは否定できないとしても、しかし、それだけだろうか。食の変化に対応できなかった農業、とりわけ近年国際競争力を失った現状から目をそらすことはできない、と私は考える。
将来の食料供給に国民の不安
表1にみられるように、日本の食料自給率は、過去半世紀間、低下の一途をたどり、いまや、カロリー・ベースの自給率(供給熱量自給率)で40%、穀物自給率(飼料用を含む)で28%という低水準にまで落ち込んでいる。この日本の食料自給率の水準は、世界各国と比べた場合、きわめて低いところに位置する。ちなみに、農林水産省が穀物自給率で比較したところによると、日本の穀物自給率の水準は世界175カ国中125番目であり、先進国といわれるOECD(経済協力開発機構)加盟国30カ国の中では26番目であるという(2003年度比較)。
この低下し続ける食料自給率に対し、日本国民の90%以上が将来の食料供給について「不安である」との回答を寄せていること、また、その国民の不安を解消するために農林水産省が、カロリー・ベースの食料自給率を45%(ないしは50%)まで引き上げるという数値目標を設定し、食料自給率の向上を図る姿勢を示し、その向上策を模索していることも周知の通りである。
農業経済学の研究者の間では、「食料自給率の向上にこだわるべきではない」との議論も存在するが、世界の食料事情や地球環境問題等の観点から考えて、政府が示した食料自給率を向上させるという方向は正しい方向である、と私は考える。だからと言って、政府の数値目標が短期間に達成される見通しは乏しい。
食料自給率低下の主原因を「食生活の変化」に求める農林水産省の見解は、同省発行の『食料自給率レポート』『食料・農業・農村白書』などで表明され、それはマスコミ論調にも受け継がれてきている。しかし、自給率低下の主原因をそこだけに求め続ける限り、情勢如何ではさらに低下する恐れさえあると言わざるを得ない。例えば、1994年から1998年のわずか4年間で、カロリー・ベースの自給率が46%から40%へと6ポイント低下したことを「食生活の変化」で説明することは到底できないからである(表1参照)。
4年間で6ポイント低下した原因
食料自給率低下の原因に関して、農林水産大臣主宰「食料の未来を描く戦略会議」座長の生源寺眞一氏は、「15年ほど前までは『食生活の変化』だったが、今は『農業生産の後退』だ」と論じている(『朝日新聞』2007年9月23日付「耕論:農業再生の道は」/生源寺眞一『農業再生』岩波書店、2008年)。15年ほど前というと、1992〜93年頃であり、上述した1994年以降に急激に食料自給率が低下し始める頃に当たる。
しかし、「農業生産の後退」は原因と言うより、低下の別表現にすぎない。したがって、「農業生産の後退」をもたらした原因こそが問われなければならない。
1994年以降、わずか4年間で6ポイントもの食料自給率低下を招いた直接的な要因は、WTO農業協定の発効、すなわちウルグアイ・ラウンド農業合意に基づく大幅な農業貿易の自由化であり、そして真の原因は〈日本農業の国際競争力のなさ〉である、と私は考える。
食料自給率という概念は、国家間の経済関係、すなわち食料・農産物の輸出入を前提とした概念であり、したがって、食料自給率の低下の根本原因は、農産物貿易をめぐる国際経済関係の中に、言い換えれば各農産物の国際競争関係にある。ウルグアイ・ラウンド貿易交渉に至るまで、日本がコメをはじめ多くの農産物に対して保護措置をとってきた理由は、国際競争力の面で多くの日本の農産物が劣っていたからに他ならない。
この点を、きちんと見抜き、「食料自給率低下の決定的要因は国際競争力のなさにある」といち早く指摘したのは、三輪昌男氏である(『農業協同組合新聞』1999年10─11月号、森島賢氏との対談)。しかし、この主張は、残念ながら多くの人の目に触れることなく忘れ去られた。
国際競争力を奪った要因は何か
食料自給率低下の原因が「国際競争力のなさ」にあるとすると、日本農業からその国際競争力を奪った要因を明らかにすることが必要である。
国際市場のもとで競争力を左右する要素は、言うまでもなく価格である。その価格面での競争力を奪った最大の要因は、1970年代初頭の変動相場制への移行とそれによって生じた急激な円高だった。1970年に1ドル=360円であった対ドル円レートが、わずか20年ほどの間に1ドル=100円といった水準にまで変化するという急激な円高は、1970年の時点で外国の農産物とほぼ互角の価格競争関係にあった日本の農産物が、20年ほどの間に3分の1以下の価格まで引き下げる努力をしなければ互角の価格競争関係を維持できない、ということを意味している(表2参照)。工業とは異なった特性を持つ農業という産業において、わずか20年ほどの間に価格を3分の1以下に引き下げるような生産性の向上は、およそ不可能と言うほかない。
加えて、円高により日本農業から国際競争力が奪われていく中で、円高を引き起こす原因となった1970年代以降の日米間の貿易不均衡を背景とし、アメリカ側から農産物市場開放要求がなされ、国境措置の枠が次々と取り外されていったことも、また、食料自給率の低下を促進した要因の1つである。ウルグアイ・ラウンド農業合意に基づくWTO農業協定の発効後、わずか4年間で日本の食料自給率が6ポイント低下した理由はそこにある。
「食の見直し」にも限界がある
農林水産省が日本の食料自給率低下の原因を「食生活の変化」とみるかぎり、同省の自給率向上策は、いわば「日本人の食生活の見直し論」へ向かわざるを得ない。周知のように、『食料・農業・農村白書』をはじめ種々の同省レポートで「食育のすすめ」「日本食の見直し」論が展開されている。
それ自体は望ましいことであるが、しかし、そのことが食料自給率向上に向けての本筋ではないことをまず認識すべきである。農林水産省は、和食の見直しを進める中で、ご飯、みそ汁、魚介類、青菜等を中心とした「和食」では食料自給率は70%となり、またパン、コーンスープ、ステーキ等を中心とした「洋食」では食料自給率は17%になるとの試算まで行っている。おそらく現時点での各品目の自給率を前提とした試算であろうが、しかし、農林水産省のすすめる「和食」は、例えば、ベトナム産のコメ、ブラジル産大豆とアメリカ産小麦を原料とする味噌、中国産の野菜、カナダ産魚介類でも可能であり、しかもそれは、進行中のWTO農業交渉の行く末を考えるならば、近い将来、大いにありうることでもある。
真の原因を見据えた政策の展開を
食料自給率の真の原因が日本農業の「国際競争力のなさ」にある、と認識したからといって、直ちに有効な食料自給率向上策が浮かんでくるわけではない。それどころか、進行中のWTO農業交渉によってさらに農業貿易の自由化が進んでいくことを考えるならば、自給率の向上どころか現状維持さえも困難だろう。しかし、真の原因を見据え、それから生じる厳しい現実を直視することなくして、問題の解決策は生まれない。
「洋風化」したといわれる食生活はすでに定着し、それを大きく変えることはできないだろう。その上で、食料自給率低下の大きな要素をなしている部分が飼料穀物の輸入にあること、その一方で膨大な耕作放棄地が生じつつあること等を考えるならば、例えば、拡大しつつある耕作放棄地を飼料用米をはじめとする飼料用作物のための耕作地に転換し、その点に手厚い保護を与えて飼料作物の生産拡大をめざす、といった政策こそが、重要な食料自給率向上策の一つではないか。食料自給率低下の真の原因を踏まえた本筋の政策展開にむけて、政府の早急な対応が望まれる。