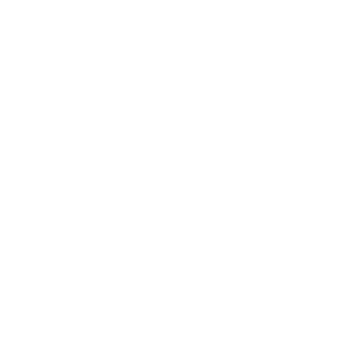近代農学の源流(中)「助っ人」御雇外国人たち
2010年10月18日
近代農学の源流(中) 国際食料情報学部食料環境経済学科 教授 友田 清彦
日本人学者の自立に貢献
ケルネル田圃の記念碑
京王井の頭線の駒場東大前駅周辺は、緑豊かな文教地区である。東京大学教養学部をはじめ、いくつもの学校があり、旧前田侯爵邸跡地を利用してつくられた駒場公園があり、柳宗悦らによって設立された日本民藝館や、日本近代文学館などの文化施設がある。公園もその一角、駒場東大前駅西口間近にあり、東京教育大学農学部の筑波移転跡地につくられた目黒区立の公園である。雑木林や多くの品種の桜に囲まれた心やすまる空間の中、公園北門から入って左側の谷地に小さな水田が広がっている。ケルネルと呼ばれ、その脇道を登った辺りには筑波大学附属駒場中・高等学校(通称、筑駒)によって「水田の碑」が建てられている。なぜ、こんなところに田圃があるのだろうか。なぜ、ケルネル田圃と呼ばれているのだろうか。「水田の碑」とは何の碑で、なぜ筑駒が建碑者なのだろうか。その答えは、一人の「御雇外国人」に結びついてゆく。
英語表記で「ザ・ヤトイ」
主に明治政府が、近代化のために高給を払って雇用した、欧米人を中心とする多数の外国人教師や技師のことを、「御雇外国人」と呼ぶ。「御」が付くのは「」が雇用したからであるが、今日では民間で雇い入れた外国人も御雇外国人の中に含めている。英文ではそのまま「ザ・ヤトイ」とも表記され、国際シンポジウムも開かれている。ユネスコ東アジア文化研究センターが編集した『資料御雇外国人』の名鑑に収録されている御雇外国人の人数は、明治初年から明治22年(1889)までで2,299人にも及んでいる。
さてケルネル田圃である。読者はもうお気づきになったと思うが、ケルネル田圃とは一人の御雇外国人の名前に因んでつけられた。当時の呼び方で、オスカル・ケルネル(Oscar Kellner)というドイツ人農芸化学者である。明治14年(1881)に来日し、同25年(1892)まで、約11年間にわたって駒場農学校で教鞭をとった。ケルネルの在日中における代表的な研究業績が、米作肥料試験である。
わが国の農芸化学の発祥
ところで、筑波大学附属駒場中・高等学校の前身は東京教育大学附属駒場中・高等学校で、遡れば昭和22年(1947)開校の東京農業教育専門学校附属中学校に行き着く。さらに、東京農業教育専門学校の前身は、東京帝国大学農科大学附属農業教員養成所(初代主事:横井時敬)である。東京帝国大学農科大学は、駒場農学校が東京山林学校と合併して東京農林学校となり、それがやがて帝国大学(京都に二つ目の帝国大学ができて、はじめて帝国大学となる)に分科大学の一つとして組み込まれて成立したものであった。
ケルネル田圃とは、もともと駒場農学校の水田(明治11年(1878)現在、水田面積は3,661坪[1.21ha])であり、ケルネルが米作肥料試験を実施した場所であった。近代日本における農芸化学研究の発祥は、この田圃と切っても切れない関係にある。ケルネルの研究は米作肥料試験に止まらず、多方面にわたった。研究助手の役割を果たした日本人研究者は、やがて日本を代表する農芸化学者となっていった。のちに東京帝国大学総長となる古在由直、古在とともに足尾鉱毒の研究で知られる長岡宗好等々である。
駒場農学校のドイツ人教師
駒場農学校の御雇ドイツ人教師は、ケルネルだけではない。ケルネル来日の前年、明治13年(1880)には獣医学教師ヤンソン(J. L. Janson)が来日している。ヤンソンは、明治35年(1902)まで22年間もの年月を駒場で過ごし、日本における獣医学の誕生と発展に貢献した。その後も鹿児島高等農林学校、第七高等学校で教鞭をとり、大正3年(1914)鹿児島の地に骨を埋めている。
また、ケルネル来日の翌明治15年(1882)にはフェスカ(M. Fesca)が来日する。フェスカの本務は地質調査所における土性(土壌)調査事業の指導であり、明治27年(1894)までその職にあったが、同時に同25年(1892)までは駒場農学校に農学教師として兼勤している。フェスカの主著『日本農業及北海道殖民論』や『日本地産論』は、明治期の日本農業に関する最も優れた著書である。ちなみに、駒場農学校卒業後、福岡の地で活躍していた横井時敬に注目し、横井を農商務省に推薦したのはフェスカであった。
駒場農学校のイギリス人教師
横井時敬は駒場農学校農学科の第2期生である。卒業は明治13年(1880)6月。したがってフェスカからもケルネルからも学んでいない。駒場農学校における横井の師は、ドイツ人教師ではなく、イギリス人教師たちであった。彼らは、明治9年(1876)に来日した。農学教師カスタンス(J.D. Custance)、農芸化学教師キンチ(E. Kinch)、獣医学教師マクブライド(J. A. McBride)、試業科教師ベグビー(J. Begbie)などである。ところが、彼らが教えた農学・農法は「いわゆる英国牧畜の粗大農」(駒場農学校1期生・玉利喜造の言葉)であり、日本の現状とは疎遠なものが多かったため、わずか2〜3年という短い期間で任期を終え、母国に帰った。したがって、農学史・農業教育史上における評価は全般的に低い。ただし、キンチは、日本の土壌・肥料等について、はじめて近代化学の視点から分析を施し、その業績は前述のケルネルの米作肥料試験につながっていくという意味で重要であり、また横井時敬はキンチを介してイギリスの農芸化学者チャーチの著書を知り、それをヒントに塩水撰種法を産み出すこととなったという点も忘れてはならない。駒場農学校2期生の中には、横井時敬のほかに、横井のライバルで名農務局長と謳われた酒勾常明、初代の農商務省農事試験場長沢野淳などがいる。
札幌農学校のアメリカ人教師
駒場農学校と並び称されるのが札幌農学校である。札幌農学校では、マサチューセッツ農科大学の卒業生を中心とするアメリカ人教師が活躍した。この札幌農学校は、わが東京農業大学とも少なからぬ関係がある。明治24年(1891)創設当時の育英黌(東京農業大学の前身)の教頭、荒川重秀は札幌農学校の1期生であったし、教師の渡瀬寅次郎も1期生、岩崎行親は2期生、諏訪鹿三は3期生であった。また、明治26年(1893)私立東京農学校と改称された当時の主任講師は、4期生の河村九淵であった。
アメリカ人と言えば、明治9年(1876)、現在の京都府南丹市蒲生に開校された京都府農牧学校のウィード(J. A. Weed)、開拓使に雇用され牧畜の指導にあたったダン(E. Dun)、農学教師ではないが アメリカから農具や種苗を取り寄せ農業技術の普及にも努めた熊本洋学校のジェーンズ(L.L. Janes)なども逸することができない。
「助っ人」が解雇されるとき
わが国における近代農学誕生のうえで、御雇外国人が果たした役割はきわめて大きい。しかし、自らも御雇外国人であり、かつ御雇外国人研究の先駆者であったグリフィス(W. E. Griffis)が、御雇外国人を“Japan’s Foreign Helpers”と呼んだように、彼らはあくまでも助っ人(Helper)であり、それ以上のものではなかった。歴代の駒場農学校校長が日本人であったことから看取できる通り、決定の主導権はつねに日本人にあり、助っ人である御雇外国人たちは、やがて日本人農学者の自立とともに解雇されていくのである。