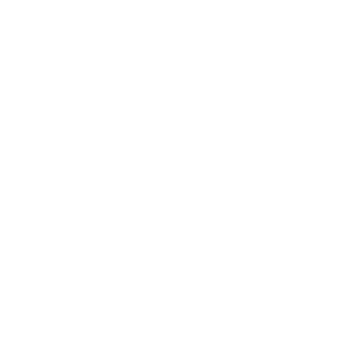近代農学の源流(上)文明開化、啓蒙家たちの時代
2010年10月18日
近代農学の源流(上)国際食料情報学部食料環境経済学科 教授 友田 清彦
その保健休養機能の研究
日本における近代農学の成立は、「泰西(=西洋)農学知識」の導入という形で始まる。かくて文明開化の時代を率いた啓蒙家たちの業績をまず概観することから、明治日本の近代農学の源流を探りたい。
『明六雑誌』、開化思想を鼓舞
山川出版社の『詳説日本史』という高等学校用日本史の教科書を繙くと、「文明開化」の項目に、「富国強兵をめざす政府は、西洋文明の摂取による近代化の推進をはかり、率先して西洋の産業技術や社会制度から学問・思想や生活様式にいたるまでをとり入れようとした」と記されている。このような動きは、農学の分野でも同様であった。
文明開化、啓蒙の時代を象徴するのが、明六社である。明治6年(1873)、森有礼・福沢諭吉・西周・加藤弘之・西村茂樹らによって創設された。結社の翌年、明治7年(1874)3月に『明六雑誌』を創刊し、同8年(1875)11月、第43号をもって廃刊するまで、短期間であったが、学問・思想の分野で、文明開化の時代を率いた。
在野の農業啓蒙家、津田仙
『明六雑誌』廃刊の翌年、明治9年(1876)1月に、津田仙という人物が農業結社、学農社を結成し、同社から『農業雑誌』を創刊した。津田仙は明六社の会員でもあり、『農業雑誌』は日本では最も早い時期に刊行された農業雑誌の一つである。廃刊は大正9年(1920)第1221号であったから、当時としては長命な農業雑誌で、後年まで農業界に少なからぬ影響力を維持している。
津田仙は旧幕臣である。蘭学・英学を学んだ洋学者で、外国奉行支配通弁(通訳)に任ぜられ、慶応3年(1867)には小野友五郎(長崎海軍伝習所一期生)の随員として渡米、戊辰戦争では越後で「官軍」に抗戦した。農業に係わるようになったのは、戊辰戦後、東京に戻り、清水喜助(清水建設創業者の2代目)の設計施工で有名な外国人向けホテル、築地のホテル館に勤務するようになってからである。麻布本村町に買い求めた土地で、このころから西洋野菜の栽培を始めている。明治6年(1873)ウィーン万国博覧会に三級事務官心得として参加、そこでオーストリアの農学者「荷衣伯連(ホーイブレンク)氏」に出会った。その農法の要点をまとめ、明治7年(1874)に刊行したのが『農業三事』という著書である。同書は大きな反響を呼び、ベストセラーとなった。
キリスト教系農業結社、学農社
学農社をおこし、『農業雑誌』を創刊、あわせてわが国最初の私立農学校である学農社農学校を開校したのは、明治9年(1876)である。同校卒業生には、のちに盛岡高等農林学校(現岩手大学)・鹿児島高等農林学校(現鹿児島大学)の初代校長をつとめた玉利喜造、『女学雑誌』の編集や明治女学校の経営で著名な巌本善治などがいる。ちなみに、勝海舟の三男梅太郎の妻となったクララ・ホイットニーの日記(『勝海舟の嫁クララの明治日記』中公文庫)には、このころの学農社の様子がいきいきと描かれている。津田仙はメソジスト派のキリスト教徒として、足尾鉱毒反対運動や禁酒運動、盲学校教育などに尽力し、また女子教育にも熱心であった。わずか8歳(数え年)の次女むめを、岩倉使節団に同行させて、米国に留学させたことはよく知られている。むめとは、津田塾大学を創設した津田梅子である。
『開農雑報』と農政官僚
津田仙は文明開化期の典型的な農業啓蒙家であり、彼の創刊した『農業雑誌』は、とく明治初期において大きな役割を果たした。しかし、『農業雑誌』は日本最初の農業雑誌ではない。『農業雑誌』に先だって、明治8年(1875)5月に『開農雑報』が、開農義会という農業結社から創刊されている。津田仙があくまでも在野において活躍したのに対して、開農義会に集った人々の多くは、内務省や大蔵省の主に農政を担当した官僚たちであった。とは言え、人材的には多彩である。
近代移行期の知識人、島邨泰
開農義会の中核であった島邨泰は、幕末期に親藩岩槻藩の藩校、遷喬館の館長を勤めた人物である。遷喬館では文道としては漢学と習礼の二科が教えられた。『開農雑報』創刊当時は大蔵官僚であり、『富国のもとひ』(明治7年)、『立会就産考』(同8年)、『農学教授書』(同9年)などの著書をあらわし、江戸時代の経済学者・農学者佐藤信淵の『田年中行事』に補注を加え刊行している。大蔵省が雇い入れたイギリス人技術者キンドル(T.W.キンダー)の『造幣寮首長年報』(明治5年)やイギリス人メイエルの『台湾風土記』(同7年)を翻訳していることから、英学の知識を有していたことも窺える。
英学者の鳴門義民と後藤達三
有力会員であった鳴門義民と後藤達三は、いずれも津田仙と同じ旧幕臣で、かつ英学者である。鳴門は神奈川奉行支配のもとで「通弁(通訳)兼翻訳御用」を勤め、後藤は明治初年に開成所や大学校(いずれも東京大学の前身)の教師などを勤めた。『開農雑報』創刊当時は、ともに内務省勧業寮の官僚であった。内務省勧業寮は、のち勧農局となり、さらに明治14年(1881)農商務省となる。今日の農林水産省である。
鳴門は、公務のかたわら鳴門塾という英学塾を経営した。その塾は、一時は慶應義塾に迫ろうとする勢いだったと言われている。鳴門には代表的な訳著として『独逸農事図解』(明治8年)がある。これは、博物学者として著名な田中芳男が、明治6年(1873)のウィーン万国博覧会の際に持ち帰った、1葉1テーマの彩色された図とその解説で構成される西洋農業図絵(全30葉、附録1葉)を翻訳したものである。後藤にも『斯氏農業問答』や『牧羊手引草』など、明治農業史上重要な訳著がある。前者の「斯氏」とは「賢理斯的墳」氏で、書名は今風に言えば『ヘンリー・ステファン氏の農業問答』である。
「尚古派農学の指導者」織田完之
開農義会の中心的会員には鳴門義民や後藤達三のような英学者も多いが、必ずしも西洋一辺倒というわけではない。最も特徴的な人物を挙げれば織田完之であろう。織田は、天誅組の変で知られる勤王家、松本奎堂について学び、幕末には国事に奔走した。明治に入ってからは、内務省の農政官僚としての勤務と並行して、佐藤信淵の多くの著書を校定復刻し、その紹介に努めた。『農家永続救助講法』『勧農雑話』(いずれも明治8年)などの著書もある。農商務省移行後は、古農書の収集や、『大日本農史』『大日本農政類編』など農史編纂に従事し、引退後は平將門や楠木正成夫人の顕彰などに尽力した。
このように洋学か国学かの違いはあるにせよ、彼らはいずれも単なる官僚ではなく、啓蒙家的な農政官僚であった。また、明治政府をテクノクラートとして支えた人々には旧幕臣が多かったと言われるが、農学の分野においても同様な傾向が窺えるのである。 明治10年代に入ると、『農業雑誌』や『開農雑報』以外にも、多くの農業雑誌が創刊され、おびただしい数の翻訳農書が刊行された。「泰西農書」などからの翻訳・翻案は、日本の近代農学の重要な源流のひとつである。しかし、源流はひとつではない。いくつかの太い水脈が、近代農学の成立に向かって流れ込んでいる。そのひとつは、農学校の御雇外国人教師である。これについては、次回取りあげてみよう。