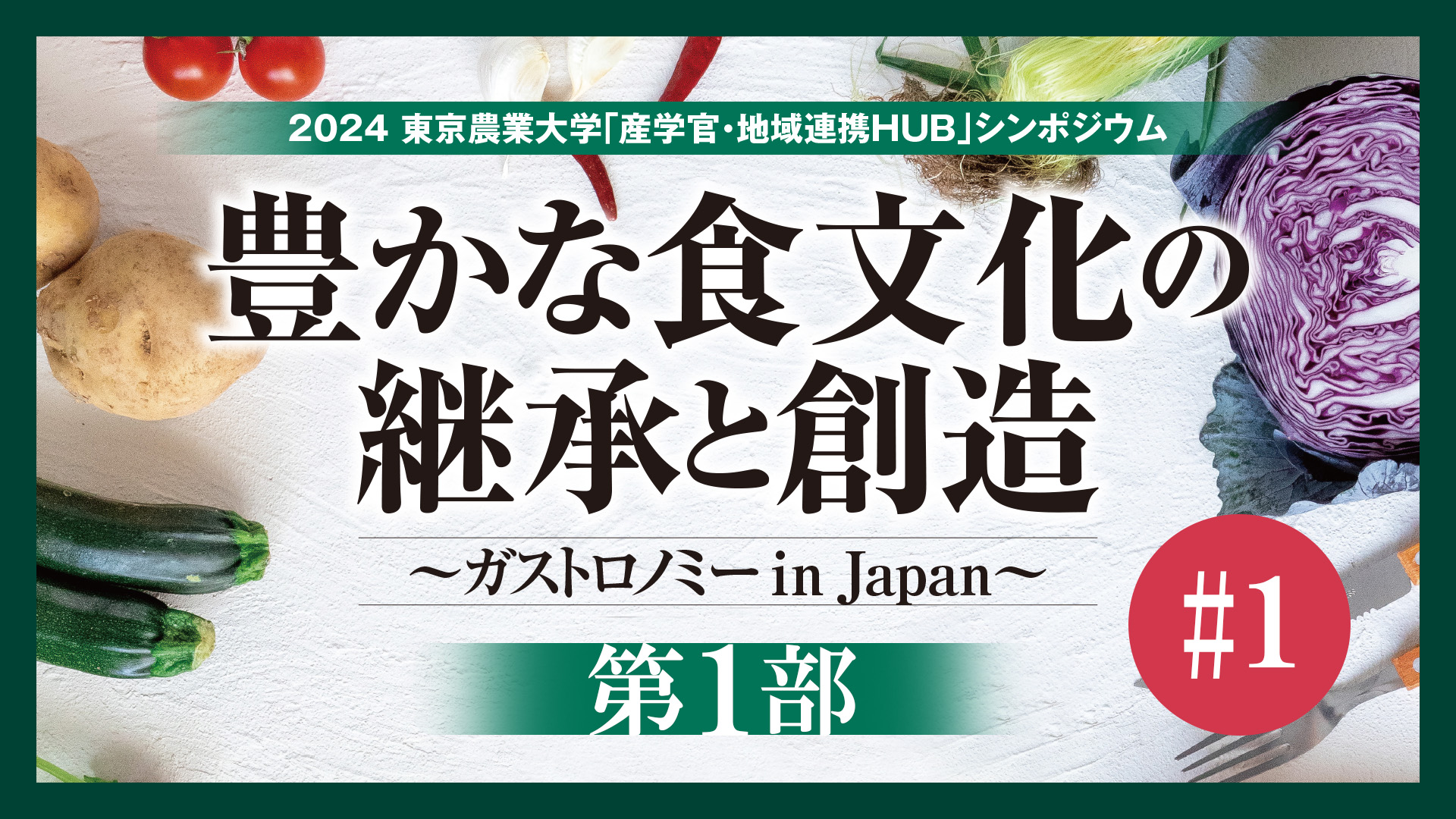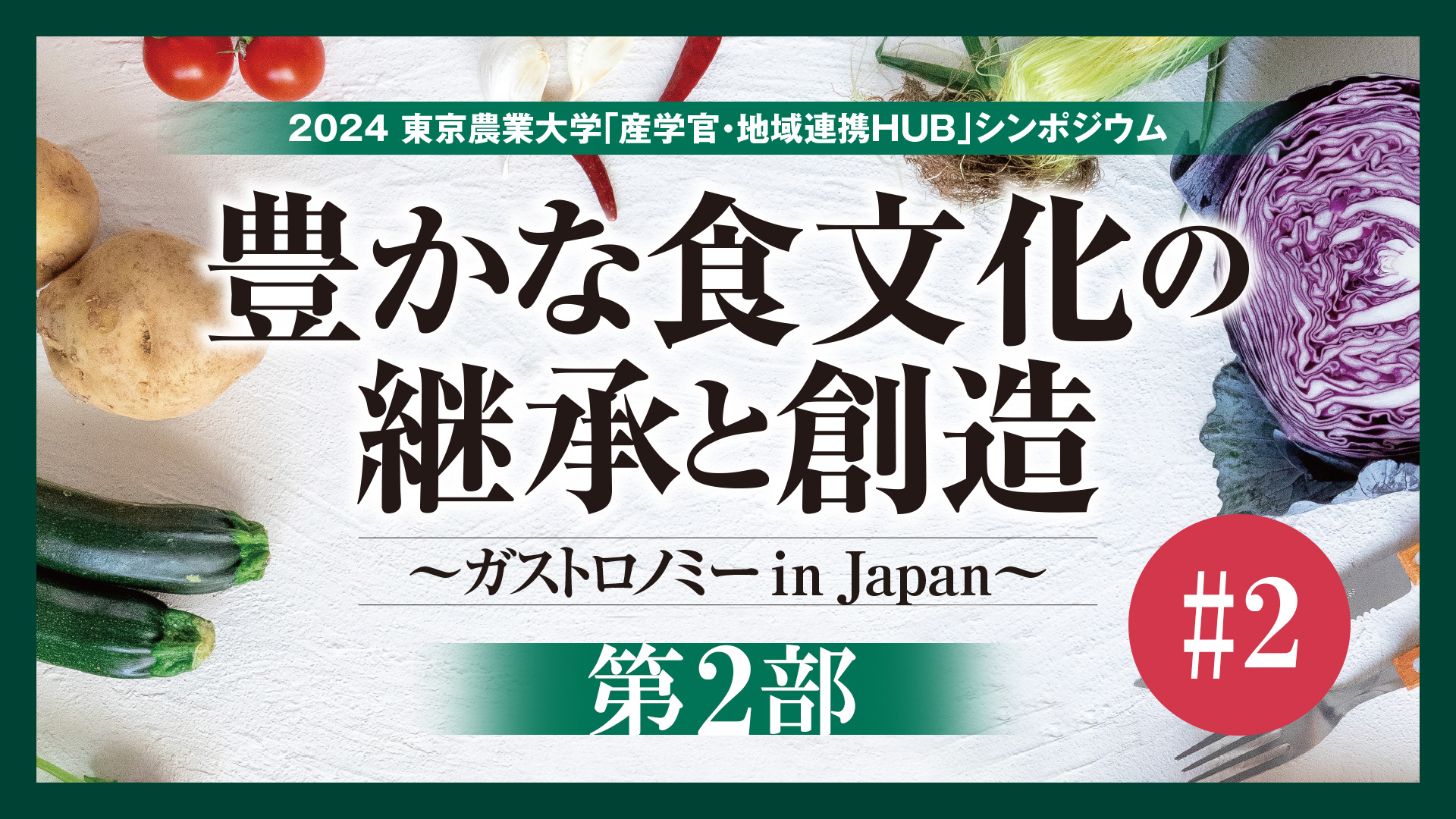東京農業大学「産学官・地域連携HUB」シンポジウム「豊かな食文化の継承と創造~ガストロノミー in Japan~」を開催
2024年12月3日
教育・学術
東京農業大学は11月14日(木)、世田谷キャンパスにて東京農業大学「産学官・地域連携HUB」シンポジウム「豊かな食文化の継承と創造~ガストロノミー in Japan~」を開催しました。


シンポジウムは産学官・地域連携センター 平山 博樹 センター長の挨拶により開会。平山センター長は「『ガストロノミー』という単語は非常に耳なじみが良く、記憶に残る言葉だが、非常に幅広い領域・学問。私も含めて、本日ガストロノミーの理解を深め、今後の活動について考える機会にしたい」と述べました。

第1部では日本各地の先進的なガストロノミーの取り組みについて、鶴岡市企画部食文化創造都市推進監(兼)食文化創造都市推進課長の三浦 裕美さん、霧島ガストロノミー推進協議会 会長 / 霧島市観光協会 副会長 / きりしま高原麦酒株式会社 代表取締役の山元 紀子さん、株式会社菊の井 常務取締役 / 株式会社ちさこ食堂 代表取締役 / ZEROCO株式会社 取締役の堀 知佐子さんから紹介がありました。

三浦 裕美さん(鶴岡市企画部食文化創造都市推進監(兼)食文化創造都市推進課長)「ユネスコ食文化創造都市鶴岡市の取組」

山元 紀子さん(霧島ガストロノミー推進協議会 会長 / 霧島市観光協会 副会長 / きりしま高原麦酒株式会社 代表取締役)「霧島ガストロノミーブランド『ゲンセン霧島』」

堀 知佐子さん(株式会社菊の井 常務取締役 / 株式会社ちさこ食堂 代表取締役 / ZEROCO株式会社 取締役)「地方食材を使用したガストロノミー」
第2部では冒頭に江口 文陽 学長が「東京農業大学ガストロノミーの現況と今後」について講演。
東京農業大学では初代学長・横井 時敬による「実学」への想いを継承し、3キャンパスと関連する地域等と連携した東京農大版のガストロノミーを打ち出している事や、ガストロノミーを単に美食や高級食材を定義するのでは無く、教育・研究・実学・健康、そして学生活動に関わる「食」と解釈している事を紹介しました。

さらに第1部でガストロノミーの取り組みについて事例紹介を行った3名と江口学長、産学官・地域連携センター 平山センター長、野口 敬夫 副センター長の6名が登壇し、トークセッションを展開。



最後に上岡 美保 副学長が閉会の挨拶に際し、日本酒や焼酎、泡盛といった日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録される可能性が高まり、東京農業大学 醸造科学科の果たす役割や注目度がさらに高まる事や、ガストロノミーが「食文化」に関する幅広い学問であり、東京農業大学の推進する「総合農学」は、その幅広さと多様性においてまさにガストロノミーという学問そのものである事等を伝えました。

東京農業大学は今後も「総合農学」に関わる教育・研究を通じて、豊かな食文化の継承と創造に貢献していきます。