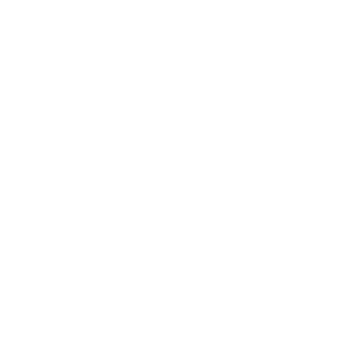ウマの輪郭
2014年9月1日
教職・学術情報課程 教授 木村 李花子
1.野にウマを見に行く
馬に会う
ウマとそれにまつわる事象が私の専門となった背景には、子供の日々に巨大な馬という生き物に直接触れた、という恐怖にも似た感動の体験がある。
この動物を知る手段として、当時まだ目新しかった動物の行動や社会を研究する学問に取り組んだ。フィールドは北海道自然放牧馬にはじまり、カナダ・セーブル島の再野生馬、アフリカ・ケニアのグラントシマウマやグレビーシマウマ、インドのインドノロバやチベットノロバなど、ウマ属の系統図を動物行動学という磁石を携えて歩いてきたのかもしれない。
野生ウマの生きざま
ウマ属動物の社会を構造の違いで分けると、ハレム型と縄張り型に分けることができる。比較的湿潤な草原のような環境下で形成されるハレム型社会では個体間コミュニケーションがよく発達し、特にハレム内には優劣関係にもとづいた順位制が存在するなど高い社会性が認められる。モウコノウマやサバンナシマウマなどのハレム雄は敵雄と戦い、雌たちを管理するために膨大なエネルギーを費やす。
一方、ノロバやグレビーシマウマなどは縄張り型社会に属する。それぞれの個体が殖兼採食地の土地を維持する社会である。繁殖戦略としての囲い込む土地の条件は、雌との出会いが多いか、あるいは出産と育児に適しているかになる。乾燥した食草バイオマスの低い土地では恒久的な群れは作られず、雌は雄の縄張りで一時的な関係を持つにとどまり、多くの縄張りを渡り歩くなど、ハレム型の集団に対し基本単位は個であると言える。
しかしこの区別も可逆性を含んでいて、原拠であるバイオマスの変化により一般的には縄張り型と考えられていたウマ属が、群れてコミュニケーション行動を発達し始めた例もある。これをふまえれば「賢い馬」と「強情なロバ」といったお伽話の中にも定着したキャラクターの違いは、種の違いというよりは、むしろ社会型の差違が生み出した特徴であると考えられる。
匂いの世界の攻防戦
ウマ属動物が深淵な嗅覚世界を持っていることは繁殖期に多くの雌を抱えたハレムの雄が一日中、雌の糞や尿に、自分の尿をかけている光景からも容易に察しがつく。雌を5、6頭も抱え込んだ大ハレムでは、この匂い付け作業に忙殺され雄はゆっくり草を食べる暇もない。糞や尿には多くの情報フェロモンが含まれており、また雄の尿には匂いの情報を隠蔽するクレゾール類が含まれていることも分かってきた。発情した雌の尿は雄の交尾行動を促す。糞には性別、発情、年齢、出産経験などの、個体情報が満載されていて雄たちにとっての格好の標的になってしまうのだ。この匂いをハレム雄は命がけで確認・隠蔽作業を繰り返すのである。匂いの世界とは個体を表出し、隠す、権謀術数、目に見えぬ闘いの世界でもある。
2.野に人を見に行く
ヒマラヤを移動する人々
インドの野生ロバについては行動学の周辺が面白い。移牧民や遊牧民等、つまりは移動する人々とウマ属動物の関係を調査する事が、家畜化や環境問題、グローバリズム等の是非に直接触れられる機会となった。西部の塩性湿地や北部の山岳地帯が次なるフィールドである。
現在、インドの国立公園や野生動植物保護区の、実に65%が牧畜民に放牧地として利用されている。これを、保護生物の危機と捉えるか、あるいは牧畜民がうまく共生を実現させている数字と捉えるかは、判断しかねるところだ。
ジャンムー・カシミール州での調査は、宮崎大学やミュンヘン工科大学の研究者らとのプロジェクトにまで発展した。はじめに野生動物保護区を放牧地として活用する遊牧民・移牧民による草地の利用状況を調査し、さらに野生ロバなどの野生動物との利用空間の競合状態、あるいは共生関係の有無等の現状把握に努めた。同時に、現代の科学と牧者らの生態知や伝統的知見を共存させることで、自然と人間の共生関係を構築できる放牧方法を共に試行した。国境地帯の良質な放牧地を、印パ戦争によって奪われた移牧民が、今後より深い洞察力と行動力を持って移牧の形態を維持し、希少生物との共存を果たすための協力を続けていきたいと思う。
移牧民の知見、遊牧民の生態知
山羊飼部族移牧民バックラワールは、冬の低地放牧地ジャンムー地方と夏の高山草原放牧地(ダシガン国立公園等)を、片道約100〜150km、3000m近い標高差を、春の約1カ月をかけて移動し、秋には1、2カ月をかけて戻る移牧を行っている。夏山には牛飼や羊飼部族も放牧しているが、放牧地では親族ごとに管理するテリトリー(ドーク)を持つことで、放牧密度の偏りがくい止められ、草地の状態は比較的良好に保たれている。放牧による食草の多様性の低下は否めないが、過放牧が全ての悪因であるかのごとき言説ほどには草地は疲弊していないようである。ここ10年間のGIS(地理情報システム)によるリモートセンシング調査によれば、植生状況の変化の要因は放牧インパクトよりも、むしろ降雨量(積雪量)によると考えられる。
一方、山羊・羊・ヤクを放牧するラダック・ルプシュ地方のチャンパは、チャンタン寒冷砂漠野生動物保護区内の、直径約20〜25km圏内を、約50家族が13000頭の家畜を年間放牧している。年間平均7カ所もの放牧地を移動し、見事に集約的草地の利用が避けられている。また、馬やヤクなどの放牧地では、多頭数を放牧した場所のバイオマスの方が増加するという、過放牧によるインパクト説とは逆の放牧効果を示す現象も起きている。伝統的手法やローカルな生態知を科学的に証明することによって、今日の問題を解決する手段とする調査研究を、今後も続けていこうと思う。
3.博物学的視点 −博物館、家畜化−
博物館で働いていた経験から、博物学的手法で事象を捉える事を常に意識している。特に生命や環境といった複雑に絡み合う現象を学ぶ者にとっては必須の手法といえよう。また学問の分野のみならず、芸術分野への興味も大いに発揮していきたいところである。現職の学術情報課程・学芸員コースの授業を通して、このような物の見方を学生諸子に習得してほしいと思っている。
現在「食と農」の博物館で、「農と祈り ─田の馬、神の馬」展を、博物館スタッフ、学術情報課程の先生方及び学生の協力を得て開催している。ここでは、馬という動物の二つの姿、つまり役畜としての馬と、宗教や儀礼・行事に深くかかわり神と人を媒介する役目の馬に焦点を当てた。馬がさまざまな習合を繰り返し、抽象的な信仰対象から、具体的な祈りをささげる民間信仰の中に息づく様は、例えば「厩猿」などの資料や、農村を背景にした農耕儀礼にかかわる藁馬などの資料から読み取ることができる。そこには、古代から昭和まで、常に国の政策に取り込まれ、公の支配下にあった馬という家畜が、さまざまな形で人に寄り添う姿をご覧いただけると確信している。
博物学とは、いいかえれば自然科学の全てであり、現代科学の分野でその本流をくむもののひとつが、エソロジー(ギリシャ語「エートス:特徴、気質」に由来する)、つまり動物行動学であるといえる。今後はウマ属の行動や社会から見る家畜化というテーマを、ライフワークとして追い続けていきたいが、エピジェネティックスという新しい遺伝学領域を考慮することで、動物の行動や気質を変化させてきた家畜化初期の段階に、重要な役割を果たしたいくつかのミッシングリンクが、おぼろげながらに見えてきたように思うのである。