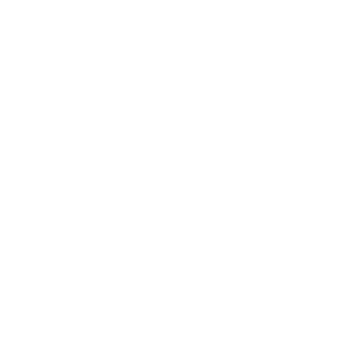遺伝子から見えてくる水産動物の進化と効果的な保全
2012年4月1日
生物産業学部アクアバイオ学科 教授 千葉 晋
東京農大「先端研究プロジェクト」報告(上)
プロジェクト名:極東亜寒帯地域における野生生物の遺伝的多様性評価とその保全
生物保全は、実学である
保全生物学は、80年代に確立された比較的新しい学問であるが、その背景には急速な生物多様性の喪失を前にして、既存の農学、森林学、水産学では対応できなかったことがある。言い換えれば、保全生物学とは人間の存続可能性と密接に関係している産業学、すなわち実学なのだが、それを認識している人はあまりに少ない。
生物多様性の認識における問題は、さらに根が深い。一般に、生物の保全として扱われている話題のほとんどは、絶滅の恐れのある「種」の保全である。希少種の保全はもちろん重要だが、それは末期的な保全レベルである。そもそも種とは、いくつかの地域ごとのグループから構成されているので、たとえ同じ種であっても、地域的に何らかの変異が見られることが常である。そして多くの場合、その見た目の変異には遺伝的な変異が関係しており、遺伝的な変異には、その地域に応じた"事情"がある。
生物種を複数の地域グループ、すなわち遺伝集団から考えることによって、保全の手法は大きく変わるだろう。また、この考え方でいけば、保全対象とすべきは、何も希少種ばかりではないことが分かる。ごく普通に見かける種でも、地域ごとに守っていく必要があるかもしれず、そこには当然、その地域を代表する観光生物資源や、魚介類のような天然食糧資源も含まれる。これからの生物多様性の保全では、「希少になる前に保全する」という考え方が重視されていくはずで、そこでは遺伝的多様性という視点がカギとなる。
平成21年度から3年間、東京農業大学先端研究プロジェクトとして、極東亜寒帯地域の遺伝的多様性の保全手法に関する研究を行う機会を得た。調査対象として、地域を代表する湿原性の植物、水産動物、鳥、哺乳類から10種を選んで行った。本号記事を含め、これから3回にわたり成果の一端をご紹介したい。初回は水産動物の中から、クロタマキビという巻貝と、ホッカイエビという漁獲対象となっている甲殻類での成果である。
種、遺伝子を保存する知床半島
北海道東部の磯には多様な貝類が存在するが、最も多いのはクロタマキビという巻貝である(図1)。クロタマキビは東北を分布の南限としている北方種で、千島列島を介して北米西海岸まで、北太平洋沿岸を取り巻くように広く生息している。極東亜寒帯を象徴する種として、この巻貝の遺伝的特性を調べたところ、私たちの認識を改めざるを得ない3つの事実が見つかった。1つ目の発見は、クロタマキビは形態からでは種を特定できないというものである。形態的に同種として判断されるクロタマキビを対象に、核とミトコンドリアのDNAを調べたところ、クロタマキビ以外にもう1種存在することが明らかになった(図1)。つまりもう1種は、クロタマキビに酷似しているものの互いに繁殖しない新種(隠ぺい種)であり、この結果はこの巻貝に対して形態による種判別は適切ではないことを意味する。2つ目の発見は、一部の新種のミトコンドリアDNAはクロタマキビのそれと同じだったことである。これはクロタマキビと新種は過去に交雑していたことを意味し、両種は比較的最近に種分化したと考えられる。そして3つ目の発見は、クロタマキビの遺伝的多様性は知床半島でのみ顕著に多様で、しかも知床の遺伝子型の一部は北米西海岸のものと共通していた。このことからは、知床半島が北太平洋におけるクロタマキビの分布拡大の一端であること、さらに知床半島の急峻かつ複雑な地形によって、氷河期等の地球環境の変動で失われてしまった多くの遺伝子が知床半島に保存されていたことが想像される。
本研究はクロタマキビを対象とした結論であるが、論理的には海岸動物の多くに適用できる。特に後者2点の発見は、知床半島の独特の地形が、多くの海岸動物の種、遺伝子を保存してきた可能性を示唆するものである。知床半島は世界自然遺産であるが、知床の環境を保全することは、私たちの認識以上の生物学的な意義がありそうである。
自分で性を決定し、しかも小型化するエビ
次に紹介したいのはホッカイエビという漁獲対象種の保全についてである(図2)。本種は、北海しまえびという商品名で流通する北海道を代表する海の幸である。流通規模が大きくない分、希少価値が高く、キロ単価は国内甲殻類でもトップレベルに位置する。本種の主たる生息地で遺伝的特性を調べたところ、数十kmスケールでの集団間で遺伝的な変異が観察された。つまり、ホッカイエビはそれぞれの地域で遺伝的に独立して進化してきた可能性が高い。一般に、海の動物は幅広い範囲で遺伝的に交流があると考えられており、ましてやエビのように移動性の高い動物が数十kmスケールで遺伝的に分断されているという事実は大変珍しい。遺伝的に分断されているのであれば、ホッカイエビ漁業の持続可能性は、それぞれの地域の保全手腕に掛っていると言える。
生物保全の基本はその種の生活史に関わるイベントの解明である。それぞれの地域でホッカイエビの生活史に影響する要因を網羅的に調べた結果、もっとも影響していたのは実は漁業活動であった。このエビは、体が大きくなるにつれてオスからメスに性転換する。漁業では、商品価値が高い大型のエビを優先的に漁獲するのだが、その結果、漁獲物の9割以上はメスになる。つまり、漁業によって慢性的なメス不足が起きてしまうのである。
ところが驚くべきことに、ホッカイエビはメス不足の程度に応じて、自分の性転換タイミングを変えていた。周りにメスが少ない時は、通常ならオスになる小型のエビがメスへと性転換してしまうのである。これは自分の利益(子孫を残す確率)を上げるためのエビによる利己的な対応であるが、結果的には、個体群の性比を一定に保つことになる。集団で暮らすホッカイエビのような動物で性比調節ができることは、理論的には古くから予想されていたものの、本研究が世界で最初の実証例である。
ただし、この性比調節は万能ではなかった。あまりに小さいメスは十分な数の卵を産めないので、最低限の大きさに到達していなければ小型メスになっても意味がない。漁業によって取り残されるエビはしばしば小さすぎて、エビによる性比調節は不十分であった。つまり選択的な漁獲による影響は、本種が進化的に獲得してきた対応能力を超えていたのである。
ここでもうひとつ興味深い事実が見つかった。四半世紀分のデータを解析したところ、メスの体の大きさは徐々に小型化していたのである。これは、性転換サイズの下限値が遺伝的に少しずつ小型化していることを意味している。では、産む卵の数はどうなっているのか。まだ状況証拠ではあるが、古くから漁業を行ってきた集団では、比較的最近に漁業を始めた集団よりも卵が小型であった。次世代シーケンサーを用いて、両集団の卵サイズの遺伝差を調べたところ、機能性タンパク質をコードする9つの遺伝子配列で変異を検出することに成功した。漁業によるメスおよび卵の遺伝的小型化は、状況証拠としては固まってきたところである。
ホッカイエビを漁獲していく限り、慢性的なメス不足は解消できない。しかし、このエビ特有の柔軟な対応能力を上手く利用すれば、持続可能な漁業は可能であると想像している。私たちは生物の持つ能力を生かした利用方法、そして保全をもっと科学的に考えるべきである。
図1.クロタマキビ(左)と今回発見された新種
図2.ホッカイエビ