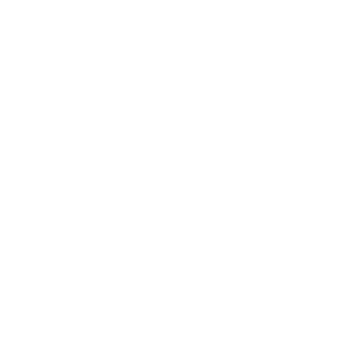日本農業の国際競争力を考える
2007年4月25日
国際食料情報学部食料環境経済学科 教授 金田 憲和
経済グローバル化への課題
経済のグローバル化が進行している。WTO(World Trade Organization:国際貿易機関)のドーハ開発アジェンダ(ドーハ・ラウンド)が大詰めに近づく一方で、世界各地で次々とFTA(Free Trade Agreement:自由貿易協定)が締結されている。わが国でも、こうした経済のグローバル化の流れに取り残されまいと、ドーハ開発アジェンダの早期決着、各国とのFTA締結を求める声が強い。 しかし、こうした国際貿易交渉を進める上で、日本農業の国際競争力の弱さが交渉の足枷として常に問題とされている。実際わが国は、輸入農産物に対して高い関税を設定して国内農業を保護しているが、それにもかかわらず、食料自給率(供給熱量ベース)は先進国では最低レベルの40%であり、大量の農産物を海外から輸入している状態である。 なぜ日本農業は、かくも国際競争力が弱いのか。ここでは、この問題を考えてみたい。
資本、労働、土地の3要素
産業の国際競争力を決めるものは一体何だろうか。これに答えを与えるのが経済学の一分野である国際貿易論である。ここでは、その重要な理論の一つであるヘクシャー・オリーン理論によって、わが国の農業の国際競争力を説明して見てみよう。
ヘクシャー・オリーン理論においては、生産要素が極めて重要な役割を果たす。生産要素とは、モノを生産するために必要な根源的な要素のことで、一般には、資本、労働、土地の三つを指す。この場合の資本とは機械設備や建物といった、いわゆる固定資本である。
ヘクシャー・オリーン理論によれば、ある国におけるある産業の国際競争力は、その国に賦存(=存在)している生産要素の量とその産業の生産要素集約度との二つで決まる。例を挙げよう。一般に、わが国のような先進国には、資本が豊富に賦存する一方で、労働の賦存量は乏しい。これに対して、中国のような途上国には、労働が豊富に賦存する一方で、資本が乏しい。この場合、資本集約的な(=生産に資本を多用する)産業である自動車産業は、資本豊富な先進国が強い競争力を持つ。一方、労働集約的な(=生産に労働を多用する)産業である衣料品産業は、労働豊富な途上国が強い競争力を持つ。この結果として、先進国は自動車を輸出して衣服を輸入することになる。逆に途上国は、衣服を輸出して自動車を輸入するのである。これはまさに、日本や中国において成り立っている貿易パターンである。
「土地賦存」の乏しい日本
このヘクシャー・オリーン理論を農業に応用してみよう。農業生産にとって特に重要な生産要素は土地である。言い換えれば農業は土地集約的産業である。しかし、農用地として利用できる土地賦存量(=面積)は国によって極端に異なる。アメリカなどと比べればすぐ分かるように、わが国の土地賦存量は大変少ない。実はこれこそが、わが国の農業の国際競争力が弱くなる最大の原因である。ヘクシャー・オリーン理論によれば、わが国のような土地賦存の乏しい国は、土地集約的産業である農業に国際競争力を持ち得ないからである。この傍証として重要な事実は、同じわが国の農業のうちでも、畜産業は比較的高い自給率を維持しえてきたことである。わが国の畜産業は飼料を国内生産せず輸入に頼るようになったが、このように国内の土地を使用しないようにすることで、畜産業自体の土地集約度を低く保つことができた。この結果、わが国の畜産業は競争力を維持し、比較的高い自給率を維持できたのである。その最も典型的な例は鶏卵産業で、自給率は今日でも95%である。
農産物輸入の土地含有量
ここで少し見方を変えてみよう。
わが国が農産物を輸入することは、土地を海外から輸入したのと同じ効果をもつ、という説明がされることがある。言い換えれば、日本国内に土地が乏しいからといって、わが国の消費者はそれだけの土地しか利用できないわけではない。海外から農産物を輸入すれば、それは間接的に海外の農地を「利用している」(=土地サービスを輸入している)ことになるからである。こうすることで日本の消費者は、国内の土地の制約を気にすることなく、海外の土地を利用した豊かな食生活を享受できる、ということである。
このように考えると、農産物の貿易は単に農産物自体の貿易というにとどまらず、土地という生産要素の間接的な貿易であると考えることができる。
筆者はかつて、日本が農産物輸入を通じて海外から間接的に輸入している土地サービスの量(=輸入の土地含有量)を計測した。日本の農産物輸入に含有される土地の量は、1985年時点で1,891万haに達した。これは、国内の農用地使用量583万haの約3倍にも当たる数値である。このように、今や日本人の食生活は国内の農用地面積をはるかに上回る海外の農用地に依存しているのである。
さて、農産物貿易が土地の間接的貿易を意味するという命題を、さらに精密化してみよう。完全な自由貿易といくつかの仮定のもとでは、輸出入に含有される生産要素は、ある数式に従うことが証明されている。これをヘクシャー・オリーン・ヴァネック理論と呼ぶ。
完全自由化した場合
このヘクシャー・オリーン・ヴァネック理論を実際の日本のデータに適用すれば、わが国が完全な自由貿易を行った場合の農業と農産物貿易の姿を知ることができる。すなわち、今後WTO交渉やFTA締結の進展などを通じて、わが国の国境措置が完全に自由化された場合に、日本の農産物輸入がどこまで拡大するのかを、海外からの土地純輸入の形で予測することができるのである。
では、筆者が実際に計算した土地純輸入の予測結果を見てみよう。表2がそれである。表の上段は、ヘクシャー・オリーン・ヴァネック理論をわが国と世界全体との間の貿易に適用した場合の数値であり、下段は、わが国と高所得国との間の貿易に限定して適用した場合のものである。耕地純輸入の予測値は、対世界全体の貿易の場合で1億2,659万ha、対高所得国の場合で5,020万haである。つまり、より数値の小さい対高所得国の場合でも、予測値は日本国内の耕地賦存量の10倍を超える。一方、現実の日本の耕地純輸入は1,585万haであり、これは対高所得国の予測値と比べても、いまだ3分の1程度でしかない。
理論による予測値と比べて現実値がはるかに小さいというこの結果は、何を意味するのだろうか。この予測値は農産物輸入の完全自由化を仮定した上で予測したものである。つまり今後、農産物輸入の国境措置が緩和されていけば、実際の土地純輸入量は拡大して予測値へ近づいてゆくはずである。これはすなわち、農産物の輸入が貿易自由化によってますます拡大することを意味する。しかも、予測値と現実値のギャップの大きさから考えて、この方向に向かう力は極めて強く働くものと考えられるのである。
食料安全保障への道
わが国にとっての農業・食料政策上の最重要課題の一つは食料安全保障である。そして食料安全保障の確保のためには、やはり国内での食料生産を一定程度維持することが望ましく、これ以上の食料自給率低下は望ましくない。
しかし、国内の乏しい土地賦存を考えれば、わが国の農産物は国際競争力の点で始めから大きなハンデを背負っている。したがって、関税などの国境措置は長期に継続する必要があり、関税の低下速度も緩やかなものでなければならない。
わが国の農政は、経営の大規模化を目指した市場志向的なものへと大きく転換しようとしている。このように今後の農政では、国内では市場メカニズムを生かしながら、その基盤として、同時に、やはり国境での効果的な保護を欠くことはできないと考えられる。