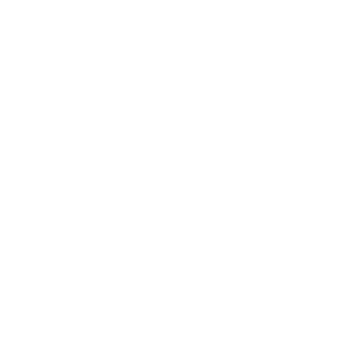有害病害虫の侵入を水際で防ぐ
2005年5月1日
農学部農学科 教授 根岸 寛光
植物検疫の現状を考える(上)
植物の輸入検疫というと、多くの人々は税関の検査と混同するか、せいぜい空港のカウンターで南方果実等の携帯品に関して植物防疫官とのやりとりを思い浮かべられる程度であろう。しかし、植物検疫とは、貨物として我が国に到着する品目に対応するものがほとんどであり、大量に輸入される植物に真摯に向き合って病害虫を検出するという、余り人の目に触れることのない地味な業務であることが多い。現在、地球的な規模で物流が増大する中、植物検疫に求められる要望は多様化の一途をたどるとともに、検疫技術も日々変化し進歩しつつあり、それに対応する専門知識と技術を備えた植物防疫官の業務はさらに重要性を増していると言えよう。大量に輸入される植物といえば木材や穀類であるが、現在このような品目については次第に検疫業務そのものが簡略化される方向にある。それとは逆に、繁殖の用に供する種苗に関しては、輸入後、国内に長期にわたって栽培される可能性が高いことから、より精密な検疫が求められている。植物検疫の現状と課題を報告する。
植物検疫の始まり
1859年ごろ、アメリカから多量のブドウ苗を輸入したフランスにブドウネアブラムシが発生した。ヨーロッパ系ブドウはこの害虫に弱く、10年足らずのうちにフランス全土に蔓延し、ワイン生産量が30%程度に減少したといわれる。隣国ドイツではこの害虫の侵入を警戒し、1872年に「ブドウ害虫予防令」を公布し、繁殖用ブドウ苗の輸入を禁止した。これが世界最初の植物輸入検疫である。
日本は四方を海に囲まれており、病害虫の侵入を防ぐには最も適した国の一つといわれる。また貿易が盛んになり、世界的に病害虫の侵入が頻繁に起こり始めたと見られる時代が、ちょうど江戸期の鎖国の時期に当たっていたため、明治以前はあまり大きな侵入病害虫の洗礼を受けなかった。
しかし、明治以降は物資の移動が激増し各種の侵入病害虫が急速に増加した。このころヨーロッパやアメリカなどの先進諸国が植物検疫制度を徐々に整備・強化したため、わが国から輸出された農産物に関するトラブルが増加した。国内の輸出業者は当初は各業者・組合が自主検査を行い、さらには地方自治体ごとに制度を制定して検査・証明を開始するに至り、1912(大正元)年、アメリカ合衆国が植物検疫法に基づいて輸出国政府に検疫証明書発行を求めてきたため、日本政府は翌年「輸出植物検査証明規定」を制定して検査・証明業務を開始し、1914(大正3)年に至ってようやく輸出入植物取締法が公布され、わが国の植物検疫制度が正式に発足した。
国際植物防疫条約の発効
国際間の物流が頻繁になる中、病害虫の移動防止が技術的に困難となったことと、各国ごとの異なる検疫制度によって貿易が制限されるようになったことを背景とし、世界各国が参加する統一的な条約を制定し、より効果的に病害虫の伝搬を防止しようとする機運が高まり、国際植物防疫条約(International Plant Protection Convention:IPPC)が1951(昭和26)年11月に国際連合の食糧農業機関(Food and Agriculture Organization:FAO)総会で承認されて、翌1952(昭和27)年4月に発効した。その後、1979年と1997年に改正が行われて現在に至っており、世界各国の植物検疫業務は、原則としてこのIPPCで認められた主権行為の一つである。
このような動きと相前後して、我が国では1948(昭和23)年の「輸出入植物検疫法」を経て、1950(昭和25)年には輸出入検疫だけでなく国内の検疫や防疫を統合して扱った「植物防疫法」が制定され、IPPCの改正に伴う変更等を経つつ、現在の我が国の植物検疫制度を支える基盤となっている。
日本の防疫体制
検疫には大きく分けて国際検疫(輸入検疫と輸出検疫)と国内検疫があり、それぞれが密接に絡み合って我が国の植物防疫体制を支えている。検疫業務の主役は国の行政機関の一つである植物防疫所で、その体制は2005(平成17)年4月の時点で5本所(横浜・名古屋・神戸・門司・那覇)・14支所(札幌・塩釜・新潟・成田・東京・伏木・清水・大阪・関西空港・広島・坂出・福岡・鹿児島・名瀬)・59出張所があり、職員数は約900名(うち植物防疫官は約800名)で、機関数は一時に比べるとやや減少、職員数はほぼ横這いまたは漸増傾向にある。
我が国は食糧自給率がカロリーベースでやっと40%といわれており、輸入される植物の品目と総量は膨大なものがある。また我が国は高温多湿な地域が多く、植物の病害虫発生に好適な環境が整っているといわれる。このような状況に対応する我が国の植物検疫体制は、いかに優秀な職員をそろえているとしてもなかなかこれで十分とは言い難いところであろう。
輸入検疫の重要性
植物防疫法に基づき、全国各地の海空港で輸入植物対する検査等を行うことは、島国という特性をもつわが国にとって、海外からの侵入病害虫を防ぐ上で非常に有効かつ重要な役割をもっている。
ここで行われる検査は科学的根拠に基づいたものであり、国際基準に基づいた検疫衛生措置がとられ、有害動植物の危険性の評価(Pest Risk Analysis:PRA)に基づいた適切な検疫措置をとることとされている。旧来の輸入検疫では、有害動植物全てが対象とされていたが、最近では植物検疫対象有害動植物が「検疫有害動植物」に限定されるようになり、蔓延した場合に有用な植物に損害を与える恐れがあるとともに、国内に存在することが確認されていないか、既に国内の一部に存在しているが国によって発生予察事業その他防除に関して必要な措置がとられているもののうちのいずれかとされている。
有害動植物の数は膨大であり、全てについてPRA(危険度評価)を行うことは現実的には不可能に近いので、現状では検疫を必要としない有害動植物として「非検疫有害動植物」をリストアップし、これを検疫対象としないことでこれに対応している。非検疫有害動植物には2000(平成12)年の時点で63種が指定されているが、いずれにせよ検疫現場では目の前の病害虫が何であるのかを迅速かつ正確に判別しなくてはならず、植物防疫官には非常に高度な知識・技術が求められることになる。
検疫対象となる有害動植物については、その危険度に応じた検疫措置をとることが定められ、危険度の高い純に輸入禁止、栽培地検査、輸入時の隔離検疫、有害動植物発見時の廃棄・消毒・選別等の措置が定められている。
通常、植物を輸入しようとする場合はその旨を申請して検査を受けることが求められており、その品目が輸入禁止品の場合には即座に廃棄、返送等の処置が命じられる。それ以外の植物では検査の結果病害虫の付着がなければ合格とされて国内に持ち込みができ、病害虫に汚染されていることがわかった場合には不合格とされ、そのまま廃棄または返送とすることもあるが、多くの場合選別または消毒等の処置がとられる。選別または消毒処理によって病害虫による汚染がなくなれば再検査の後合格とされ、国内への持ち込みが可能となる。
従来、危険度が極めて高い上に輸入時の検査では発見困難な有害動植物が付着する恐れのある植物は輸入禁止の対象とされ、それ以外のものは隔離栽培対象物件を除き原則として輸入検査で対応してきた。しかし、輸入禁止対象に次ぐレベルの重要な有害動植物中には、輸入時点での検査では発見困難であるが、輸出国の栽培地では発見が比較的容易なものもある。これらのものについて、わが国未発生であること、侵入・蔓延した場合わが国の農業生産に重大な影響を及ぼす恐れが極めて高いこと、主な寄主植物が栽培用であること等を要件にPRA(危険度評価)を行い、いくつかの有害動植物の付着する恐れのある植物については、発生国(地域)に対して栽培地検査を要求し、輸出国政府機関による栽培地検査で、その有害動植物が付着していない旨の検査証明書を添付することを求めている。
条件付き輸入解禁も
わが国には現在未発生であるが、侵入した場合はわが国の農業に多大の被害をもたらす恐れのあるチチュウカイミバエのような病害虫については、その種を指定するとともに、その病害虫が発生している地域や国からの宿主植物の輸入が禁止されている。
しかし、輸出国側が一定の検疫条件を満たした場合に限っては、輸入禁止品であっても特に輸入を認める制度(条件付き輸入解禁)がある。解禁の条件には濃密な病害虫防除が行われている地域で生産されたものであり、対象となる病害虫の侵入を防止できる植物検疫措置が確立していて、輸出国政府が行う植物検疫措置および輸出検査を、日本から派遣された植物検疫官が確認していること、また消毒・検査後に再汚染が起きないよう万全の防疫措置がとられており、日本向けの荷口であることを示す一定の表示がなされ、輸出国政府植物検疫機関の発行した植物検疫証明書が添付されている等の項目がある。
条件付き輸入解禁は、1969(昭和44)年4月1日に措置が講じられたハワイ産パパイヤ以来50品目以上に及び、現地での検疫業務のために年間約70名の植物防疫官が輸出国に派遣されている。時折店頭で見かける輸入果実等の中に、「Plant Quarantine」と書かれた小さなシールが貼られていることがあるが、あのシールは日本に輸出するために特別な措置を講じたことの証明である。