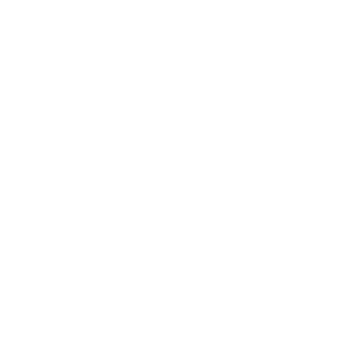皮から革へタンニン鞣しは健在です
2010年8月2日
東京農業大学短期大学部 醸造学科 教授
醸造学科食品微生物学研究室
前副学長
中西 載慶
主な共著:
『インターネットが教える日本人の食卓』東京農大出版会、『食品製造』・『微生物基礎』実教出版など

タンニンは、多くの植物の樹皮、葉、実、根などに含まれる成分で、種類も多く複雑な構造をもつ物質です。身近なところでは、渋柿、栗の渋皮、赤ワインの渋みや苦味の成分がタンニンです。化学の分野では、物質の化学構造を基に分類、命名した名称を優先して用いるため、最近では、タンニンとはいわずポリフェノールと総称されています(本誌No.15〜17参照)。しかし、食品学では、渋み(苦味)に関係する成分でもあることから、便宜上今でもタンニンという名称が広く使われています。タンニンの特性を簡潔にまとめると、タンパク質、コラーゲン、金属などと容易に結合する性質を持つポリフェノールの一種ということができます。タンニンの語源は、英語のtan(皮をなめす)に由来しています。語源のとおり、古代から動物の皮なめし(鞣し)に用いられてきました。その理由は、タンニンが皮のタンパク質やコラーゲンに結合することや皮繊維の間に沈着することにより、皮に防腐性、耐熱性、耐薬品性が付与され、また柔らかく使い易くもなるからです。一般に、鞣されていないものを皮、鞣されたものを革というそうです。毛皮のように鞣されているのに皮の字を使っている例外もあります。
タンニンを用いた皮鞣しは、30以上もの工程と多くの時間、手間のかかる作業ですが、その工程の概略を紹介します。まず、塩漬保存した皮を、塩抜き、脱毛します。次いで、その皮を低濃度のタンニン溶液槽に一定期間浸し、それから順番に濃度の高い槽へと移しながら約1ヶ月位をかけ皮鞣しを行います。その後、乾燥、ローラーによる引き伸ばし作業などを経て、皮が革になるのです。現在では、安価、短時間な作業工程のクロム(硫酸クロム)鞣しが主流ですが、タンニン鞣しならではの革の魅力があり、現在でも連綿と行われています。皮鞣しに使うタンニンは、ミモザ、ケブラッチョ、チェストナット、オークなどの植物の樹皮や木質部から抽出されています。タンニンは鞣し以外にも、医薬や化学原料としても利用価値の高い物質で、身近なところでは、黒インキや草木染の染料として、また、古くは、お歯黒の染料などにも使われていました。
ところで、植物は、なぜタンニンを多く含んでいるのでしょうか? 植物も生き残るために多くの生体防御機能を持っています。タンニンもその機能の一つで、細胞組織を強固にし、苦味や渋味により動物や昆虫に食べられ難くする役目を持っています。また、タンニンの抗菌力やタンパク質を変性させる性質は、病原菌の感染を防いだり、昆虫の消化酵素を変性させ昆虫の攻撃から身を守る役目をしています。自然界は、本当に様々な生物の「せめぎ合い」、「しのぎ合い」、そして「微妙なバランス」の上に成り立っているのです。タンニンといえば、苦い話、渋い話、飲食の話がつきものですが、後回しになってしまいました。それらの話は次号以降ということに。
このシリーズも今回で50回目となりました。本誌は年10回発行ですから、丁度丸5年書き続けたことになります。うろ覚えの知識をもとに、関係書を読み直したり資料を調べ直したりもしてきました。結局、このシリーズで一番恩恵を受けたのは私自身のようで…遅まきながら、本学創設者の榎本武揚の書「学後知不足」(学びて後足らざるを知る)の言葉が、改めて、意味深く心に響いているこの頃です。ひとムチ入れて、次号「タンニン(2)」につづく。