FooDoo
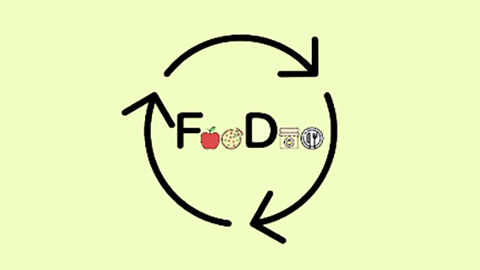
活動団体
FooDoo
プロジェクト名
食品廃棄を減らそう!
学外協力者
豊国園(山梨県)など
活動の動機、背景、目的
昨年度までの活動では、みつ症の梨や傷がつき廃棄されてしまう桃を、農大周辺の飲食店とコラボレーションしてスムージーやかき氷、サンドイッチ等のパンにして販売してきた。他にも同じように産地で廃棄されてしまう作物があると考え、今年度は新たに協賛をいただいた学外協力者の方々と共に食品廃棄を削減するような活動を行うことで、廃棄量の減少に貢献したい。また、引き続きInstagramでの食品ロス削減のアイデアの投稿、桜丘小学校での食品ロス削減授業や中野マルイでのアンケート調査、今年度開催予定の料理研究家とのべジブロス料理教室を通じて、家庭系食品ロスの削減に繋がる方法を広めていきたい。
産地では、食べられるのに廃棄されてしまう農作物が数多くある。その中でも昨年から関わりのある農家さんに提供していただいている桃、梨、新たにご協力いただく春キャベツに注目する。桃は繊細な果物であり、傷がつくとすぐに痛み、三流品となってしまう。三流品となった桃は、価格が大幅に下がるなど、販売が困難になってしまう。梨はみつ症になると食べられるのに廃棄されてしまう。春キャベツは梅雨の水分吸収や収穫の遅延などが理由で葉や芯が割れてしまうことで商品価値が失われてしまう。このように、廃棄されてしまう作物が多くあることで、農家の生産性の低下や廃棄による環境への負荷が考えられる。
活動初年度に行ったアンケート調査にて食品ロスの認知状況は高いが行動に移せていない消費者が多いことが分かった。しかしながら、過去2年間の中野マルイでのアンケート調査や桜丘小学校での食品ロス授業では、消費者が無意識的にてまえどりを行っていたり、野菜の皮をチップスにしたり、大葉等はキッチンペーパーを水に浸して保存したりする等、実際に習慣化されてきている箇所もある。この変化を柔軟に捉え、家庭内で簡単に食品ロスを削減するためのアイデアを提供し続け、実行に移すためのきっかけとなることが家庭系食品ロスの削減に繋がると考える。
価格をつけにくかったり、廃棄されたりしてしまう作物を加工して商品として販売し、廃棄量を減少させること。家庭で実践可能な食品廃棄を削減する方法をInstagramを通じて発信し、廃棄削減活動を実践してもらい、家庭内廃棄量を削減すること。
活動の具体的内容
"活動を大きく3つに区分すると、1.産地廃棄の商品化、2.家庭内系廃棄の減少活動、3.じゅんかんチャレンジへの参加である。
1. 産地廃棄の商品化
昨年から提供いただいている桃、梨に加えて、新たにメンバーに関わりのある安西ファームの春キャベツを使用した商品を制作する。今年度の活動においては、(1)飲食店コラボレーション、(2)レトルトカレー化、の2パターンでの商品化を目指す。
(1)飲食店コラボレーション
① 昨年作成した桃・梨の資料及び春季休業中に農家さんから得たキャベツの特徴をまとめた資料等を活用し桃、梨、春キャベツについての知識を深める。
② Onkaさんに加えて、他の飲食店でのコラボ先を探す。コルティ経堂で10月頃にみつ症梨を使用したイベント開催に向けて、コルティ経堂や各飲食店に相談する。(イベント開催が難しい場合は来年度に持ち越す)
③ 桃、梨、春キャベツを使用した商品案を練る。商品化できるものをいくつかレシピを考えたうえで各飲食店に提案し、商品化する。選択された商品案を農家さんに相談し、決定する。
④ 商品の宣伝・販売をする。宣伝はInstagramやポスター、リーフレットを使用する。フィードバックのために購入者向けのアンケートQRコードを作成する。警察署に公道でのチラシ配布の許可を取り、一部販売期間、メンバーでチラシ配布を行う。
(2)レトルトカレー化
食品ロスの食材を使用してレトルトカレーを販売しているMOTTAINAI BATON株式会社さんと農大サポートさんと共に、安西ファームさんの春キャベツをレトルトカレー化して販売する。
① FooDooがMOTTAINAI BATON株式会社さんに商品案と企画書を提出する。MOTTAINAI BATON株式会社さんが工場を選定する。農大サポートさんに販売先や方法に関するご相談に伺う(4月)
② 試食会を通じて商品とパッケージデザインの決定。
③ 5月末~6月頭に春キャベツの規格外品が提供されるため、6月中に商品納品。
④ 各協力先の持つ販売先以外の販売先を探し、確保する。①の企画書にてFooDooの考えた販売戦略で販売を行う。そのための広告やポスター、フィードバックのために購入者向けのアンケートQRコードを作成する。
2. 家庭系廃棄の減少活動
家庭内のロスを減らすためのレシピや保存方法、産地廃棄についてInstagramを用いて発信する。今年度はInstagram班を創設し、その班員を中心に企画を考え、インサイトを研究し、投稿内容や投稿時間を工夫することで、フォロワー数の増加に努める。
① Instagramでの投稿を制作する班を作り、企画の決定など投稿に向けた準備をする。
② 投稿内容について調べたり、実際に行ったりして投稿用の写真を撮っておく。
③ 投稿するための画像や文章を作成し完成したら、投稿する。
④ 産地廃棄の実態や商品化で私たちが感じたことを消費者へ伝える。企画以外にも中野マルイでの活動報告、じゅんかんチャレンジで知り合った農家さんからの廃棄野菜の宣伝を通じて食品廃棄の問題や改善の周知を図る。
3.じゅんかんチャレンジ
家庭系食品ロスの削減方法を周知する手段の1つとして、世田谷すみればネット(じゅんかんチャレンジ)の方々と共に世田谷区の地域住民の方々を対象に、食品ロス削減の料理教室や家庭科の授業の一環として区立桜丘小学校での食品ロス授業を行う。
① 6月開催予定の料理教室のために、じゅんかんチャレンジ代表の大江さん、野菜を提供してくださる中杉玲子さん、料理研究家の東明日香さん、桜丘小学校の副校長先生と家庭科教諭の方々との打ち合わせを重ね、方向性を定める。
② 対象や内容が決まったら、桜丘小学校や世田谷区桜丘エリアの自治体の掲示板等を通して、料理教室の宣伝を行う
③ 料理教室の開催
④ 2‐3月に、一昨年度より行っている食品ロス特別授業を行う。"
