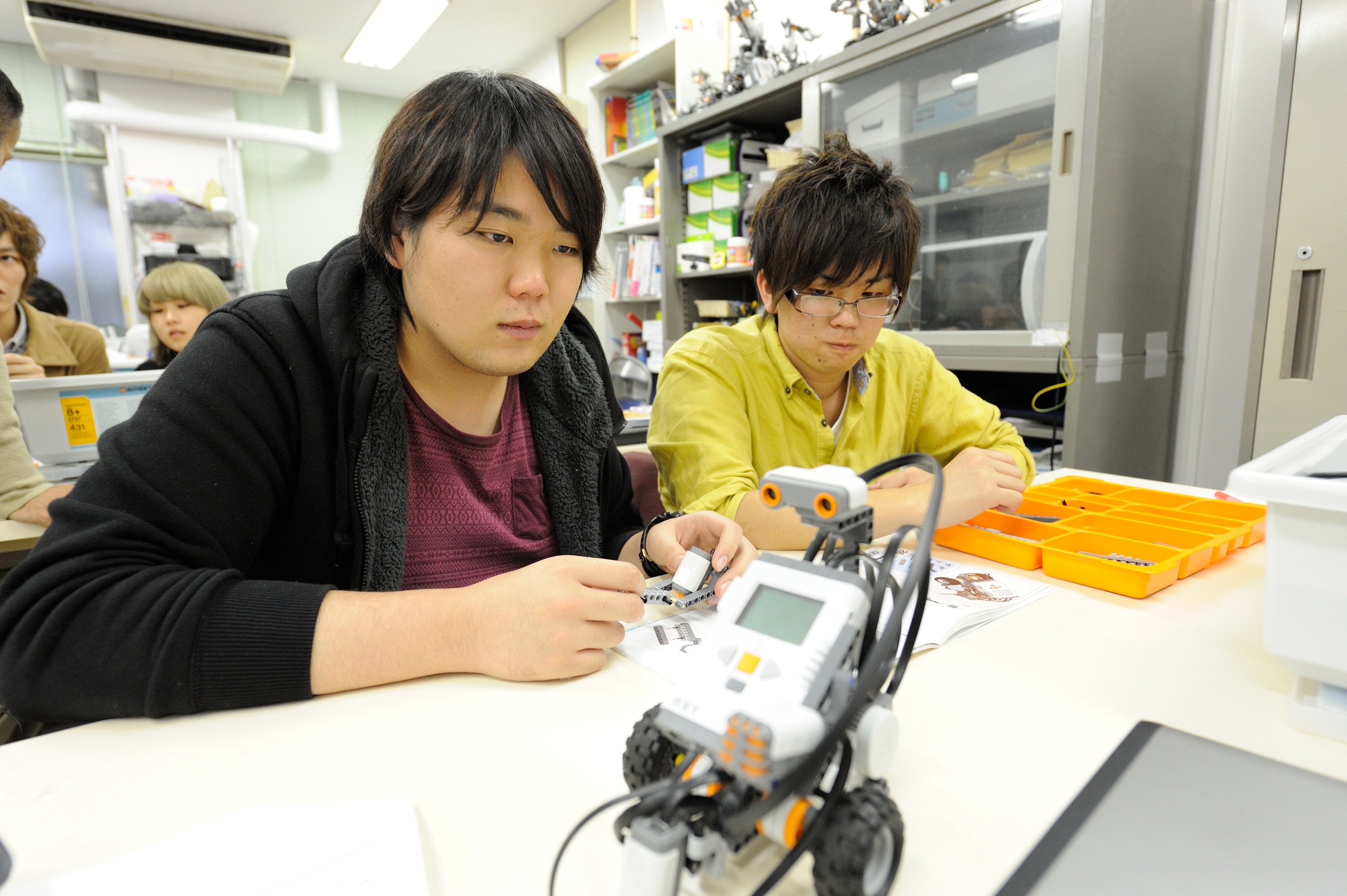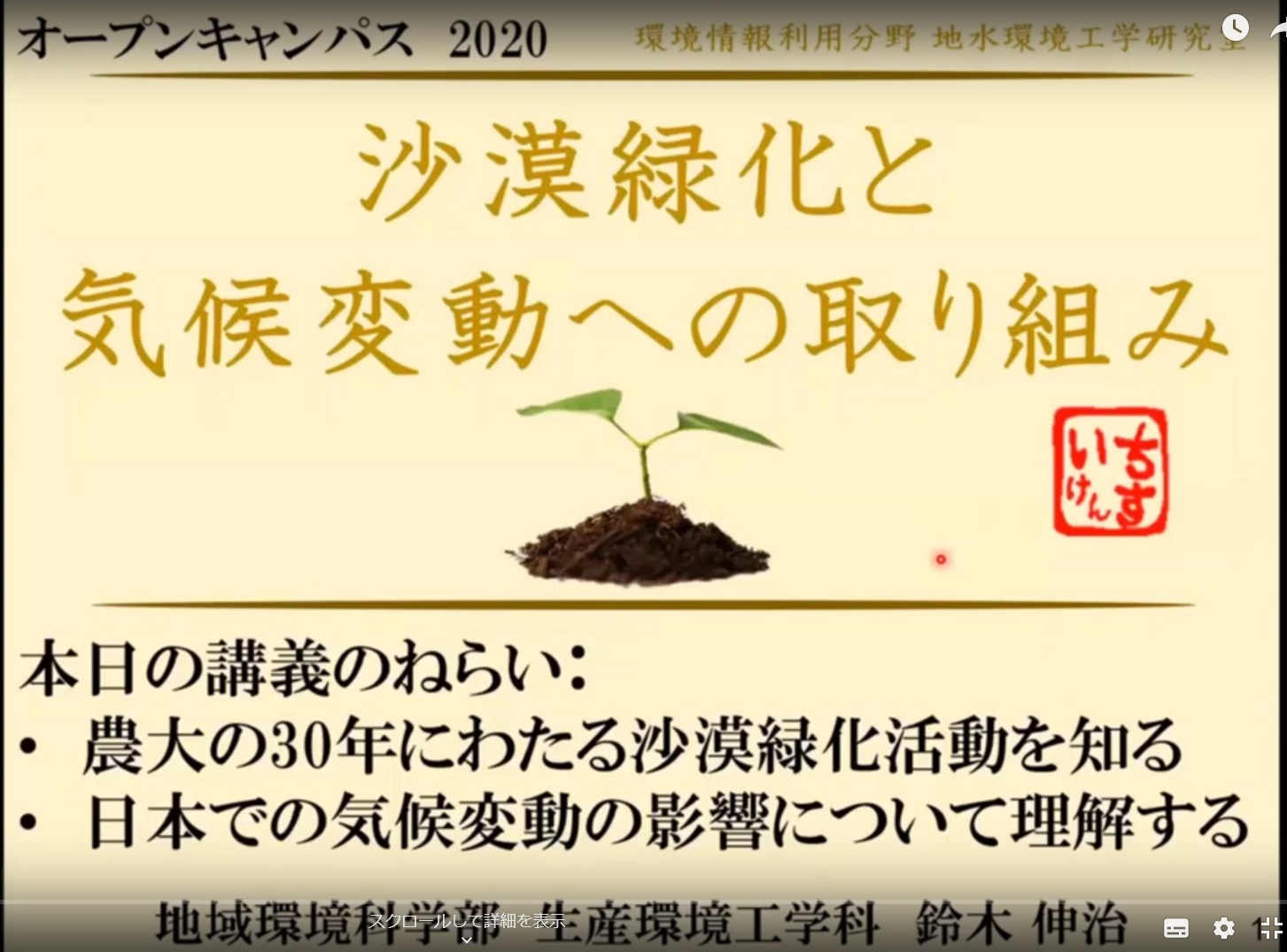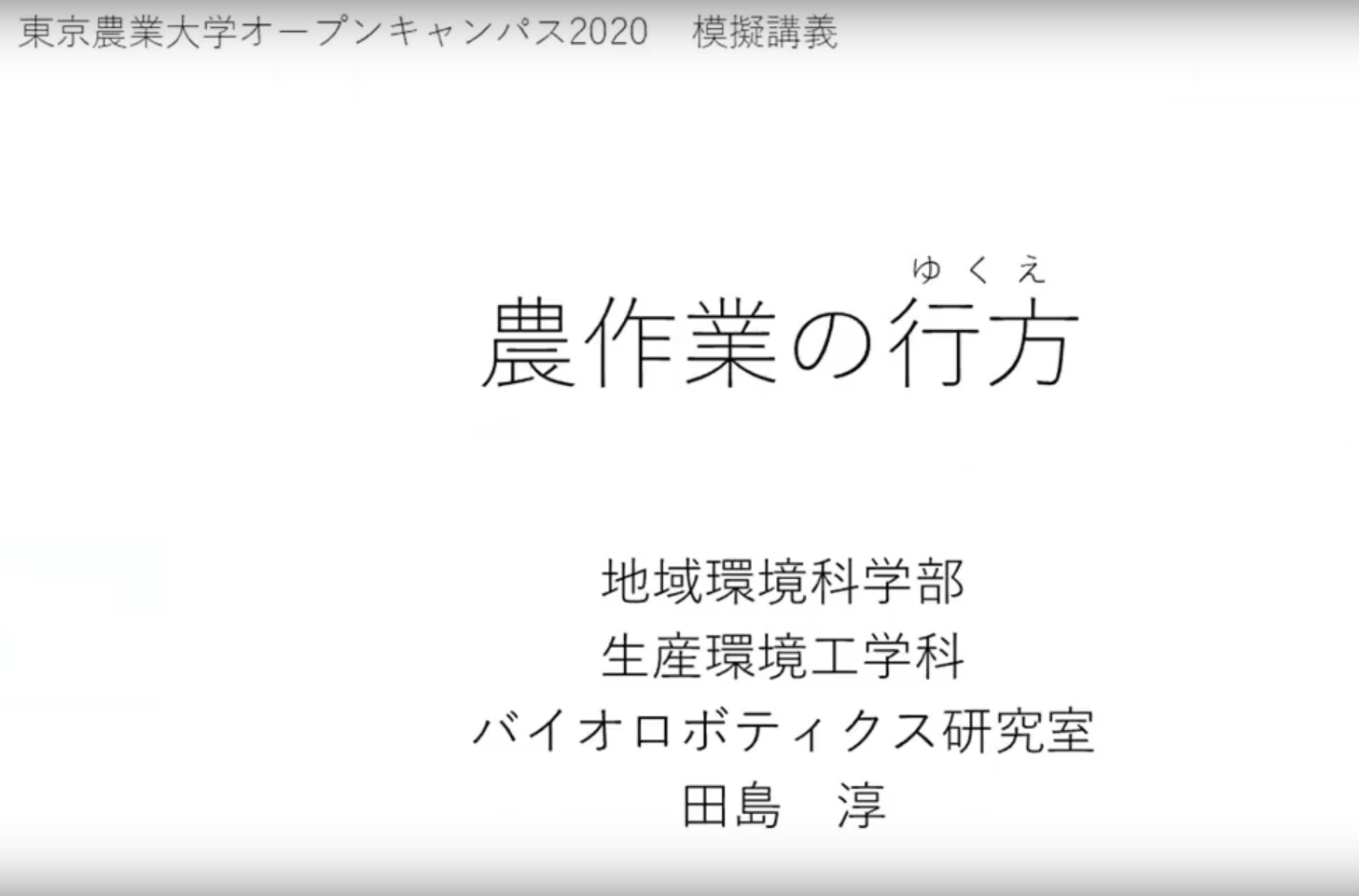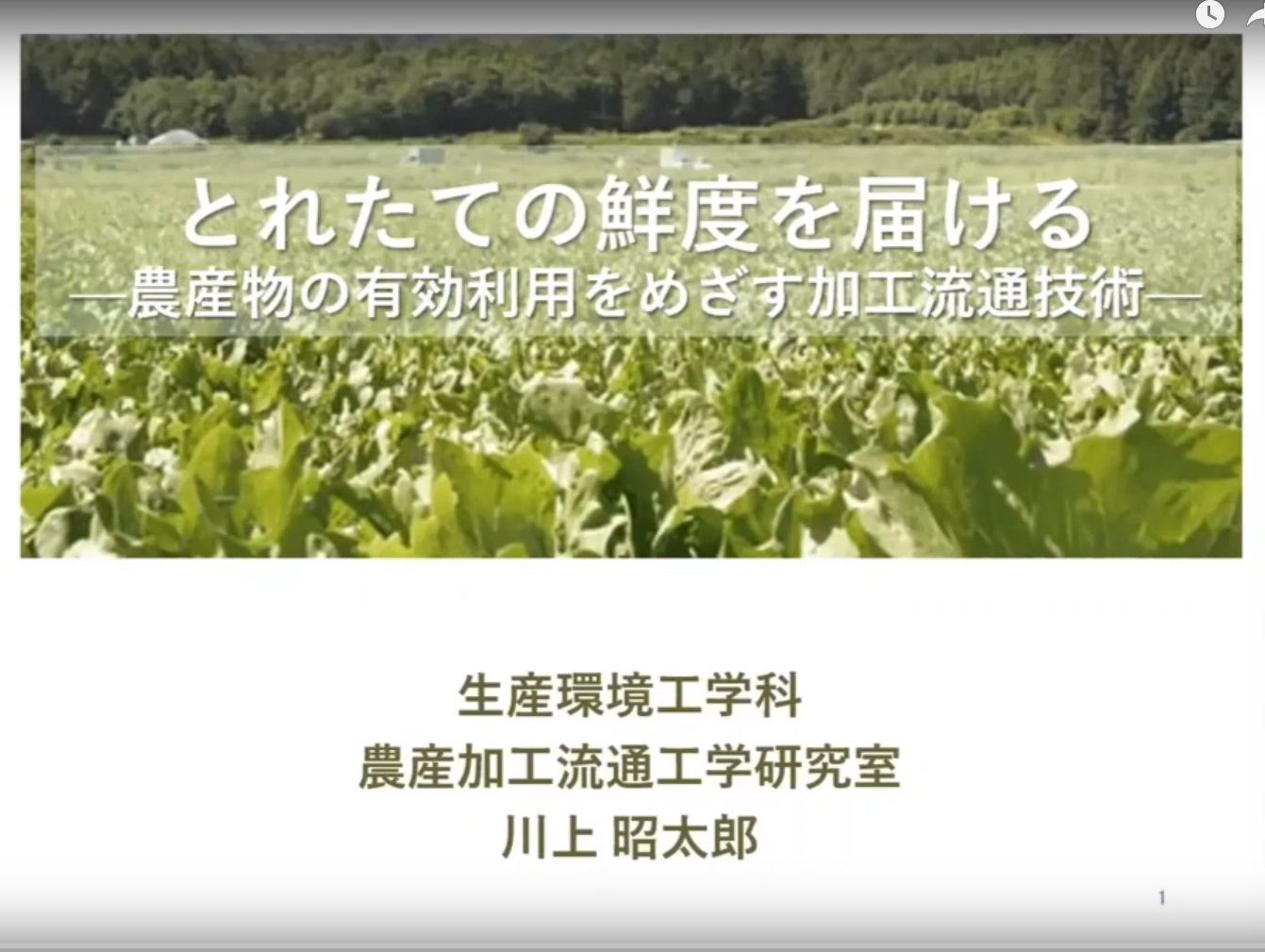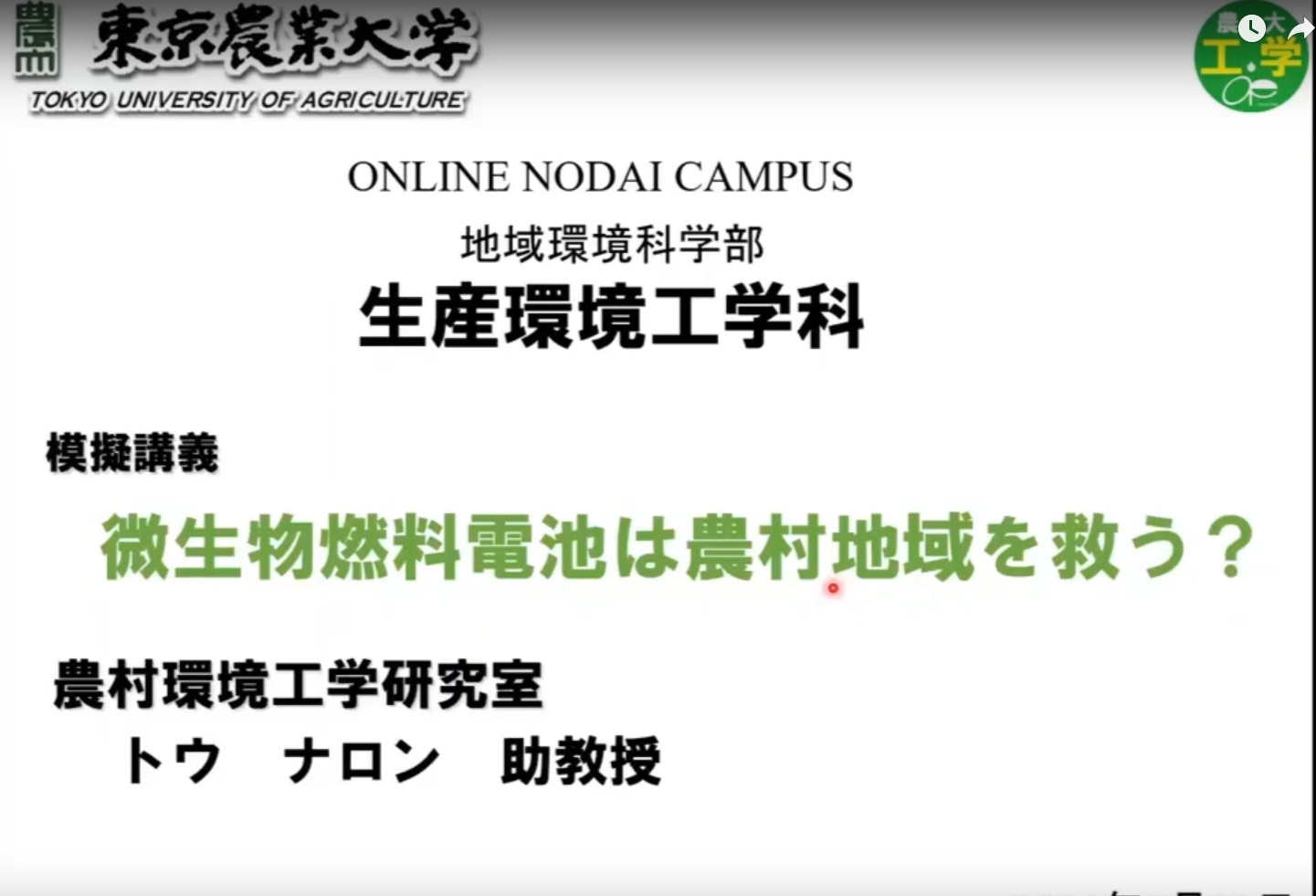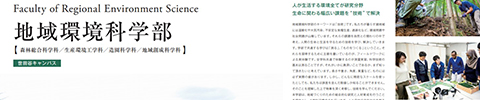生産環境工学科
世田谷キャンパス
伝統ある農業工学に、AIやデジタル技術を掛け合わせ、サイバー空間と現実世界を融合させた次世代社会「Society5.0」の実現に向けた教育・研究を進めています。「農業×工学×データ」の力で未来農業の基盤を築き、自然とともに生きる持続可能な社会をめざしています。
※生産環境工学科は2024年度から研究室体制を変更します。2023年度入学生までの学科体制はこちらです。
学科基本情報
生産性と環境保護の調和をめざして
本学科は、農業生産の基盤づくりや機械の活用について、80年以上にわたって教育と研究を重ねてきた、伝統ある学科です。自然環境に働きかけながら行う農業において、生産性を高めつつ、いかに環境への負荷を抑えるか――この問いに向き合い続けることが、本学科の変わらぬテーマです。

Society5.0時代の農業を切り拓く
いま、地球規模で環境問題が深刻化する一方で、日本では農業や農村の衰退が大きな課題となっています。こうした状況の中、本学科では「農業の生産と環境をどう両立させるか」という視点から、環境に配慮した持続可能な農業生産技術の研究を進め、日本と世界の食料・環境問題の解決に取り組んできました。
近年は、AIやテクノロジーの力で社会課題の解決と経済成長を両立する「Society5.0」という新たな社会像が注目されています。その中で、スマート農業やフード&アグリテックなど、農業のあり方も大きく変わろうとしています。
こうした時代の変化に応えるため、本学科では、生産環境や生産システムの新しいかたちをつくることにも力を入れ、次世代の農業を支える「生産環境工学」の学びを深めています。
地域から地球まで。課題解決に挑む力を
本学科の教育目標は、これからの食料・環境・資源・エネルギーといった多様な課題に対して、「土と水」の機能や文化、そして「農」のもつ多面的な価値を原点に、人類の暮らしと未来を支える人材を育てることです。地域から地球規模まで幅広い視点で、革新的な技術にも柔軟に対応できる力を養います。
そのために本学科では、2つの教育コースを設けています。ひとつは、農業や農村の課題に対し、工学的・環境科学的な視点から解決をめざす【生産環境コース】。もうひとつは、将来、設計や施工管理の責任者として活躍する「技術士」の資格取得をめざす、JABEE(日本技術者教育認定機構)認定の【技術者養成コース】です。
これらの教育を通じて、本学科ではデジタル技術を活かしながら、次世代の農業生産システムを支える人材を育成しています。
教員・研究室紹介
農業環境工学分野
スマートアグリ分野
数値解析アプリ
PICK UP 教育関連
授業紹介
1年次
必修
情報基礎(一)
1人1台ずつパソコンを用いて、電子メールや学生ポータル、図書館の検索システムの利用法をはじめ、文書作成、表計算ソフト、インターネットの情報検索などの基本操作を習得する授業です。また情報処理や解析に必要なプログラミングに関する基礎技術の演習をおこない、今後の課題学習や研究室活動の際にコンピュータを効果的に活用するために必要な知識を身につけます。
2年次
必修
測量実習
2年次前期のこの実習は、同じく前期開講の授業「測量学」と関連しており、理論を実践にリンクさせながら授業を進めます。トラバース測量、平板測量、水準測量を中心とした測量技術の習得をめざして、屋外で実際に測量をおこない、方向角や座標の計算、製図にも取り組みます。また測量機器のひとつであるトータルステーションやGPS(汎地球測位システム)を利用した測量技術も学びます。
2年次
必修
基礎実験
2年次前期に選択する専攻分野で必要とされる実験技術の基礎を習得する授業です。地域資源利用分野では水と土の基本的性質とその測定技術、環境情報利用分野ではプログラミングの基礎と土壌や大気の物理量の収集・解析法、環境基盤創成分野ではコンクリートの材料特性と実際の水理現象、機械システム創成分野では耕うん機の構造とロボティクスおよび農産物の加工・品質評価技術についてそれぞれ習得します。
模擬講義
PICK UP 研究活動
進路状況
専門技術を活かし、地球環境改善・地域活性化に貢献
食・環境・農業分野で、土木・機械・情報などのエンジニアリングを学んだ人材が幅広く活躍しています!生産環境工学科では、食・環境・農業に関する様々な問題を解決する手法として科学と技術を重視し、農業土木・機械・情報の専門的知識と技術を持った人材を育成しています。その専門性を活かし、公務員や各種一般企業、教員などで活躍しています。
主な進路先
[公務員] 農林水産省、国土交通省、経済産業省、東京都庁、愛知県庁、長野県庁、埼玉県庁、茨城県庁、千葉県庁、岐阜県庁、秋田県庁、新潟県庁、神奈川県庁、千葉県庁、福岡県庁、福島県庁、横浜市役所
[サービス業 建設造園コンサルタント] 東京水道サービス、上伊那広域水道用水企業団、日本工営、フジヤマ、NTCコンサルタンツ、内外エンジニアリング、サムシングホールディングス、東京設計事務所
[ サービス業 情報・通信] NTTコムエンジニアリング、NTTデータビジネスシステムズ、富士ソフト、NECソリューションイノベータ、キャノンシステムアンドサポート、農中情報システム、システムクエストクレアビジョン、アルテニカ、ダイナテック、アイレット、こまちソフトウェア、日立社会情報サービス
[ 建設] 鴻池組、京王建設、金杉建設、佐田建設、三機工業、NIPPO、鉄建建設、日特建設、大林道路、前田道路、西松建設、大成建設、東鉄工業、日本国土開発、竹中土木、世紀東急工業、日特建設、日本道路
[ メーカー その他] 井関農機、サタケ、カワサキ機工、ヤンマー、フソウ、スガノ農機、エスビック
大学院との連携
農業工学専攻 博士前期・後期課程
農業工学専攻は、環境に配慮した地域資源の有効利用と循環型社会の構築を理念とし、これらを技術的に具現するために農業土木および農業機械分野の学問を基軸とした実践的な教育研究を行い、現場での高度な技術開発・問題解決と学術的な研究を両立できる能力を持った人材の養成を目的とします。

卒業生の声
資格取得
- ・教員免許:高等学校(農業・理科),中学校(理科,技術科)
- ・技術士補(技術士一次試験免除)
- ・測量士補 など
- ※必要な科目や要件を満たしていなければなりません