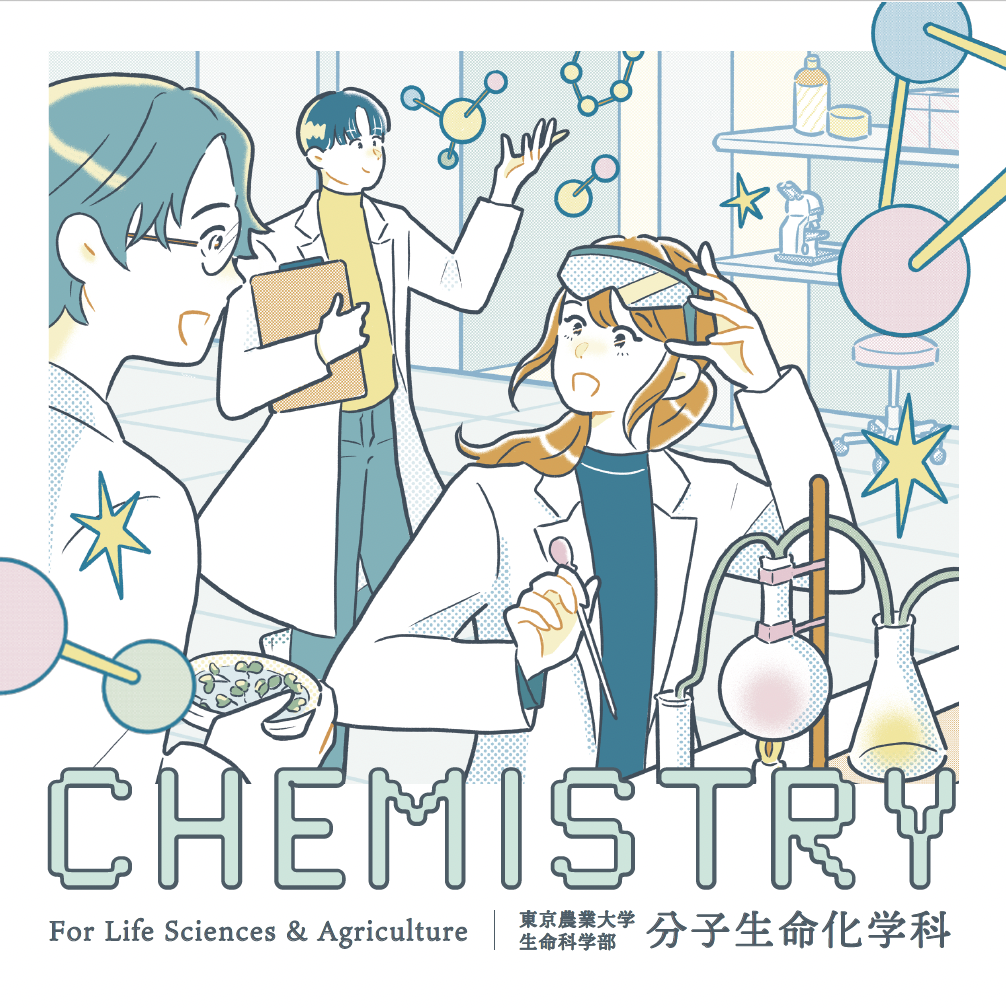分子生命化学科
世田谷キャンパス
生物圏のあらゆる“生命”現象には、原子・分子が関わっています。この原子・分子の働きを化学的な視点で解明していくことで、これからの生命科学の可能性をより広めていくことをめざしています。精密有機合成、天然物化学を中心に、高分子化学、分析化学を基盤とした教育・研究を通じて医薬・農薬・動物薬およびバイオプラスチックの開発への道を拓きます。
学科ニュース
学科基本情報
伝統的科学としてのケミストリーの視点
化学は厳密な再現性・定量性及び論理性を有する物理学・数学等の伝統的科学の一分野です。19世紀の代表的な化学者であるリービッヒの最小律に示される様に、化学は農学・生命科学領域と密接な関係にあり、それから現在に至るまで農学・生命科学領域に本質的な貢献をしています。
現代は広範囲の多様性と激しい変化の時代です。化学分野の研究・教育も既存の構成に捕われず柔軟に時代に対応する事が求められています。

研究者を志向して大学院進学も視野に
本学科は伝統的な化学の視点を保持しながらも生命高分子、分子設計等新しい観点を導入し、時代の変化に捕われない普遍的な価値をもつ研究成果の発信と人材の育成をめざしています。入学初年度には化学をはじめ、幅広い理系基礎教育科目を充実させて開講し、その後は無機化学、有機化学、分析化学などの中核となる化学系科目とともに高分子化学実験や天然物化学実験などの基盤となる実験を開講します。さらに生物学への化学の応用展開をはかる領域として、バイオプラスチック(生分解性プラスチック)や医薬・農薬の開発に関連する科目も学べることが特徴です。
より高度な知識・技術の修得をめざし、大学院博士前期課程 (2年間)への進学も視野に入れれば、6年間を通じたカリキュラムとして、3年次までの前半を基礎・教養教育の課程、4年次と大学院2年間の後半を高度な専門教育の課程ととらえた教育体制も整えています。
有機化合物を対象とする研究・開発機関への道を拓く
1年次後期までに危険物取扱者免許(甲種)を取得するのに必要な科目群を履修できるように配置し、在学中の資格取得を奨励します。研究室に所属するのは3年次からですが、研究室では自然界からの物質の単離・構造決定、化学合成、生体機能解析、応用展開とあらゆる化学・生物学的な視点からバリエーションに富んだ研究を展開します。
卒業後は、確かな理系の基礎知識・技術を身に付けた人材として、香料・材料関連の化学系企業、製薬・農薬会社などの化学を対象とする幅広い企業への進出が期待されます。大学院へ進学する場合は、広い視野と応用力を身につけた「化学と生物の専門家」の育成をめざします。
教員・研究室紹介
有機化学分野
分子機能解析学分野
スポットライト
卒業生の声
PICK UP
3年次
専門選択
生命高分子学
生命を担う高分子は実に多彩です。まず、DNAやタンパク質そして多糖などが、細胞を構成し巧みに駆動していることを学びます。また、各種高分子の構造や物性機能を多角的に理解します。DNAやタンパク質の「生合成の仕組み」と石油系高分子の 「化学合成の仕組み」の違いがわかれば合格です。さらに、バイオプラスチックの医療や環境分野へ応用する道筋を楽しみます。
3年次
専門選択
生物無機化学
無機元素の中には、生物に対して必須である元素がある一方で、毒性を示す元素もあります。この必須性や毒性など元素が生物に与える機能は、生体内での元素の化学形態によって決まります。この科目では、生体有機分子との複合体など無機元素の生体内での存在化学形態を学びます。そして、無機元素の生物に対する機能のもととなる分子基盤を理解していきます。
3年次
専門選択
天然物合成化学
抗生物質や抗がん剤となりうる有機化合物が天然から見いだされていますが、それらの未確定な構造の決定や、実用化のための大量合成には有機合成化学的手法が不可欠です。目的の化合物を化学合成するために、どの炭素と炭素を連結すればよいのか、どの官能基をどんな反応を用いて変換すればよいのかなど、知的なパズルによって分子を精密に組み立てる手法を学びます。