食品安全健康学科
世田谷キャンパス
食の流通のグローバル化によって、市場には新たな食材や加工食品があふれ、人々は豊かな食文化を楽しむ一方で、在来・外来の食材が食の安全を脅かす危険から自分たちを守る必要が生じています。こうした「食の安全・安心」をはじめ「食の機能と健康」を科学的に解明する研究拠点に、社会の期待が高まっています。
学科ニュース
学科基本情報
人々の健康に貢献する食品の科学的情報を発信
「食」とは、私たちの生活を営む源であり、「食品」とは、その具体的なモノの数々を指すことばです。従来、この食品そのものを総合的に理解することを目的に教育・研究をおこなってきた栄養科学科食品栄養学専攻を発展的に改組し、食品の安全面と健康増進に役立つ機能に対する幅広い知識・技術を得るために、平成26年4月から開設したのが「食品安全健康学科」です。
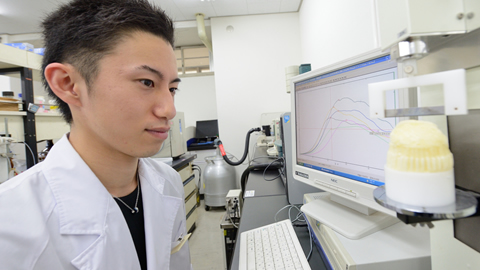
本学科がめざす領域は、社会にあふれる食品に対して、衛生学的な視点からの「安全・安心」を検証するという従来の枠にとどまりません。「食品の機能」が「生体の機能」にもたらす影響の未知の部分を解析し、「食品の安全利用」とともに、人々の健康に貢献する科学的な情報を発信していくことをめざします。
化学・生物学の基礎力を食品の生理活性理解の土台に
本学科では食品の安全と機能の両面に深い理解をもつ人材の育成をめざしていきます。1・2年次は、化学と生物学の基礎学力習得のための講義や実験に重点をおきます。そして食品機能学、食品加工保蔵学、公衆衛生学などの専門科目を初歩から学び、病原微生物学や分子生物学などの科目によってミクロのレベルから食材の安全性と機能性を理解します。
3年次からは研究室に所属します。研究活動を通じて、それまでの講義・実験で得たものを食品の生理活性への理解に生かします。また外部からも教員を招いて、輸入食品の流通に対する知識や、リスクマネジメント論などの専門的な領域も学習していきます。
4年次には卒業研究をおこない、各研究分野での成果を検証します。研究室内外でのコミュニケーションなどをもとに、実社会で必要とされる問題解決能力、企画・提案力、プレゼンテーション能力を身につけたうえで、研究成果の発信をめざします。
食の安全・安心に基盤をおいた2つの分野
本学科では学びの専門分野として「食品安全科学分野」と「健康機能科学分野」の2つを教育・研究の柱としています。食品安全科学分野では、食品自体の有害因子の検出と生体影響評価やリスクマネジメント、食品の保蔵・機能強化加工法、摂食嚥下まで多面的に研究します。健康機能科学分野では、食品の機能性成分や危険因子が生体に与える影響について、モデル細胞や疾患モデル動物を用いた遺伝子発現から代謝レベルにいたるまでを研究します。
教員・研究室紹介
食品安全科学分野
健康機能科学分野
PICK UP
2年次
必修
分子生物学
様々な生命現象をDNAやタンパク質といった「分子」の機能を通じて理解することを目的としています。ここで学んだ知識は専門科目を理解するための基礎知識となります。他の学部学科でも同じ科目が開講されていますが、当学科では、食品研究に携わる教員が講義するため、食品成分の生理機能や生活習慣病の発症メカニズムなどと関連させた内容であることが特徴です。
3年次
必修
病理学
病理学は、「病気の理屈」を学ぶ学問です。病気は、体を構成する細胞レベルの異常に由来していきます。病理学の講義では、各レベルでの異常を様々な手法で検出し、背景機構を解析し、適切な予防・治療・進展阻止の方法を探索する方法を学びます。食品や健康に係わるどのような職業でも病理学で学ぶ知識は有用です。
3年次
必修
感性科学
感性科学は、心理学から脳機能にいたるまでの幅広い領域が対象です。人は、食品を口腔内で知覚することで「おいしさ」という感性的な評価をしますが、このことを食品の物理的特性としてテクスチャーを定義し、さらに味覚について生理学や分子生物学の知識を基盤にそのメカニズムの理解をめざします。そして食べる人にとって安全でおいしい食品とは何かということを多角的に講義します。
卒業後の進路
大学院との連携
食品栄養学専攻 博士前期・後期課程
食品栄養学専攻は、食品の開発や安全性確保、医療における食事療法などの専門的な研究を行い、さらに食品学および栄養学領域において豊富な専門知識・技術と研究能力を持った研究・産業発展の指導的立場を担える高度な専門家となる人材の養成を目的とします。




