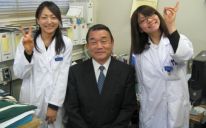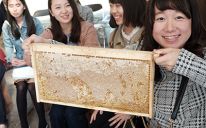醸造技術分野 発酵食品化学研究室
食酢、チーズ、くさやなど様々な発酵食品の製造中や保存中における成分変化に寄与する微生物群の動態について解析している。解析した多様な成分と微生物群の関連を統計的に見出し、鍵となる微生物の生理を分子レベルで明らかにすることで、伝統的発酵食品の科学的側面の解明と新規発酵技術の開発を目指している。
KEYWORDS
発酵食品、水産発酵食品、チーズと乳酸菌、代謝解析、食酢と酢酸菌、ゲノム解析、フードミクス、発酵食品と放線菌、抗生物質
微生物側の視点に立ち発酵食品の未来を創る
発酵食品化学研究室を動画で紹介しています。

研究室トピックス
所属教員
学生の主な研究テーマ
- チーズ分離細菌を用いた白カビ熟成チーズの模擬的熟成
- ウォッシュチーズから分離した好塩性・好アルカリ性乳酸菌の好気代謝能に関する研究
- 食酢醸造用酢酸菌の酢酸発酵時における不活性型アルコール脱水素酵素の役割
- 酢酸菌のセルロース合成に関する研究
- 熟成チーズ、くさや、ふなずしなどの成分分析と発酵微生物との関連
- 発酵食品からの特徴的な微生物の分離と微生物叢の解析
- 熟成と品質劣化の観点からの発酵食品のフードミクス
- 伝統水産発酵食品「くさや」と製造に重要な「くさや汁」に関する研究
- 伝統水産発酵食品「くさや」から分離された放線菌の抗生物質生産に関する研究
- 伝統伝統発酵食品「ふなずし」からの微生物の分離と発酵現象の解明
- 八丈島産「くさや」発酵槽から分離した乳酸菌の微生物学的特徴と発酵乳製品製造への応用
FREE TALK
微生物の世界へようこそ
発酵食品製造にはスターター菌だけではなく様々な微生物の力が必要不可欠です。そのようなスターター菌以外の微生物はどのような働きをしているんだろうと非常に興味がありました。そこで、チーズや漬物、くさやなどの発酵食品から微生物を分離してみると、実に様々な微生物が生息しているということを自分の実験で調べることが出来ました。3年間の座学講義では正直なんとなく想像でしかわからなかった微生物の実態を、自分の分離操作で知ることが出来たことは貴重な経験です。分離した微生物について、同定や生理試験などやることは沢山ありますが、分離した微生物が発酵食品の未来を担うと考えると、とてもワクワクします。
「変わり者」の乳酸菌を追い求めて
私達は熟成チーズから分離した乳酸菌の研究を行っています。乳酸菌は普通、酸性で塩のない場所を好みます。しかし私達が探しているのは、それとはまったく逆!アルカリ性が好きで塩も好き、そんな一風変わった乳酸菌です。どのチーズにいるのか?どこからきたのか?チーズにどんな影響を与えているのか?解明しなければならないことは山積みです。少しでも成果を上げようと力を尽くしました。
この乳酸菌に関して,私が1年間行った実験の成果は微々たるものかもしれません。しかしこの研究活動を通じて。「未知のものを、自分の手で解明した」という大きな達成感を得ることができました。この経験は一生ものです。
くさやのひみつ
「くさや」は独特なにおいがあるせいか、どちらかというと敬遠されがちな発酵食品だと思います。しかし、「くさや」の歴史と製造過程を詳しく見てみると、とても興味深い発酵食品なんです。「くさや」製造に不可欠な「くさや汁」は特に興味深く、100年以上使い回していたり、天然の抗生物質が入っていると言われていたり・・。歴史的に謎が多いことにビックリしました。「くさや汁」は一度失うと二度と同じ物を作ることが出来ないため、昔は嫁入り道具としていたり、今でも各加工業者さんの家宝として守られているそうです。そんな「くさや」の謎を解明するべく「くさや」製造業の方と密に連携を取って成分や微生物、抗生物質について研究しています。研究によって様々なことが分かってきているので、改めて「くさや」の魅力を感じています!だから・・色んなところで罰ゲームとして使われてるのは本当に心が痛いですね。あのにおいは微生物が頑張って作っているんだよって。是非、色んな人に「くさや」を食べてみて欲しいですね。きっとその魅力がわかるはず!
「変わり者」の乳酸菌を求めて
私達は熟成チーズから分離した乳酸菌の研究を行っています。乳酸菌は普通、酸性で塩のない場所を好みます。しかし私達が探しているのは、それとはまったく逆!アルカリ性が好きで塩も好き、そんな一風変わった乳酸菌です。どのチーズにいるのか?どこからきたのか?チーズにどんな影響を与えているのか?解明しなければならないことは山積みです。少しでも成果を上げようと力を尽くしました。
この乳酸菌に関して,私が1年間行った実験の成果は微々たるものかもしれません。しかしこの研究活動を通じて。「未知のものを、自分の手で解明した」という大きな達成感を得ることができました。この経験は一生ものです。
発酵食品の成分ってこんなにあるんだ
発酵食品を食べたとき、おいしさってその味だけではなく、においも重要な因子です。発酵食品中のにおい成分って数種類くらいしかないと思っていましたが、実は1つの発酵食品でのにおいい成分は数十種類以上あります。そこで、様々な発酵食品中のにおい成分を最先端のガスクロマトグラフィー質量分析計(GC/MS)で分析したところ、例えばチーズだと30種を超える成分が含まれていて、その中の微量成分がにおいの特徴として重要であることがわかってきました。分析機器の取り扱いや得られたデータの解析は難しいですが、色々な発酵食品の成分を分析して、それぞれの特徴となるにおい成分の特定もしていきたいです。
研究室内の交流って重要だよね
私たちの研究室では、研究室内での情報・データは研究室メンバー全員で共有するようにしています。だから、普段から研究室内での交流が活発で、学科行事(チーズ会やソフトボール大会)には研究室メンバー全員で参加しています。より一層交流を深めるために研究室旅行にもみんなで行きます。1泊2日という短い時間でしたが先生や先輩と色々と交流が出来て、より一層団結力が高まりました。道中、酒蔵見学などにも行って現場の方ともお話しが出来、貴重な体験が出来ました。今はコロナ禍で行けていませんが、また行けるようになったら良いな なんて思ってます。