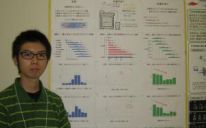水圏フードシステム分野 水圏生産科学研究室
国際連合食糧農業機関は、世界の人口が2050年までに90億人を超えると予想しています。人口増加が避けられない中でも動物性タンパク質の安定供給が望まれますが、天然海域における水産資源の開発が進んでおり、新たな資源の発見や利用が難しいのが現状です。また、漁獲される魚介類の種や量の変化が水産業に大きな影響を及ぼしているため、環境への負荷を最小限に抑えた持続可能な増養殖技術により、魚介類を安定して確保することが喫緊の課題です。当研究室では染色体操作を利用した新品種の開発、対象種毎に異なる生態に最適化させた飼育・生産技術、生物生産にあたり避けて通れない病害防除技術など、水産資源を「殖やす・保全する」ための「安心・安全・簡便」な技術を研究開発し、オホーツクの水産業を通じて食糧問題の解決に貢献することを目標にしています。
KEYWORDS
種苗生産、染色体操作、クローン、防疫、冷水性甲殻類、サケマス
水圏生物を「殖やす」次世代技術の開発
世界の人口は2050年までに90億人を超えると予想されており、動物性タンパク質の安定供給が望まれます。魚介類は動物性タンパク資の供給源として重要ですが、天然海域におけるその資源量は常に変動します。従って、魚介類を安定して確保する対策の確立が喫緊の課題です。本研究室では染色体操作を利用した新品種の開発、対象種毎に異なる生態に最適化させた生産技術など、重要な水産資源を「殖やす・保全する」ための「安心・安全・簡便」な技術を研究開発し、オホーツクの水産業を通じて食糧問題の解決に貢献することを目標にしています。
所属教員
学生の主な研究テーマ
・サクラマスにおける尿中トリプトファン代謝物の時空間的変化
・カジカ小卵型の雄の生殖生理・繁殖期の営巣に伴い増加する尿の機能
・遅発性筋痛発生および治癒過程における発痛物質と一酸化窒素の関連
・魚病細菌Vibrio anguillarumに対する緑茶カテキン類の殺菌活性
・魚病細菌Aeromonas salmonicida非凝集株に対する緑茶カテキン類の殺菌活性
・魚病細菌Aeromonas salmonicida自発凝集株に対する緑茶カテキン類の殺菌活性
FREE TALK
石井君の発表後
日本水産学会北海道支部大会でサクラマスの性フェロモン応答に関する口頭発表してきました。参加した学生・院生の中で3年生は私だけでした、恐らく最年少者だったと思います。懇親会にも参加しましたが、先生方ばかりで飲食物が喉を通りませんでした。発表はまあまあ上手くいきましたが、質問に充分答えられたかは何とも言えません。発表後、先生と函館地ビール明治館に行きました。ここは先生が院生時代に、論文が受理されたり誰かお客さんが来たり送別会の時など、何か特別な事があると皆で呑みに来ていたそうです。発表の緊張と疲れのため、沢山呑めませんでしたが大変美味しかったです。ピアノとサックスの生演奏もあり、とても楽しかったです。今後も機会があれば、学会発表したいです。函館の回転寿司も美味しかったです。

中標津の別荘で秋刀魚祭り
熊石サンプリングに続き、北海道立水産孵化場道東支場において成熟魚の尿もサンプリングしました。中標津には研究室で別荘を借りています。実験魚の馴致やカテーテル装着までは、楽しい時間を過ごすことが出来ます。今回は根室のサンマ祭りに有志が出向き、サンマを1箱買ってきました。先生が刺身を造り、学生達が七輪での秋刀魚塩焼と肉を焼きました。大変美味しかったです。その後はシルバーウィークにも拘わらず、交代で夜番し皆で作業しました。そんな中、ミンクが出没し、カテーテル付きの魚を3匹捕られてしまいました。実はこれ以前にも行動実験用の魚が皆殺しに遭いました。この顛末は研究室メンバーのみ知るところです。

サンプリングついでに温泉
研究室では、八雲町熊石にある北海道立水産孵化場道南支場において、未熟サクラマス親魚の飼育水と尿をサンプリングしています。道中は行きも帰りも好天でしたが、サンプリング中日は雨天が続き大変でした。宿泊したバンガローは快適でしたが、水路が濁水で増水したせいで頂いたサクラマスが飛び跳ねたり、4年生がズブ濡れになったり、水路に院生が落ちたりとハプニングの連続でした。先生は体調を崩し、夜番を学生達に任せて寝てしまいました。慌ただしく時間を過ごしましたが、夜は無料の「熊ノ湯」に行きました。また、先輩が夕方の引き潮を狙って院生が海サクラ(3kgと1.5kg)を釣ってきました(合法です!)。ここは激戦区で早朝には多数の釣り人が押し寄せ、千葉から来ている人もいました。釣ったサクラマスは丁重に持ち帰り、後日ルイベとして美味しく頂きました。

本当の目的
私たちの研究室ではサケ科魚類のフェロモンについて研究をしています。毎年5月になると、道南方面の熊石という周りを海と山などの大自然に囲まれた場所(僻地?)に数人でサンプリングに行きます。ここで1週間ほど交代しながら、24時間体制でサクラマスの採尿を行います。要するに、魚の生活リズムに自分たちの生活リズムを合わせて生活するということです。それは想像以上に辛く厳しい作業ですが、ある一つの楽しみのために頑張ることができます。それは釣りです。2月~5月、熊石地方を含めた日本海側では、サクラマスが遡上のため岸寄りします。海にいるサクラマスのことを北海道では“海サクラ”と呼び、その難易度の高さと良質な味から、この時期の釣りのメインターゲットとなっています。すべての条件が合わないと釣れないこの魚を、海まで5分という最高の環境で、条件が合うまで毎日狙うことが出来るこの機会を体験してみませんか?きっと楽しいですよ。

研究室旅行.日光
研究室旅行は各研究室によって行き先は異なりますが、その旅行での思い出を紹介します。水圏生物化学研究室の研究室旅行は日光を訪れました。他の研究室と違って生化研は遊びに来ているのではなく、研究の一環としてきているので皆初めは嫌そうにしていました。それは研究紹介のスライド発表があるからです。中禅寺湖付近の宿に泊まり、初のゼミ発表を行いました。皆お酒を飲んでおり、楽しい雰囲気で行うことができました。発表後も、飲む人は飲み、次の日は日光を観光して無事研究室旅行を終えることができました。この旅行で、研究室の3年生に新たな絆が深まりました。最後は皆「楽しかった」と言っていました。