デザイン農学科
厚木キャンパス
「デザイン」とは、「問題解決の手段」であるとともに「新たな価値を創造」すること。デザイン農学科では、私たちの間近に迫っている社会問題を農学的視点で解決し、新たな価値を創造します。
学科インフォメーション
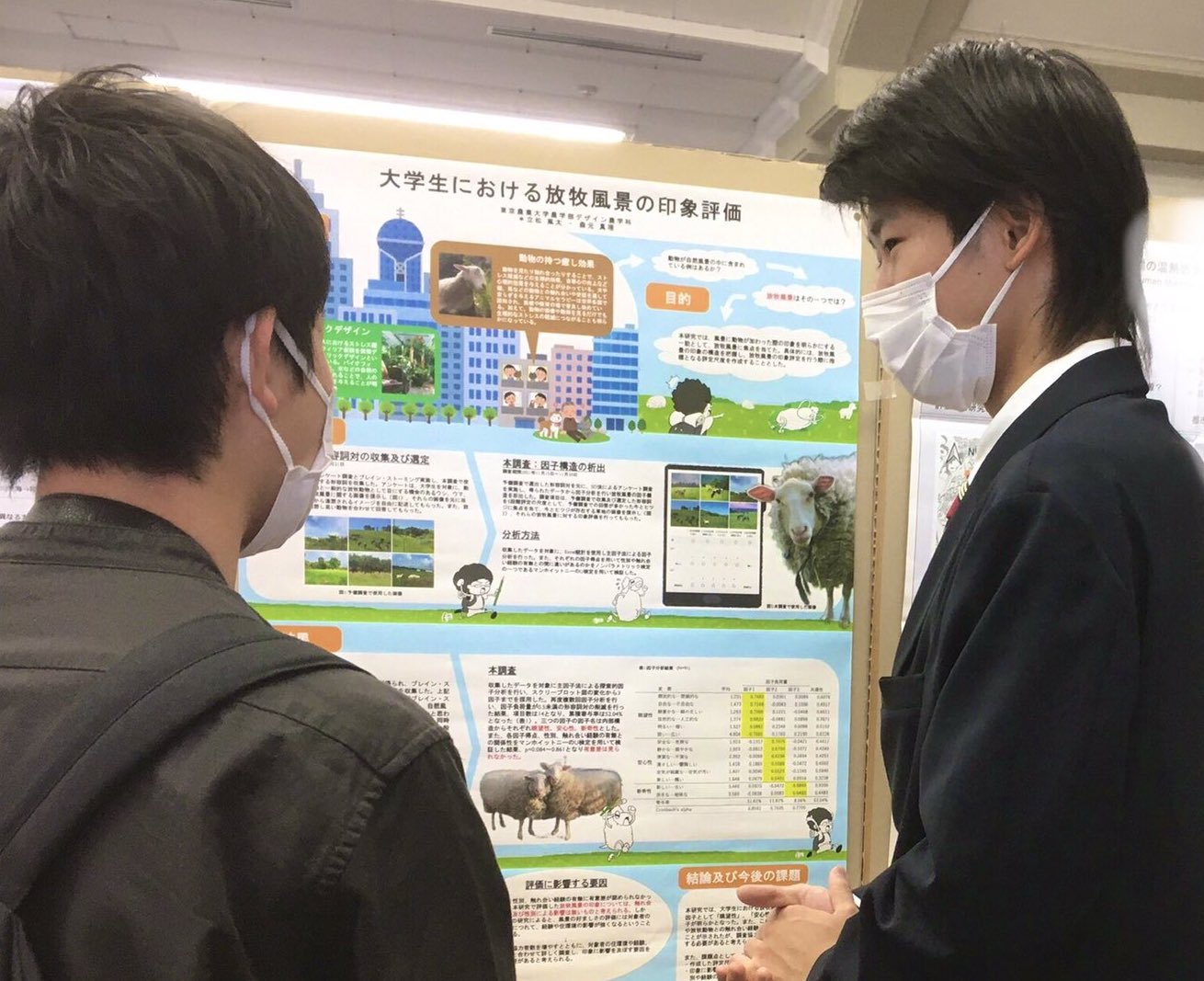
【学会発表】北海道大学にて造園学会が開催され、生物機能開発学研究室の学生がポスター発表に参加。放牧風景に対する人の印象を調査したものでした。発表お疲れさまでした!2022/6/19
【食品加工実習でパン作り!】食機能科学研究室では実習の一環でアンパンとソーセージパン、ロールパンを作りました。生地をこねるのは業務用のミキサーにて行って,約3.5キロのパン生地から75個のパンが完成。できたパンはみんなで持ち帰りました!2022/6/12
学科基本情報
現代社会が抱える多様な課題に、新発想な農学で対処する
デザイン農学科では、「農学」を専門家や生産者といったひとにぎりの人たちだけに向けた学問領域ではなく、一人ひとりの生活者にとってより良い暮らしをデザインするための学問領域として捉えています。

あらためて私たち自身の暮らしに目を向けると、昆虫、動物、草花といった生き物や、生命を支える食品などの「農」に囲まれています。デザイン農学科ではこれら生き物や食がもつ機能性に着目し、それらを応用して持続可能な社会をデザインしていく学科です。つまり、SDGs実現に向けたこれまでにない発想の農学を進めています。
デザイン農学が切り拓く未来(研究プロジェクト)
デザイン農学科の研究対象は実に多彩です。生物の構造や機能を応用したテクノロジー開発 、環境に配慮した先進的な食品加工技術の探求、これまで廃棄されていた未利用資源や加工副産物を活用した食品開発や機能性の分析、福祉や教育といった身近な生活領域での動植物の活用法の提案、膨大なデータと統計学を駆使した都市や農村地域の社会システム構築など、理系を中心とした自然科学と文系を中心とした社会科学の「知」を横断的に学びます。
#バイオデザイン 昆虫の触角を利用した「匂いセンサ」で危機管理
多くの昆虫が持つ、匂いを探知する能力を人工的に再現し、高感度の「匂いセンサ」として、空港での爆発物等の探知に利用できないかを研究しています。

#エディブルデザイン 失われていく農作物の「色」の機能を保持
果物や野菜の鮮やかな色には、抗酸化作用などの機能があります。加工や保存で失われていく色の安定性を高め、色の持つ機能を守る研究をしています。

#ライフデザイン 農業と福祉が連携する「訪問かいこプロジェクト」
リハビリの一環として家庭でカイコを育て、繭を化粧品の原料として売ることで収入や生きがいが得られる、「訪問カイコプロジェクト」が始まっています。

クローズアップ研究者
文理の枠にとらわれない2分野5研究室体制
デザイン農学科は、「農」のチカラで暮らしを豊かにする「イノベーション農学分野」と、「農」の知恵で暮らしの課題を解決する「サスティナビリティ農学分野」に分かれています。
イノベーション農学分野
サスティナビリティ農学分野
授業 Pick Up
2年次
必修
畜産物利用論
私たちが豊かで健康的な生活を送るうえで畜産食品は欠かせません。普段なにげなく食べている畜産食品は原材料を加工することにより、様々な物理・化学変化を生じさせ、製品となります。本科目では主に乳・肉・卵の生化学的、栄養化学的、製造学的な特性について学びます。
2年次
必修
生活デザイン農学
家庭動物の飼育やガーデニング作業は、日々の疲れを癒し、生活に規則正しいリズムを与えてくれるなど心理的・身体的な効果をもちます。本科目では、生活の中でかかわる動植物の機能性を理解し、生活や福祉の領域で多面的に活用するための基礎知識について学びます。
3年次
選択
バイオミミクリー論
生き物の機能性には現代の科学技術を駆使しても真似できないものが多く存在します。タマムシの発色機構を真似た塗料を必要としない製品(写真)、蚊の針を真似た痛くない注射針など、本科目ではこうした生き物の模倣技術(バイオミミクリー)について解説し、環境に配慮した社会のあり方について学びます。
デザイン農学科の学び
卒業後の進路
就職先の展望
私たちの生活に直結する「食」にかかわる分野はもちろん、「衣」・「住」にかかわる工学や環境そして福祉の分野、また政策決定にかかわる分野、さらにサイエンスコミュニケーションの分野などで活躍することが期待されています。
予想される進路
- 食品製造業
- 機能性製品(医薬・化粧品)製造業
- 流通関連事業
- 協同組合
- 農園芸関連事業
- ペット関連事業
- 社会福祉関連事業
- 広告代理業
- 金融関連事業
- マスコミ・出版関連事業
- 国家公務員
- 地方公務員(上級職)
- 高校教員(農業)など
