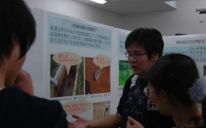動物共生分野 野生動物学研究室
学生の主な研究テーマ
・自動撮影カメラを使用した小型哺乳類調査法の開発
・飼育下におけるチーター(Acinonyx jubatus)の鳴き声及び行動に関する研究
・環境温度変化がアカネズミApodemus speciosus雄の血中テストステロン濃度に及ぼす影響
・ニホンヤマビルの分布および生息密度と哺乳類の出現頻度の関係
・外来種ハリネズミの捕獲効率向上に関する研究
・日本産モグラ2種(アズマモグラMogera imaizumiiおよびコウベモグラMogera wogura)における光感受器官に関する研究
・イエネコが野生動物に与える影響について
FREE TALK
大学生として最後で最も大きな課題、卒業論文。私は人と野生動物の関係についての研究を行いたかったので、卒論は獣害についてのものを考えていました。その結果、シカとヤマビルの関係を調べる研究を行いました。ヤマビルと聞くと、なんだそれ?と思うかあんなものを?と思う方が大抵だと思います。正直、自分でも大学に入ってまさかヤマビルの研究を行うとは夢にも思っていませんでしたし、これで卒論が書けるのかとさえ不安に思っていました。しかし、かなり苦労しましたが無事卒論をまとめることが出来ました。
こんな風に、大学とはかなり自由なところです。そして高校までとは違って授業(講義)は多くは無く(もちろん忙しいときはありますが)、自由な時間がたくさんあります。大学に入って暇だなと思う人もいるかもしれません。しかし、私は大学とはこういった自由な部分で自分の望むことをやり遂げるところなんだと思います。
卒業研究、研修旅行、収穫祭や先生と仲間との活動での感想
まず研究室の思い出と言ったら、収穫祭とわが野生動物学研究室の特色が出ている分野別実習・演習だと思います。3年次の収穫祭に、文化学術展といった自分たちが行っている研究を伝える展示を行うのですが、一丸となって作業を行うことは想像していた以上にとても大変で、それゆえ完成したこと、沢山のお客さんが展示を見て反応してくれることに喜びも一入でした。次に、分野別実習・演習ですが、研究室で主に研究している哺乳類や鳥類だけではなく磯の生き物とふれ合ったり、様々な調査技術また標本作製と幅広く学ぶことでジェネラリストな視点を身につけることができ、その土台があったからこそ、大学生活4年間の集大成となる卒業研究に取り組むことができました。他にも、研修旅行や先生や仲間との日々の生活と多くの思い出がありますが、興味がある方は、是非是非研究室に遊びに来て聞いて下さいね。
私は消極的でコミュニケーションも苦手だというのに、なんとなく研究室3年のとき学年長に立候補してしまいました。そしてそのまま学年長、4年のときは幹事長になりました。それぞれリーダー的存在であり、研究室とは学生が動かなきゃいけません。よくもまあ2年間研究室をやってこれたなぁと本当に思います。なんとかなったのは先輩や同級生がいろいろやってくれてたおかげですね。仮にも学年長から幹事長、同じ研究室の人たちと関わることはなかなかあります。今思えば、人と関わるたびに一つ一つと人の良さというか、楽しさを知っていったような気がします。研究室での生活はすっごい大変なこともあればすげぇ楽しいこともあり、さらにちょこちょことやらなきゃいけないことがあったりと色々な事ばかりです。それに、たとえ大変であっても意外と頑張れるもんです。それはきっと大切なものが何なのか分かってきたからではないかと思います。紆余曲折はあれど、自分なりに色々やってみれたらいいんじゃないかと思いました。最後に、研究室生活で先生、先輩、後輩、なにより同じ学年の仲間たちに出会えたことが一番嬉しいと思える事でした。