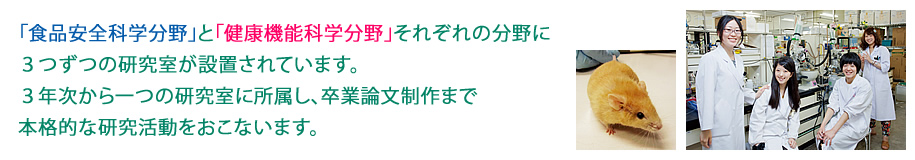| 食品安全解析学研究室 |
食品中の有害因子を探り出し、その生体影響を定義する
食品安全解析学研究室では、食品中に存在する化学物質や微生物のような有害因子を検出し、それらがどのような生体影響をあらわすのかを網羅的に調べ、さらに体内のどこにどのように作用するのかを分子レベルで解析します。そのうえで有害因子が与える健康影響を定義し、正確なリスクおよび安全性評価のための基礎情報を得ていきます。さらに有害因子と生体との相互作用を有機化学の視点から理解するために多様な研究手法を組み合わせて問題解決にあたります。
研究OUT LINE
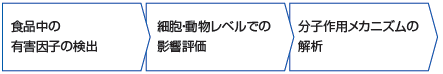 |
|
研究テーマ例
・有害因子の細胞内・生体内ターゲットの探索とそのメカニズムの解析
・神経毒の標的部位への結合メカニズムの定義
・安全性を考慮した有用化学物質の設計 |
|
| 食品安全評価学研究室 |
食品中の有害因子の生体への影響を分子病理学的に評価する
ヒトの健康の維持・増進には、食品中の化学物質の優れた機能を生かし、有害性を排除することが必要です。食品安全評価学研究室では、ヒトの健康への悪影響が懸念される物質や、老化・がん・糖尿病・脂質異常症などの予防や治療効果がみこまれる物質の、生体への影響について、動物実験と分子病理学の解析手法によって検出し、その詳しい背景を解明します。また、さまざまな組織や細胞を用いた「動物実験代替法」の開発とその有用性の検証にも取り組みます。
研究OUT LINE
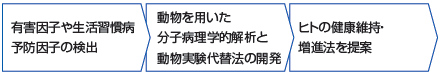 |
|
研究テーマ例
・食品中の化学物質を利用した生活習慣病予防と治療に関する研究
・食品中の化学物質の安全性評価と管理に関する研究
・化学物質の安全性評価のための動物実験代替法に関する研究 |
|
| 食品利用安全学研究室 |
食品の機能と安全に配慮した新たな加工学を切り拓く
食品を有効に利用する、あるいは生活習慣病を防ぐためには、食材がもつ栄養機能や嗜好機能などの多様な機能を保持・向上させる加工や
保蔵の技術が必要であることから、食品素材のもつ多様な機能を明らかにし、それを活かす新しい加工法の開発をめざしています。一方、食中毒を防ぐためには、より安全性の高い加工保蔵法が求められています。また食品の腐敗・変質の原因となる微生物の性質を分子レベルで
解明し、食品の保存性向上に役立てる基礎研究もおこないます。
研究OUT LINE
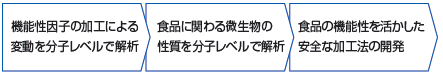 |
|
研究テーマ例
・食品微生物のストレスに対する耐性に関する研究
・食品の物性の制御と口腔内の知覚情報に関する研究
・加工による機能性因子の変動に関する分子メカニズムの研究 |
|