新任あいさつ2024 荒川
新任のご挨拶
荒川 弦矢 助教(酒類生産科学研究室)
今年4月に醸造科学科酒類生産科学研究室の助教に着任しました荒川弦矢と申します。着任して2ヶ月とまだ戸惑うことも多いですが、母校である東京農業大学で教育と研究に携われることに大きな喜びを感じています。また、たった2ヶ月と短い期間ですが授業や研究室活動に携わり、教員と言う立場の責任の大きさを改めて感じる日々を過ごしています。研究者としても、教育者としても至らぬ点が多くございますが、醸造科学科の諸先生方、卒業生の先輩方におかれましては、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いします。この場をお借りして自己紹介とご挨拶をさせていただきます。
私は1992年に愛知県岡崎市に生まれ、東京農業大学に進学するまで味噌と言えば赤味噌と言う文化で過ごしてきました。また実家が昔ながらの酒販店であったこともあり、桶いっぱいの味噌を量り売りする両親を見て育ったため、小学生のころは味噌は酒屋で重さを伝えて買うことが普通だと思い込んでいました。思えば、清酒に醤油、味噌、味醂と醸造食品に囲まれた環境で育ったことが東京農業大学の醸造科学科を進学先として選択し、現在の職を志望した下地になっていたのだと思います。
大学1~3年生は大学生らしくバイトに部活にと勉強は後回しにしていましたが、大学4年生になって本格的に研究室活動が始まってからは未知を既知にすると言う研究の魅力にのめり込んでいきました。研究室では麹菌の二次代謝制御機構の解明を大きな目標として、徳岡昌文先生の指導の下、未知機能の制御因子に注目して遺伝子機能の解明に取り組みました。麹菌は日本の伝統的な醸造食品に欠かせない微生物であり、私たち日本人は古くから食してきた経験があるため安全な微生物だと捉えていますが、他の糸状菌が二次代謝産物としてカビ毒を作ることから、過去に海外で麹菌が危険視されたことがあります。科学的な根拠を持って麹菌の安全性を説くためには麹菌の二次代謝制御機構の解明は日本の醸造産業の安全性を担保するための重要な課題です。この様な背景のもと、まだいずれの生物種でも機能が判明していない遺伝子について二次代謝との関与を中心に解析を進めました。運良く結果が実を結び、注目していた制御因子が分生子形成の中心的な制御因子を介して二次代謝と分生子形成の制御に関わることを明らかにしました。解析していた遺伝子に私たちで名前を付けることになったのですが、いずれの生物種でも名付けられていない遺伝子でしたので、この時は随分と嬉しかったのを覚えています。この研究の成果で、アシロマ会議で有名なアメリカのカリフォルニア州アシロマで開催された国際学会30th Fungal Genetics Conferenceで初めて海外の学会に参加しました。海外の大御所の先生や興味深い論文を出していた若手の研究者と交流したことで、世界には凄い人が一杯いるのを実感し、身の程を知りました。同時に、こんな人たちがわざわざ聞きに来てくれる研究が出来ていたことにも気付き、多少の自信を持つこともできました。修士・博士課程は焦りがあったため当時は余裕がありませんでしたが、今思えば研究のみに集中できる稀有な時期であり、その時期に目一杯研究に没頭でき、徳岡先生に様々なことを指導していただけた貴重な時間でした。
博士号を取得後は富山県の食品研究所で研究員として働きました。産業に近い環境であったため、産業界のニーズやシーズを意識するいい機会でした。他にも総米50kg規模での仕込みをしたりと、大学の研究室では中々できない経験をさせていただきました。この時期から清酒の製造工程に関する研究を始め、運の良い出会いもあったことから清酒の非加熱殺菌方法を報告し、講演などの依頼も来るようになりました。遺伝子関連のみでなく清酒の製造工程に関する論文を書けたことで、研究の幅を広げることができたと思います。
私はこれまでに醸造微生物の遺伝子や清酒の製造工程に関することを中心に研究をし、それらの研究を通じて様々な醸造産業に携わる人と交流を持つことで、いろいろなことを学んできました。これからは、次代の醸造産業を担う人材の育成と醸造産業の発展に寄与できるような研究を心掛けて、東京農業大学での教育と研究に従事したいと思います。重ねて、醸造科学科の諸先生方、卒業生の先輩方の皆様、ご指導とご鞭撻の程、どうぞよろしくお願いいたします。
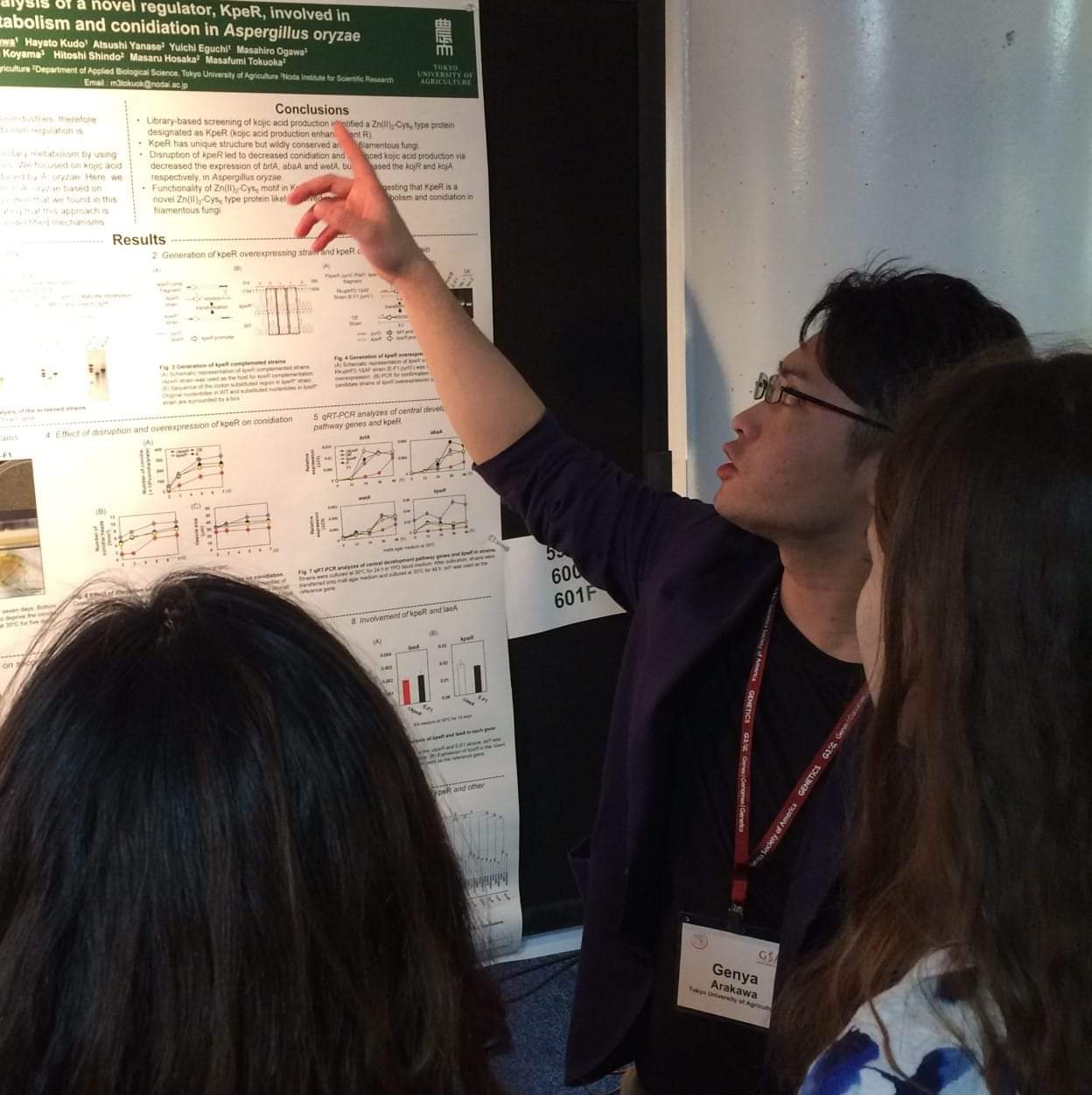
 国際学会での発表の様子(博士課程) 総米50kgの仕込みをしている様子
国際学会での発表の様子(博士課程) 総米50kgの仕込みをしている様子
(富山県食品研究所にて)