| |
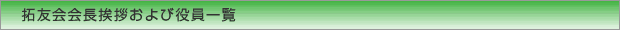
 拓友会会長挨拶 拓友会会長挨拶 |
この度、長尾文博会長の後を受けることになりました。専門部拓殖科、農業拓殖学科、そして現在の国際農業開発学科の卒業生約8,500人を有する拓友会の新会長として、本会の発展に微力ながら貢献したいと思いますので、皆様のご指導とご支援のほど、どうかよろしくお願いいたします。

私は農業拓殖学科14期ですが、在学中に1年間インドで海外実習をしましたので、卒業は15期の皆さんと同期になります。学生時代は、熱帯殖産研究室 (現在は、熱帯作物学研究室)に所属し、栗田先生、西山先生、早道先生に師事しました。今や第1号館も解体され、世田谷キャンパスも大きく様変わりしましたが、研究室が入っている2号館だけは全く変わっていないため、今でも学生時代を懐かしく思い起こすことができます。
昨年は、東京農業大学創立125周年、農業拓殖学科60周年の記念すべき年でした。この歴史的節目に、校友会が主催して「世界大会」が9月23日に開催され、世界で活躍されている多くの拓友会会員も集まりました。大会式典の各国代表講演で、拓友会会員の一人でもあるタイのタマサート大学科学技術学部長ソムチャイさんが、「東京農業大学は、なかなか卒業させてくれない大学だ」という話をされました。農大で学位を取得され、帰国後も繋がっている大学との絆を表現されたものですが、拓友会の設立趣旨にも叶い、感慨深く聞き入っていました。
私も、特に海外に滞在しているときなど、卒業後も農大との繋がりを有難く思ったものです。いつでも答えてくれる農学的なアドバイスのみならず、国内外の人脈は卒業生共有の財産でしょう。この貴重な大学との繋がりや卒業生としての人脈を、常に世代を超えて活性化していくことが拓友会の目的であると思います。
昨年、実践的な農業を修得する場として「NPO法人農と人を拓く学び舎向志朋 (こうしほう)」を、農大卒業生の仲間とともに千葉県白井市に立ち上げました。農業を基盤とする国際協力や国内の地域活性化に取り組む人材の育成を目的としていますが、拓友会の一つの拠点として、大学や卒業生との繋がりを維持するための接点になればと、考えています。
卒業させてくれないユニークな学風のもと、拓友会会員の絆をさらに堅固にし、会員及び大学の双方にとって意義ある拓友会とすべく、特に若い世代の会員に対しては頼りがいのある会にしたいと思っています。
会員の皆様のご健康とご活躍を祈念し、今後とも一層のご支援とご協力をお願いして、就任のご挨拶とさせていただきます。
大塚正明 (農業拓殖学科14期卒業生)
|
 役員一覧 (平成28年10月1日〜平成30年9月30日) 役員一覧 (平成28年10月1日〜平成30年9月30日) |
| 名誉会長 |
入江 憲治 (国際農業開発学科長 |
| 会長 |
大塚 正明 (農業拓殖学科14期) |
| 副会長 |
佐藤 貞茂 (農業拓殖学科15期) |
| 井佐 彰洋 (農業拓殖学科21期) |
| 顧問 |
戸神 重美 (元校友会長専門部拓殖科7期) |
| 原 瀬利 (元会長専門部拓殖科7期) |
| 藤井 勝政 (元会長農業拓殖学科1期) |
| 渡辺 直行 (元副会長農業拓殖学科1期) |
| 大川 純一 (元会長農業拓殖学科3期) |
| 赤地 勝美 (元会長農業拓殖学科5期) |
| 大田 克洋 (元会長・元名誉会長農業拓殖学科6期) |
| 黒柳 正巳 (元副会長農業拓殖学科5期) |
| 島田 文雄 (元副会長農業拓殖学科10期) |
| 小金丸 梅夫 (元副会長農業拓殖学科12期) |
| 太田 保夫 (元名誉会長) |
| 河合 省三 (元名誉会長) |
| 小野 功 (元名誉会長) |
| 鈴木 俊 (元名誉会長農業拓殖学科7期) |
| 豊原 秀和 (元名誉会長農業拓殖学科11期) |
| 監事 |
中川 昭夫 (農業拓殖学科8期) |
| 高橋 久光 (農業拓殖学科13期) |
|
|
|
|
|
|
|