| |
|
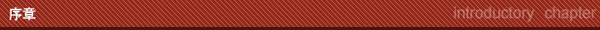
序章
本学は、併設の東京農業大学の建学精神「人物を畑に還す」、教育理念「実学主義」を基盤とし1950(昭和25) 年に設立され、東京農業大学と連携を図りつつ短期大学における教育研究を推進し、産業界で活躍する多くの有為な人材を養成すると共に特色ある短期大学として評価されている。1992(平成4) 年に、その後の大学進学率の増加、大学数の増加、18歳人口の変動、産業の高度化など社会情勢の変化から、短期大学教育へのニーズの変化を捉え高等教育における短期大学の位置づけに鑑み、農業科を生物生産技術学科と環境緑地学科に改組、醸造科および栄養科をそれぞれ醸造学科および栄養学科に改称し、4学科体制とした。また、1998(平成10年)には併設の東京農業大学では、農学部10学科を農学部、応用生物科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部に改組し、1989 (平成元) 年に設置した生物産業学部と併せ5学部体制となった。本学と東京農業大学が連携し、社会および時代の要請の変化に対応し、建学の精神、教育理念の実現に向け改善と改革を進めている。
本学では学則第2条の2において「教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行うことに努めること」及び「自己点検評価委員会を置くこと」を規定している。この規定に基づき1994年に自己点検を実施し、その結果をまとめ翌年「東京農業大学農業大学短期大学部の現状と課題」を公表している。1999年に2回目の自己点検・評価を実施し、2000年に2000年版「東京農業大学農業大学短期大学部の現状と課題」を公表すると共に、学外者による外部評価を実施し2000年12月に公表した。
2004年に外部評価が義務づけられたことから、同年に3回目の自己点検評価を行い、その自己点検・評価報告書を(財)短期大学基準協会へ提出し、2006年3月28日付けで(財)短期大学基準協会による第三者評価の結果、適格と認定された。その際、向上・充実のための課題として次の3点の指摘があった。
「教育の内容」
<1>学生による授業評価の活用について組織的な対応が求められる。
「教育目標の達成度と教育の効果」
<2>成績のばらつきが目立つ学科は、その対策が望まれる。
<3>学科によって、退学者が多い傾向が見られる。学科への不適応かあるいは学力不足等の理由によるものか、追跡調査が望まれる。
その後、指摘された問題点について、以下のように改善した。
<1>全授業科目で学生による授業評価を実施した。集計結果を各教員に通知する共に、実施状況を組織的に把握し学部長会で検証を行った。
<2>成績結果のばらつきの対策として、成績評価の指針を明確に定め、全教員に周知した。2006年度からGPAを導入し、成績評価の指針設定と共に成績評価のばらつきを小さくすることに寄与した。
<3>退学者はきめ細かな指導により減少した。追跡調査の結果、成績不良および進路変更が全体の約7割を占めた。本人の希望と学科内容とのミスマッチを減らすために、受験段階での学科目的等の周知を一層はかるとともに、入学時の学力不足に対応するためリメディアル科目を導入した。
今回、4回目の自己点検・評価を実施し、2回目の第三者評価を受審するにあたり、併設の東京農業大学と共に(財)大学基準協会に審査を申請することを決定した。
自己点検・評価の実施経過としては、2010年12月21日学部長会で作業スケジュール、点検・評価項目について承認を得た。2011年2月1日に全学自己点検評価委員会を開催し、委員長から作業スケジュール、点検・評価項目ごとの責任者等について説明し、各委員に点検評価内容の周知と実施体制の整備を依頼した。全学自己点検評価委員会は併設の東京農業大学との共通組織であるため、短期大学部委員会を設け、教学部分は短期大学部長を中心に各学科と関係機関を配置し、学生支援・施設設備・管理運営等の部分については事務局長が中心となり関係所管を統括して点検評価を進めることとした。その後、東日本大震災により作業スケジュールが大幅に遅れ、6月14日学部長会において作業スケジュールの修正と点検評価体制の再確認を行い、6月17日に大学基礎データおよび関連データの作成を委員長から関係所管に依頼した。7月5日に(財)大学基準協会から講師を招き、「認証評価の新段階―内部質保証システムをいかに機能させるか―」との内容で講演いただき、全学自己点検評価委員会委員および関係者が出席するとともに、同日全学自己点検評価委員会を開催し、委員長からスケジュール変更と点検評価作業上の注意点、報告書の記述方法等について説明し、報告書の作成を依頼した。また、7月12日学科長会においても、報告書作成依頼と作成上の注意点等について説明を行った。8月には大学基礎データが完成した。9月下旬には、各責任者から提出された報告書について、教学部分は短期大学部長、学生支援・施設設備・管理運営等については事務局長が中心となり、報告書内容の確認・ヒアリングを実施した。報告書原案が概ねまとまったことを受け、11月1日に全学自己点検評価委員会を開催し、作業の過程で気づいた点等について意見交換するとともに、全委員に報告書原案を配付して内容の確認を行った。各委員から寄せられた意見を基に報告書原案に修正を加え、12月1日の全学自己点検評価委員会で承認を得て、自己点検・評価報告書が完成した。
2004年の3回目の自己点検・評価から、各学科・部署では日常の活動を日々点検し、問題点を解決すると共に、共通認識の形成に努め組織的な改善を進めてきた。また、入口と出口、すなわち志願者数、編入学数、就職率など直接的な数値だけの評価に甘んずることなく、社会の付託に応えるべくこれらの評価の基盤となる教育研究の充実に努めてきた。第三者評価は、7年間の本学の活動およびその成果を客観的な視点で検証する機会と捉え、今回の自己点検・評価活動の中で策定された改善方策を実施に移し、さらに今後の認証評価による指摘事項を真摯に受け止め、本学のさらなる充実と発展を目指していく所存である。関係各位のご指導ご鞭撻を心からお願いする次第である。 |
|
|
|
|
|
|