| |
|
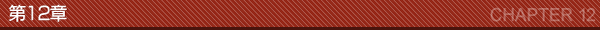
【学長、短期大学部長の役割と選任手続き】
【現状の説明】
学長の選任については、学校法人東京農業大学人事規則第15条第1項で「東京農業大学の学長は東京農業大学長選挙規程によって選任する。」とし、同条第3項で「短期大学部の学長は、東京農業大学の学長の併任とする。」と規定している。学長の選任手続きは、「東京農業大学学長選挙規程」により次のように行われる。
- 学長の候補者の範囲は、学の内外及び年齢を問わず、広く適任と認められる者のうちから選出する。学内候補者は10名、学外候補者は20名の推薦人を必要とする。
- 学長の任期は、就任の日から4年とする。ただし、重任を妨げない。
-
重任された学長の任期は、就任の日から2年とする。ただし、重任は二期4年を限度とする。
-
選挙権者は、助教以上の教務職員
上位クラスの事務職員
法人の理事、監事、評議員 とする。 -
選挙は、直接単記無記名投票により行う。選挙は、選挙権者総数の2分の1以上の投票者数をもって成立する。
-
選挙管理委員会は、選挙において白票及び無効票を除く有効投票総数の2分の1以上の得票者を当選者とする。
-
学長の任命については、選挙結果を速やかに理事会に報告し、理事長が任命する。
短期大学部部長の選任については、学校法人東京農業大学人事規則別表第4(第61条関係)「東京農業大学短期大学部の補職」に規定している。選任手続きは、教授会において教授のうちから互選により短期大学部部長を選出後、人事委員会で決定する。
学長は、学校法人東京農業大学寄附行為の定めるところにより、理事・評議員として法人の管理運営に直接かかわっている。学長の職務については、学校法人東京農業大学人事規則第7条第1項に「学長は、大学の業務を掌理し、所属職員を統督する。」と明記している。また、東京農業大学学則第4条の2では「学長は、本大学の業務一切を掌理し所属職員を統督すると共に本大学を代表する。」と規定しており、学長の職務は法人の理事としての職務と、学校教育法第58条に基づく「学長」の職務との両面を有している。対外的には、大学を代表して諸行事にも出席し、大学の方針及び決定事項を公表している。
学長は、法人・教学それぞれに固有の職務を有していることから、理事会、評議員会の職務上の構成員となり、学部長会あるいは全学的審議機関である全学審議会の議長として、大学、大学院の経営・教学の意思決定に深く関与している。
本学では、学校教育法に定める大学の長たる学長の機能を十二分に活かすために、学生サービス向上担当、大学改革推進担当及び研究推進担当の副学長を2004年4月から新設し、2011年7月からは教学担当副学長、学生生活担当副学長を置き、学長の職務を補佐している。
短期大学部部長は、全学的審議機関である全学審議会および学部長会の職務上の構成員となり、教学の意思決定に加わっている。また、短期大学部に関わる案件を審議決定する教授会を招集し、その議長となって短期大学部の運営を統括している。加えて、大学内の各種委員会(会議)の職務上の構成員となり、委員長として委員会運営を行うこともある。
学長は、法人・大学(教学)それぞれについて固有の職務を有していることから、理事会のほか全学的審議機関である全学審議会を学長が招集し議長となる。全学審議会の組織・審議事項等については、次のとおり規定されている。
第2章 組織
第2条 審議会は、次に掲げる審議員をもって構成する。
(1)学長
(2)副学長
(3)大学院各研究科委員長
(4)各学部長
(5)短期大学部部長
(6)総合研究所長
(7)教職・学術情報課程主任
(8)学術情報センター長(図書館)〔世田谷〕
(9)エクステンションセンター長
(10)国際協力センター所長
(11)コンピュータセンター長
(12)博物館長
(13)世田谷学生サービスセンター長
(14)学生部長〔世田谷〕
(15)農学部教授1名、応用生物科学部教授1名、地域環境科学部教授1名、国際食料情報学部教授1名、生物産業学部教授1名及び短期大学部教授1名計6名
(16)大学事務局長
(17)世田谷学生サービスセンター事務局長
第4章 審議事項
第4条 審議会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)学則等本大学全般にわたる重要な規則・規定の制定・改廃に関する事項
(2)本大学全般にわたる重要な予算に関する事項
(3)本大学の組織及び職制の新設・改廃及び重要な施設の設置・廃止に関する事項
(4)人事に関する基準の設定並びに教職員定員に関する事項
(5)本大学名誉教授称号の授与に関する事項
(6)本大学名誉農学博士号の贈与に関する事項
(7)学生定員の決定に関する事項
(8)各学部間の連絡調整に関する事項
(9)研究所、農場等の運営に係る基本方針並びに調整に関する事項
(10)その他本大学の運営に関する重要事項
このように、全学審議会は大学運営に関する基本的な重要事項を協議あるいは審議決定する教学サイドの機関である。大学全体の決定にあたっては、副学長、大学の各学部長と短期大学部部長との意思疎通を図り、審議会は、審議員総数の3分の2以上の出席をもとめ、議事は、出席審議員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決している。
なお、大学運営に係わる通常的事項を連絡、調整し、方針を示すための機関として学部長会がある。構成員は、学長、副学長、大学院研究科委員長、農学部長、応用生物科学部長、地域環境科学部長、国際食料情報学部長、生物産業学部長、短期大学部部長、事務局長及び世田谷学生サービスセンター長をもって組織し、学長が議長となり中心的な役割を担っている。
学科長の職務については、東京農業大学短期大学部組織及び職制第17条に「学科長は部長の命を受け、学科を統括する」と定められている。その選出については、学校法人東京農業大学人事規則第61条に規定されており、学科の教授の互選によりそれぞれの学科において選出し、その後人事委員会に付議され決定している。学科長の職務を遂行するため、学科長は学科会議の場を設け、学科内での授業運営についての意見を把握したり、学外での実習での巡回指導や学外者からの指摘事項について協議・運用を進めたりしている。また、学生生活についても種々気配りを欠かさない。このように学科長は、学科内における教育計画にかかる協議・運用事項について、当該学科所属教員の意見をとりまとめ、円滑な運営を図るという重要な役割を担っている。
【点検・評価】
2008年に改正された学長選挙制度は、選挙の投票日10日以前に2日間、選挙権者名簿を選挙権者の縦覧に供した後選挙権者を確定し、投票は選挙権者名簿に基づき行うことから民主的な手続きを経て適切に行っている。また、短期大学部の学長は、大学との併任であることから学長の職務上の負担は大きくなるが、大学全体を通しての円滑で適切な運営がなされている。
短期大学部部長の選出に関しては、人事規則で定めた選任方法にしたがった短期大学部の独自性を尊重した現在の方式を維持することで適正に機能している。
短期大学部の主体性は、学長がその役割をいかに適切に果たすかによって定まる。そういった観点から、現在、学長は適切にその役割を果たしている。一方、昨今の時代や環境変化に伴い、学長の職責は、学長のリーダーシップのもとに全学的な取組みを要する課題が多岐にわたり、かつ対外的な面での学長一人体制は実務上などからも相当激務となっている。教職員の資質向上や学生に対する施設設備の整備や充実など大学運営を積極的に実行していく上で、学長と副学長、短期大学部部長との連携の円滑化を今以上に図ることが必要である。
短期大学部部長は、学長の命を受け、短期大学部を統括し、所属教員を指揮して短期大学部の円滑な運営に当たっている。職務上の内容から照らした場合、短期大学部部長としての役割は適切に果たしている。
全学的審議機関である全学審議会と学長の連携協力関係及び機能分担、権限委譲については、主要なメンバーである学長と短期大学部部長との間で会議に先立ち必要な調整が図られ、会議においては闊達な議論が展開される等、適正な審議員の構成という観点も含めて概ね適切に機能している。
学科長の役割は、学科内における主に教育計画にかかる構想を明確化、具現化することにあり、会議運営や意見集約、短期大学部部長及び他学科の学科長との連絡調整といった場面でリーダー性を発揮することが必要である。このことから、学科長の選出が学科に任されていることは、学科内でのフォロー体制が整いやすく、役割りの行使を支えることとなる。また、学科長会に出席し、学科内の意向を短期大学部全体に説明し、全学的な動向を学科内での協議に生かしたりする場が担保されていることになり、前述の学科内でのフォロー体制とともに長所といえる。
【将来の改善策】
短期大学部の社会的存在価値を検討しつつ、学長の政策形成機能を支える体制の強化が必要となってくる。副学長を置き業務の分担化を進めている中で、学長権限(役割)の一部について副学長へ委譲することを検討していきたい。
短期大学部部長の職務権限、業務基準などについては、学長、副学長との連携の中で、短期大学部部長へ権限を移譲できる業務を明確にして実施することで、さらなる短期大学部の発展につなげることができる。
学長と全学審議会の関係をより効率的に向上させるために、全学審議会の中に各種課題に対し検討するための委員会が設置されており、これらの的確な運営が求められる。
学科長は、前述のとおり、各学科の実情に応じた教育計画を進めることになるが、全学的な検討の場への道筋が担保されているため、学科長の職務は過重ではあるが職務遂行が円滑に運ばれているといえる。短期大学部各学科の今後のあり方を検討することが不可欠な時代において、学科長の役割、行使の適切性をいかに確保するかが重要であることを認識し、様々な議論を通した中で適切な管理運営がなされるよう改善・改革をすすめていく。

|
|
|
|
|

