| |
|
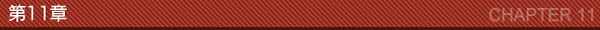
�y�}���A�}���ق̐����z
�y����̐����z
�@�{�w�̐}���ق́A����4�N����w�ł��铌���_�Ƒ�w�Ƌ��p���Ă���B
�@�}�������ɂ��ẮA��{�I�ɖ{�w����������w�╪��ł���L�`�̔_�w�֘A������̐��}���𒆐S�Ɏ��W�������A���发�I�Ȑ}�����ʋ��{�I�Ȑ}���ɂ��Ă�������s���Ă���B�w�p���Z���^�[�\�Z�ōw������}���y�ъe���ǂ̎������K��ōw������}���ɂ��ẮA�����Ƃ��Ċw���i��w�@�����܂ށj�̗��p�ɋ����鎑������̂ɑI�肵�A�����̌����p�}���ɂ��ẮA�l������ōw�����邱�ƂƂ��Ă���B
�@�w�p���Z���^�[�Ŏ����}���̑I����@�͕�������B���F����I�����@�́u���v�炢�I���v�́A�e�w�ȁE�ے�����I�o���ꂽ�ψ������X�̎������}���̌����ɕtⳂ����čw���}�������߂Ă���A���́u���v�炢�I���v�𒆐S�ɑI�����s���Ă���B���̑��A�w���E���E������́u��]�}���v�𐏎��t���A�K�v���f���]�����z�Ȑ}���łȂ�����͍w�����A�w���E���E���̗v�]�ɑΉ����Ă���B�Ȃ��A�s���{���j���w�j�W�̎����̎��W�A�]�ˊ��E�������̔_���̎��W�A�Ȃǂ������Ƃ��ċ�������B
�@����A�}���͗��p�҂̗��p�ɋ����邽�߂Ɏ��W�������̂ł���A�`������̂ł���ȏ�A���p�̉ߒ��ŕ�����j���Ȃǂ������A���p�ɋ����Ȃ��ƂȂ蓾�邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃł���B����āA�}���̏��Ђ͋}���ł���B2004�N�x���}�����Ў戵�v�̂����肵�A���Џ����������s���Ă���B
�@�w�p�G���ɂ��Ă��A�L�`�̔_�w�֘A������̎����𒆐S�ɘa�G���E�m�G�����p���I�Ɏ��W���Ă���B�w�p�̈�̊g��Ƒ��l���ɂ���āA�w�ǂ��K�v�ȎG����{�����ω����Ă���B���̂��ߊe�w�ȁE�ے��ɃA���P�[�g���s���A�e�G���i�^�C�g���j�̕K�v�x�̒������s���Ƌ��ɁA�G���i�^�C�g���j���Ƃ̗��p�����Ă�����ŁA�p���������ΏێG���i�^�C�g���j�����X�g�A�b�v���A�ŏI�I�ɉ^�c�ψ���̏��F�Ď��{���Ă���B�_��ɂ��ẮA���i���̂��߂̃R���\�[�V�A���ł���JUSTICE�֎Q������Ƌ��ɁA3�L�����p�X�ꊇ�̌_��ɂ���ċ��z��}�����Ă���B
�@�d�q�W���[�i���́A���ݍw���_�Ă���^�C�g�����͖�5,400�^�C�g���ł���B���q�̍w���̕��Y���Ƃ��Ė����ŃA�N�Z�X�ł���d�q�W���[�i���́A�ɗ͉{���ł���悤�Ƀz�[���y�[�W��Ƀ����N���쐬���Ă���B�����̓d�q�W���[�i���́AOPAC�֏����������ƂƂ��ɁA��p�̌����c�[����p�ӂ��邱�Ƃŗ��������߂Ă���B
�@�w�p�G���̔��e�ɓ��鎑���Ƃ��āA����������B�����́A������������Ȃǂ̑��̂ŁA�ꎟ�����ł���}����w�p�G�����̂��̂�T�����߂̎����ł���B�w�K�����ւ̗p�r�ɉ����A�����̋Ɛѕ]���Ɍ������Ȃ������ł���B�{�w�̐�啪��ɕK�v�ȓ����f�[�^�x�[�X�����A���p���i�Ɍ����ču�K������{���Ă���B
�@�����o�����ɂ��ẮA�I���W�i�������E�M�d�����d�q���̉ߒ��ŁA�����Ԃ̕ۑ��ɑς�����}�̂Ƃ��āA�����̃}�C�N���������{���Ă���̂ŁA���̕��ɂ��Ă͍�����������čs���\��ł���B
�@�w�p���Z���^�[�}���ٓ���2013�N�x�J�ٗ\��̐V�}���ٓ��i���́j�ւ̈ړ]�����Ƃ���2011�N10������A�����̍u�`�������C�������}���قł̉^�p�ƂȂ�B
�@���}���ٓ��̖ʐςƎ��������\�͎͂��̂Ƃ���ł���B
�������� |
��� |
�p�r�敪 |
�ʐ�
�i�u�j |
���������\�́i���j |
���}���� |
�T�[�r�X
�X�y�[�X |
�{���X�y�[�X
���[���X�y�[�X
���̑��i��c�����j |
1,140
130
40 |
|
�Ǘ��X�y�[�X |
�J�ˏ���
���{���X�y�[�X�Ƌ��L
�����X�y�[�X |
1,140
120 |
140,000 |
���v |
|
|
1,430 |
140,000 |
���ʐϋy�ю��������\�͉͂��݂ɂ��T�Z
�@�w�p���Z���^�[�}���ق̉��}���قɂ����鎑�������\�͂́A��14�����ł���B����57�����̏����̂������}���قɎ����ł��Ȃ��}��������43�����́A�O���̑q�ɂɗa�����p�҂̐����ɉ����Ď��ĉ{���T�[�r�X���s���B
�@�V�}���ٓ��i���́j�́A�v��ł͐}�������̎����\�͂��J��22�����A����������40�����̌v62�����ł���B�T�[�r�X�X�y�[�X�Ƃ��Čʊw�K�Ȃ͒ʏ�G���A�ƐÎ�G���A��p�ӂ��A�O���[�v�w�K���������葝�݂��A��w�j�����i��w�j�A�{�w���Ɛ��_�������A�M�d�������j���ʂɐ݂���v��ł���B
�@�w�p���Z���^�[�}���قɂ�����2011�N�x�̊J�َ��Ԃ͎��̂Ƃ���ł���B
�j�� |
�s���� |
�J�َ��� |
���@�� |
���ƁE�������Ԓ� |
9:00�`21:00 |
�t�E�ċG�x�Ɗ��Ԓ� |
9:00�`20:00 |
�y�j�� |
���ƁE�������Ԓ� |
9:00�`17:00 |
�@2010�N�x�N�ԊJ�ٓ����͎��̂Ƃ���ł���B
�N�ԊJ�ّ����� |
�y�j�J�ٓ��� |
�x���J�ٓ��� |
281 |
13 |
5 |
�@����Ղɂ��ẮA3-4�N�������Ƃ���X�V���A3�L�����p�X�����̈ψ���̂��ƍs���Ă���B
�@�w�p���Z���^�[�}���ق̃l�b�g���[�N�V�X�e���̊Ǘ��E�^�c�Ɩ��́A�R���s���[�^�Z���^�[���s���Ă���A�c�[����R���e���c�̊Ǘ��E�^�c�́A���w�p���Z���^�[���s���Ă���B�Ǘ����e�́A�w���J�����̑ҋ@�A���o�C�g�̔z�u�A�l�b�g���[�N��p�\�R���g���u���������̑Ή��A�����e�i���X�A�X�V���̌v����蓙������B
�@�w�p���Z���^�[�ɂ����闘�p���́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@���p�҃T�[�r�X�ɒ��Ă���p�\�R���́A�f�X�N�g�b�v55��A�m�[�g�^20��ł���B�}���ق̒���R���e���c�ȊO�ɂ��A�w���l�b�g���[�N�Œ����e��T�[�r�X�𗘗p���邱�Ƃ��\�ł���B�f�X�N�g�b�v�̂���5���OPAC��p�[���Ƃ��āA�e�L�����p�X�����̉��f�����V�X�e������Ă���B�܂��A�w�_�ƃZ���T�X�x�d�q�}�̂𗘗p���邽�߂̐�p�[����p�ӂ��Ă���B
�@�}���ٓ��̉{�����ɂ͖���LAN���z������A�ݏo�p�m�[�g�p�\�R���◘�p�Ҏ����p�\�R���̗��p�ɑΉ����Ă���B
�@�܂��A����22�N�x�̍X�V�ɂ�����SSL-VPN�T�[�r�X���J�n����AIP�F�Ō_���R���e���c�𗘗p�҂̎����O�o�悩��̗��p���\�ƂȂ����B
�@�����o�@�ނ̑ݏo�́A�f�W�^���J�����E�r�f�I�J�����E�v���W�F�N�^�E�X�N���[���Ȃǂł���A�����o�������{������DVD�v���[���[2���ݒu���Ă���B
�y�_���E�]���z
�@�}���̑I���ɂ������ẮA���F�̂���I�����@��������Ă���A�T�˖{�w�̋���E�����ɗL�����p�����}�����I������Ă���B���Ɋw�p���Z���^�[�}���قŎ��{�́u���v�炢�I���v�͑I�����̊m�ۂ��K�v�ł���Ƌ��ɁA���O�����E���㏈���ɑ���ȘJ�͂�v���邪�A��������Ɏ��A���e���m�F������ōw���̉ۂ����f�ł���Ƃ����傫�ȃ����b�g������B�������Ȃ��炱�̕��@�����ɗ���ƁA���X�����v�炢�p�ɑI�{�̒����炵���I���ł��Ȃ��Ƃ����댯�����͂��ł���B����y�ь����ɖ��������I�[�����E���h�Ȑ}���̑I���E���W�ɔ�ׁA�����I�ȃR���N�V�����̍\�z�����܂�i��ł��Ȃ��̂�����ł���B�܂��A�����_���Ŗ��炩�ɂȂ����s�ǃf�[�^�̏������K�v�ƂȂ��Ă���B
�@���݊w�p�G���ɂ��ẮA���q�̂���d�q�W���[�i���ֈڍs����ߓn���ł���A�^�C�g�����ƂɁu���q�݂̂̂̂��́v�A�u���q�́{�d�q�W���[�i���̂��́v�A�u�d�q�W���[�i���݂̂̂��́v�Əo�Ō`�Ԃ��قȂ��Ă��邽�߁A�I���E���W���j�����ɗ��ĂÂ炢�ƂȂ��Ă���B�܂��A���ɍ��q�̂̍w���𒆎~����ꍇ�́A���{�G���������Œ��f���邱�ƂɂȂ邽�߁A�w���I�ȃR���Z���T�X�̍\�z���K�v�ƂȂ�B
�@�w�p�G���A���ɗm�G���̉��i�����ɂ��ẮA�C�O�̂������̓Ɛ�I�ȏo�ŎЂɗ��炴��Ȃ��\���I�ȏo�ŊE�̏����݂��Ă���A�Ȃ��Ȃ��X�̑�w�}���ك��x���ł͑Ώ�������Ȃ��ɂ���B
�@�w�p���Z���^�[�}���ٓ��́A2013�N�x�J�ٗ\��̐V�}���ٓ��i���́j�ւ̈ړ]�����Ƃ���2011�N10����������̍u�`�������C�������}���قł̉^�p�ƂȂ��Ă���B���̂��߁A�}���ِݔ��̋K�́A�@��E���i�̐����Ƃ��̓K�ؐ��̓_���E�]���ɂ��ċL�q����ɂ͎���Ȃ��B�������A���݂̗��p�҂̗v�]�܂����}���قł̐����ɂ��ẮA�K�X���i�߂Ă��������B
�@�{�����Ȑ��ɂ��ẮA���}���قł̉^�p�ƂȂ��Ă��邽�߁A�[���Ȑ����m�ۂ��Ă���Ƃ͌����Ȃ��B���̂��߁A����͌��L�K�͂̒��œK���ɐ�������悤�w�߂����B�܂��A�J�ٓ��E�J�ٓ����ɂ��ẮA����̎��{�̐��ɂ����Ă����ނ˗��p�҂̊�]�����Ă��邪�A�ٓ��ɐݒu���Ă��鎿��E���k�J�E���^�[�ɔ_�w���C�߂����t�@�����X�ɐ�O�ł���E����z�u�����p�҃T�[�r�X�̊g���ڎw���Ă��邱�Ƃɂ��ẮA���̎��{�̐��̍\�z���s�\���ł���B
�y�����̉��P��z
�@�u���v�炢�I���v�̃f�����b�g�i���X�����v�炢�p�ɑI�{�̒����炵���I���ł��Ȃ��Ƃ����댯���j�����P���邽�߂ɁA���̑I�����@�i�X���I���Ȃǁj�p���ĕ⊮������A���炩���ߐ}���ّ��ŗl�X�ȏo�ŏ������W������A���X���ɑ��Č��v�炢�ɓW������}�����w������ȂǁA�}���ّ���̂̑I�����s���邽�߂̕�����������Ă���B�܂������E�}���و����o�����X���I��������ɏ[�����������B
�@�I���ɂ������ẮA�����I�ȃR���N�V�����̍\�z�Ɍ������u����܂��̓e�[�}�v�̐ݒ���тɂ��́u����܂��̓e�[�}�v�ɉ������d�_�I�Ȏ��W�E�I���̎��_���K�v�ł���A�V���{�̎��W�����ł͂Ȃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͌Ï��X�Ƃ̘A�g�ɂ�鎑�����W�̕K�v�����������Ă���B
�@����I�ȑ����_���v�������E���{���A���N�ɂ킽�菊�ݕs���Ȗ{��A�����͂̏o�Ă���{�ɂ��ẮA�u�}�����Ў戵�v�́v�Ɋ�Â��āA���Џ������s���B�܂��A���p���l���������}���ɂ��Ă��A���v�̂Ɋ�Â��ď��Џ������s���Ă���B
�@�w�p�G���ɂ��ẮA��������q�̂��w�����ăo�b�N�i���o�[�ɂ��Ă����{�ۑ����p��������̂ƃo�b�N�i���o�[�̕ۑ��͒��~���A�ŐV�̓d�q�W���[�i���ł̒����C���Ƃ�����̂Ƃ̋敪���ɂ��Ċw���I�ɃR���Z���T�X�Ď��{���A�V���Ȋw�p�G���̑I���E���W���j������v�悵�Ă���B
�@�܂����݁A�w�p�G���͏o�Ō`�Ԃ����q�̂���d�q�W���[�i���ւƈڍs����ߓn���ɂ���A����m���ɓd�q�W���[�i������̂ɂȂ��čs���\���������Ǝv����B���̋@����Ƃ炦�A�d�q�W���[�i���ւ̃V�t�g�ɂ������ẮA�P�ƂŌ_����s���̂ł͂Ȃ��A�l�X�ȑ�w�̂܂Ƃ܂�ɂ��R���\�[�V�A���iJUSTIS�Ȃǁj�ϋɓI�ɎQ�����A�R���\�[�V�A���S�̂Ƃ��ďo�ŎЂƂ̉��i�����s�����Ƃʼn��i�����Ɏ��~�߂�������w�͂����Ă���B
�@2013�N�x�J�ٗ\��̐V�}���ٓ��i���́j�ւ̈ړ]�ɂނ��āA�}���َ{�݂̋K�́A�@��E���i�̐����ɂ��ẮA���̓K�ؐ������㌟�����Ă��������B�܂��A�w���{�����̍��Ȑ��A�J�ٓ��A�J�َ��ԁA�}���كl�b�g���[�N�̐������A�}���ٗ��p�҂ɑ��闘�p��̔z���̏ɂ��Ă��A���̓K�ؐ������㌟�����Ă��������B

|
|
|
|
|