| |
|
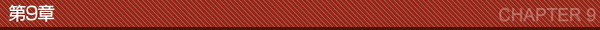
【事務組織と教学組織との関係】
【現状の説明】
教学組織は、自らの教育・研究活動を充実させ、学生の教育にあたる。事務組織は教育・研究活動にあたる教学を支援する立場にある。事務組織と教学組織はそれぞれに機能があり、大学運営上欠くことのできない相関関係にある。本学では、事務組織と教学組織は常に一体化した大学運営を行っている。学長のリーダーシップと短期大学部部長により、教学の方針を学部長会(短期大学部部長、事務局長・事務部長相当職も構成員)、全学審議会(短期大学部部長、事務局長も構成員)、大学運営会議(短期大学部部長、事務局長・事務部長相当職も構成員)、短期大学部教授会(事務局長・事務部長相当職も出席)において大学全体としての意思決定をしている。これら大学運営全体に係る諸会議には、教学の立場と事務の立場からの両者が出席し、それぞれ独自性を保ちながら協力している。
決定された方針は、学科長会及び事務局各部署に周知し、教員組織と事務組織が迅速に対応している。大学の方針は教学、事務組織とも常に一体化している。
【点検・評価】
学長からの方針は、大学運営会議、学部長会、学科長会、全学審議会及び教授会において示され審議された後、事務組織では事務局長から事務連絡会等により各所属長をとおして職員に周知している。
一方、学長の方針に基づく教員組織における意思決定のプロセスに事務組織がどのように関与できるかが重要である。事務組織は、学長の考えに基づき、方針と法律・規程との整合、進捗管理、法令遵守との関係、想定されるリスクの大きさ等について情報を収集しそれを踏まえ、学長及び教員組織に対してその根拠を説明する役割が求められる。
事務組織と教学組織は、連携する関係である。大学の目的を実現させることや、サービスの提供のためには、常に双方の良好な協調関係があってこそ実現されるものである。
半面、教育研究が置かれた現状は変化が激しく、その変化に対応するためには、教学組織と事務組織は必ずしも協調関係が保たれればよいということではない。これは双方の立場を尊重し、必要以上に介入しないという縦割り組織となり、結果として組織が硬直化し、新たな取り組みへの障害となる可能性も秘めている。
【将来の改善策】
学長等の方針に基づく意思決定を円滑に進めるためには、事務組織にマネジメントの機能が必要となる。したがって、管理職にマネジメント能力を有することを必須とすること、管理職登用に向けて、育成・養成に具体的なプログラムを作成し、運用することが必要となる。ただし、これは即効果がでるものではなく、一定の年数を必要とする。5年10年の中長期的計画に基づいて継続的に実施する必要がある。

|
|
|
|
|