| |
|
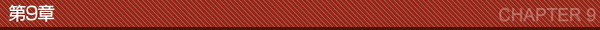
【事務組織の整備】
【現状の説明】
本学は、併設大学である東京農業大学の世田谷キャンパス内にある。事務組織は、併設大学を有するメリットを最大限に活かして東京農業大学の事務組織と一体となり運営している。学科事務担当以外の職員は、すべて東京農業大学の事務組織を兼務している。よって、以下の記載は、本学と東京農業大学(以下「農大」という。)を包含したものである。
○2006年5月1日現在の人員配置は、以下のとおり。
農大131(世田谷キャンパス93、厚木キャンパス20、オホーツクキャンパス18)人、法人本部46人
(法人全体専任職員256、嘱託職員32、派遣職員32(含委託)、臨時職員31人)
○2011年5月1日現在の人員配置は、以下のとおり。
農大135(世田谷キャンパス96、厚木キャンパス21、オホーツクキャンパス18)人、法人本部45人
(法人全体専任職員253、嘱託職員42、派遣職員68(含委託)、臨時職員53人)
2007年4月から、任期制職員制度を導入した。同制度は、優れた人材を確保しかつ育成することを目的として制定した学校法人東京農業大学任期制一般職員規程に基づき職員を採用するものである。
職員を専任職員として採用する場合は、必ず任期制職員(任期は3年)として採用し、任期中の人事評価において一定基準に達した者を専任職員として任用している。
専任職員の異動(職場移動・昇格・役職任用等)は、毎年度2回、4月と10月に実施している。特に職場移動は、業務繁忙期を避けた10月移動を中心に実施している。異動に係る申請・選考・決定は、法人の異動ルールに基づき新人事評価制度により実施している。
なお、6級(課長補佐相当職)への昇格及び8級(課長相当職)の登用については、筆記試験及び面接試験を行う。また、7級(上級課長補佐相当職)への昇任については、面接試験を行っている。試験結果とフォローアップについては、法人本部長又は大学事務局長が所属長及び本人に対して、面接のうえ文書を手交し改善・育成を主眼とするフィードバックを行っている。
異動に係る所属長及び本人に対する内示は、業務の引き継ぎ・人事評価表の引き継ぎ等に配慮して、異動日の約2カ月前までに行っている。
【点検・評価】
各キャンパスにおける職員1人当たりの学生数は、①学生数÷専任職員、②学生数÷(専任職員+嘱託職員)、それぞれ以下のとおりである。
○2006年5月1日現在
世田谷キャンパス:①95人②91人、厚木キャンパス:①113人②102人、オホーツクキャンパス:①93人②76人
○2011年5月1日現在
世田谷キャンパス:①91人②82人、厚木キャンパス:①134人②122人、オホーツクキャンパス:①100人②78人
2006年度と2011年度の職員配置を法人全体で比較した場合、専任職員は概ね同数であったが、嘱託職員が10人増、派遣職員(含委託)が36人増、臨時職員が21人増加している。
また、職員の採用は、人事規則に定める人事委員会及び人事委員会第二専門委員会において、法人全体の職員数を定め、その職員枠の範囲内で計画し採用している。職員枠の管理は、2006年4月1日現在の事務所管別専任職員(256名)を職員の定員枠とし、原則として採用は退職者の補充のみとしている。この間の業務量の増加に対しては、業務のアウトソーシング、嘱託職員、臨時職員及び派遣職員の採用により対処している。
最近6年間の法人全体の職員採用は、2006年度7人、2007年度7人、2008年度9人、2009年度7人、2010年度7人、2011年度9人、合計46人である。一方、退職者は2005年度8人、2006年度6人、2007年度6人、2008年度7人、2009年度10人、2010年度9人、合計46人で、退職者と採用者が同数であった。
職員の人事評価及び昇格等の結果については、被評価者へのフィードバックは行っているものの、人事評価表自体のフィードバックについては所属長の裁量に任せているのが現状である。人材育成の視点から、人事評価表 自体のフィードバックについて管理職が適切な面接指導ができる体制づくりが必要である。
【将来の改善策】
事務組織の規模及び職員配置は、定められた職員枠内で管理することを継続して行う。
職員の採用及び配置は、法人全体のバランスがとれた教育支援、管理運営体制を整えることを基本にしていることから、法人本部及び法人傘下各部門の職員枠を設定せず、法人全体の職員枠の範囲内で計画し適切に行う。 また、法人全体の学生サービス・教育支援並びに管理運営に係る人件費(職員人件費)の安定化に配慮した採用と職員配置等について引き続き留意する。
人事評価表のフィードバックにおいては、評価点数によるフィードバックに特化することではなく、評価要素(評価項目)に基づき、管理職として普段から具体的な指導、進捗管理ができる能力を保有することが重要である。今後、管理職への定期的な研修を実施し資質向上を進めることで対応する。

|
|
|
|
|