| |
|
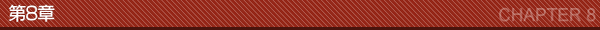
(1)教員組織
【教員組織】
【現状の説明】
教員組織は、学長、短期大学部部長および各学科の教授、准教授、講師、助教、助手(栄養学科のみ栄養士法による実験補助の助手制度がある)からなっている。また、各分野の技術、知識の広がりに対応したカリキュラムの運用のため、嘱託教授、嘱託准教授、非常勤講師なども配置されている。職制上の組織として、学科ごとに学科の運営に関する打ち合わせ、教員会および各学科の必要により作られる委員会、学科を越えた教授会、学科長会および主事会(併設の東京農業大学の委員会と合同)で日常的な運営・調整を実施している。また、各種の委員会(併設の東京農業大学の委員会と合同)の構成委員として各学科から随時選出された委員により会議が開催される。
2008年度「質の高い大学教育推進プログラム(教育GP)」として『学生と教員の協働による学科横断的実学教育』が採択されたことにより、本プログラムを遂行するに当たり、短期大学部長、学科長および各学科からの委員1名で構成される教育支援委員会が設置された。本委員会は、リメディアル教育、初年次教育、学科横断的専門教育およびキャリア教育について教育内容の計画、実行、検証、改善を行い、2010年にプログラム終了後も継続して設置されている。
4学科を連係する研究組織として生活科学研究所が組織され、全教員が構成員として日ごろの研究を社会に還元する共同プロジェクト研究を行い、研究面での連係に機能している。現在専任教員は教授13名、准教授8名、講師3名、助教7、助4名の35名で構成している。全教員が一堂に会し情報交換を行う短大教員会も各学科の持ちまわりで毎年開催されている。
4学科とも短期大学設置基準に基づく教員数で組織される教授、准教授、講師、助教、助手で日常の学科運営がなされている。現場の技術、経験を教授するためにそれぞれの教科を担当する嘱託・非常勤教員は日常の学科運営には関与しないが、各学科において非常勤講師との懇談会を開催しそれらの意見を取り入れており、閉鎖的教員組織にならないように運営されている。
4学科とも主要な授業科目へ専任教員が配置されている。演習・実習科目においては複数教員が配置され、専任・専任、専任・兼任、専任・兼担、専任・兼担・兼任などの組み合わせでカリキュラムに適任教員が配置されている。各学科の専任/科目数、兼担/科目数、兼任/科目数を示す(組み合わせの関係で合計は100%を超える)と生物生産技術学科65.4%、11.5%、50%、環境緑地学科46.3%、32.9%、31.3%、醸造学科57.4%、4.3%、44.7%、栄養学科70%、14%、40%のように、専門科目、教養科目を含めた全科目の50%から70%の科目を専任教員が担当している。
教員組織の年齢構成と性別構成にはアンバランスが見られる。特に性別構成については女性教員数(助手含む)が生物生産技術学科2人/9人、環境緑地学科0人/6人、醸造学科1人/9人、栄養学科7人/14人と,栄養学科以外の3学科において女性教員の比率が少ない。年齢構成と性別構成については、担当教科目の適正人事との兼ね合いを考慮しなければならないので早急な解消は難しい。
教員間の連絡調整は、基本的に毎週開かれる学科会議において行われている。各委員会等学内諸会議で決定、伝達される情報は、学科会議で検討され、適宜学科の状況にあわせた教育課程に調整される。
教員採用に当たっては、大学教員・研究者、社会人、外国人の区別はしていない。専任教員については公募制をとっており、その科目に適した人事を行っている。社会人からの採用は20%から30%に達しているが、外国人の受け入れは応募が無いためなされていない。実学主義を掲げているカリキュラムに必要な現場の技術と知識の教授のため、マイスターセミナーには現役の社会人の講義を開講している。また、英会話担当には外国人非常勤講師も採用している。
【点検・評価】
教育支援委員会において、4学科の教員が一緒に教育内容について議論する機会を得たことにより、短期大学部内の意思疎通が良くなっている。
各学科とも、必修専門科目については概ね専任教員が担当しており、授業時以外の質問等にも対応しやすい。
2014年3月で講師の職階が廃止され、国立大学に準じた職制となる。短期大学部の将来構想が決まっていないことが、教員採用にも影響を与えかねず、早急に将来構想を決める必要がある。
【将来の改善策】
全学改革改善委員会で、東京農業大学における短期大学部の位置づけを再検討し、早急に短期大学部の将来構想を決め、教員組織を再構築する必要がある。

|
|
|
|
|