| |
|
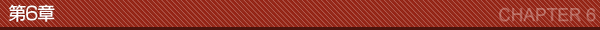
(1)研究活動【研究活動】
〔全体〕
【現状の説明】
本学は、東京農業大学の教育の理念である実学主義に基づき、人格の陶冶、基礎理論に裏打ちされた思考から現場での問題解決能力を身に付けた実践的技術者の養成に耐えうる教員を構成員として、従来の学内での自己完結的研究活動から社会に開かれた研究活動を目指してきた。その結果、他の短大とは異なり、研究が出来る短大と位置づけされている。そのための研究環境は、4年制大学と同程度の高度なものに充実させている。
教員の論文数、学会発表数は他の短大と比べると多く、本学教員の努力を評価することができる。しかし、論文作成数が極端に少ない教員も若干見受けられる。
各教員は、それぞれ4〜5の学会・研究会に所属して、口頭発表、学会誌への投稿などを行っている。論文や研究発表以外に校閲委員、評議員、理事などを務めている教員もいる。また、学内での学会の年次大会などもよく開催され、そのときは重要な職務を担当している。
【点検・評価】
研究と教育は大学教員の役割として両輪の位置にある。教員は研究以上に教育の比重が高い短大において研究成果をあげ、健闘している。さらに、教育活動を啓発するためにも研究活動の活性化が必要である。
【将来の改善策】
教員は、さらなる学科間の共同研究活動の推進や研究領域がオーバーラップする併設大学および大学院との研究連携を強化する。
〔生物生産技術学科〕
【現状の説明】
教員の口頭発表は1人年平均1〜5報と成果がみられるが、論文数は年1〜3報以内である。生物生産技術学科は毎年学内で教員の研究発表会を公開で行っている。
【点検・評価】
教員は、学生指導等に追われ、論文作成の時間的余裕が少なく、夏休みに集中で行われる実験・実習と授業期間が長くなったことから学会出張や国際学会などへの参加も難しい。
【将来の改善策】
事務処理の簡略化等を進め、研究にかけることのできる時間を確保する。
〔環境緑地学科〕
【現状の説明】
研究会・学会、学術雑誌等への発表は、各教員が年間1〜2件実施している。
【点検・評価】
研究は、レベル的には2つに大別され、卒業研究に代表される教育的研究と、教員自身が遂行する継続的な研究である。
【将来の改善策】
教員は、他の研究者との共同研究ならびに学生との卒業研究の論文化を図ることにより、限られた時間の中でも論文数を維持・増加させていく。
〔醸造学科〕
【現状の説明】
各教員は、年に1回程度、国内外の学会に参加・発表しており、他の短大と比べると学会活動等は盛んである。
【点検・評価】
4年制大学と比較すると研究設備や研究費等が少ないが、それ以上に問題となっているのはマンパワーが不足していることである。
【将来の改善策】
醸造学科から、大学運営に携わる役職者を何人も出している事から、学科運営に支障を来たしている面もあるので、役職を均等に配分する等の調整を行う。
〔栄養学科〕
【現状の説明】
教員は、1人が年に1〜2回、国内外の学会に参加・発表している。
【点検・評価】
教員は、十分とは言えないが、短期大学部における研究活動の現状(研究時間、予算、スタッフ数など)から考えると健闘している。
【将来の改善策】
各教員に1年に1回は発表するという目標を持たせて努力を促す。

|
|
|
|
|