| |
|
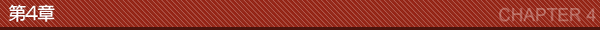
(1)学生の受け入れ方針および受け入れ方法
【入学者選抜における高・大の連携】
〔生物生産技術学科〕
【現状の説明】
複数年にわたり生物生産技術学科への受験・入学実績があり学業成績が良好な高校を指定校として選定している。2011年度入試においては314校を選定した。各年度末に次年度入試要項を検討する際に、指定校推薦による入学者の学業成績、生活態度も検証され次年度の指定校を選定している。
【点検・評価】
指定校の場合、多くは生物生産技術学科の特徴を理解し、適切な人材を推薦しているが、明らかに問題の多い学生が推薦されてきた例もあり、その様な場合は次年度の指定校から外すことにしている。また、学力とともに精神的に大学生活になじめない学生も増加傾向にある。
【将来の改善策】
指定校制度で入学した学生は、成績、生活面ともに良好で、学生の模範となる学生も多く、指定校の意義はあるものの、一部に問題点もある入学者もいることから、毎年見直しを継続していく。
〔環境緑地学科〕
【現状の説明】
環境緑地学科では2011年度入試において87校を指定校として選定した。指定校の選定にあたっては環境緑地学科の教育方針を十分に理解しており、過去にも多くの受験生や入学者のあった高校を対象に選定している。各高校より1名、一部の高校については2名の推薦枠を設定し入学を許可する協力関係を築いている。
【点検・評価】
毎年、指定高校の見直しを行っており、指定校推薦の取り組みにより安定的に優秀な入学者を確保することができている。
【将来の改善策】
毎年、指定校入学者の入学後の学業成績および生活態度を検証し、指定校の見直しを行うことにより指定校との信頼・協力関係を築いていく。
〔醸造学科〕
【現状の説明】
醸造学科においては、2011年度入試において60高校を指定校として選定し、醸造学科のアドミッションポリシーに適合する入学希望者の推薦を依頼している。ある程度の入学実績と入学後の学業成績等を勘案し指定校を選定し信頼・協力関係を構築しているが、一部に基礎学力あるいは醸造学科への適性の面で適切でない例もあり、各年度の指定校選定に際し見直しを行っている。
【点検・評価】
2011年度入試では60高校の推薦指定校中10校から指定校推薦入学者を受け入れた。指定校から一定レベルの入学者が獲得できる反面、指定校における推薦者のレベルチェックがまだ十分に行われているとは言い難いケースもあるので、さらなる高校との信頼関係の構築も重要である。
【将来の改善策】
受験者確保の観点から、指定校推薦制度もある程度必要と考える。公募制推薦入試や指定校推薦での入学者は、総体として一般入試やセンター利用入試による入学者と基礎学力において格差があることから、それを補う学科内容への理解や学習意欲の保持について高校との信頼関係構築をはかっていく。
〔栄養学科〕
【現状の説明】
栄養学科においては2011年度において123校を指定校として選定し栄養学科のアドミッションポリシーに適合する入学希望者の推薦を依頼している。過去の入学実績と入学後の学業成績等を基礎に、特に公募制推薦入試による入学者の出身校の中から選定しているが一部に栄養学科への適格性に欠ける入学者もあり、毎年指定校の見直しと一部差替えを実施している。
【点検・評価】
指定校推薦による入学者は、2011年度は26名であった。過去3カ年も同程度の入数であり安定した入学者数となっている。入試制度別の入学後の学業成績をみると他の入試制度に比較して特に優れているわけではなく、平均的な数値となっているが、一定程度以上の質と入学者数が保障される入学制度として評価できる。
【将来の改善策】
指定校推薦入試による入学者の質の向上には、当該高校とのより深い信頼・協力関係が不可欠であるが、受験者層が公募制推薦入学と重なるケースが多く、指定校数を増加すると募集人数を明示する公募制推薦志願者の質や量が減少することも想定されるので、慎重に対応していく。

|
|
|
|
|