| |
|
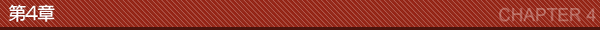
(1)�w���̎�����j����ю�����@
�y�w����W���@�A���w�ґI�����@�z
�y����̐����z
�@��ʓ����i�T���A�U��)�A�Z���^�[���p����(�O���C���)�A���吧���E�����A�O���l�����A�A���q����������юЉ�l�����ɂ��ẮA���i��L����҂�����ł��Ȃ����ƁA�܂��{�w�e�w�Ȃ̃A�h�~�b�V�����|���V�[�ɓK������l�ނ��L�����߂�K�v����A��w�ē�����ё�w�̃z�[���y�[�W�ɓ������x���Ƃ̕�W�l���A���i�ґI����A�ߔN�x�������ʓ����f�ڂ��A�o�菑�ނ̐�������u��E�ɂȂ���悤�L�Ă���B
�@����A�w��Z���E�����A�^���I�萄�E�����A�n���p�Ґ��E�����A���Ɛ��q�퐄�E�����A�����_�ƋL�^�ܐ��E�����A���ݍ��Z�D������A�Z�p���K���D������ɂ��ẮA�I�l�菇�͂��ꂼ��قȂ邪�Ώێ҂����肳��Ă���̂ŁA��w�ē��ɓ������x�̖��݂̂̂��L�ڂ���ɂƂǂ߂Ă���B�܂��������x�̐��i��w�Ȃ��Ƃ̕�W�l�����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂Łu����v�Ƃ��āu��ʓ����̕�W�l���Ɋ܂߂�v�Ƃ��Ă���B
�@��w�ē�����ѕ�W�v���ɂ����ĕ�W�l���L���Ă����ʓ����A�Z���^�[���p��������ь��吧���E�����̍��v�����e�w�Ȃ̓��w����Ɉ�v���邪�A�{�w�͓��w�����1.1�`1.2�{����w�҂Ƃ��邱�Ƃ�ړr�Ƃ��Ă���̂œ��ʑI���������̓��w�҂��z�����Ă���B
�@����w�ґI�����@��@�������x���ƂɁA�����I����e�w�ȓ��̑I�l��c���o�Ċw���A���w���A�Z����w�������A�e�w�Ȓ����\�����Ƃ�������I�l��c�ɂ����č��i�҂����肵�Ă���B
�@�{�w�̓������x���A�I�l��̖ʂ���敪����ƁA�w�̓e�X�g�ɂ���b�w�͂肵���i�҂�I������u��ʓ����v����сu�Z���^�[�������p�����v�Ɠ��Y�w�Ȃɑ���A�w�ӗ~��K���ɂ��I��������吧���E�����A�w��Z���E��������т��̑��̓��ʑI�������ɕ�������B�{�w�ł͖��N�A�݊w���̓������x��GPA(�O���[�h�E�|�C���g�E�A�x���[�W)���w�Ȋw�N���ƂɎZ�o���A�������b�����Ƃ��āA�������x���Ƃ̕�W�l���̌��A���������s���Ă���B
�y�_���E�]���z
�@�{�w�͑��l�ȓ������x�����{�����w�҂�����Ă��邪�A�S�w�Ȃɂ����āA��ʓ����A�Z���^�[�������p�����A���吧���E��������юw��Z���E�����ɂ����w�҂��唼���߂Ă���B�Ȃ��h�{�w�Ȃɂ����Ă͉h�{�m���i�擾��ړI�Ƃ���Љ�l�����ɂ����w�҂����w�҂�5�����x����B
�@�w��Z���E�����͐��x�̐�����A���i��100���ł��邪�A���吧���E�����ɂ����Ă��قڍ��i��100���ƂȂ��Ă���B����͎w��Z���E���x�����{���Ĉȗ��A���吧���E�����Ă����҂̏o�g�Z���w��Z�ɂȂ������Ƃɂ��w��Z���E�����ɕύX����P�[�X���������Ƃɂ��B�w��Z�̑I��ɂ������ẮA�ߋ��̓��w�҂̓��w��̐��ѕ]�����܂߂����w���т��d�v�ȗv�f�Ƃ��Ă���̂ŁA�w��Z�𑝂₷���Ƃ����吧���E�̎u��҂̌����������A���ʂƂ��ĕ�W�l�������Ă�����吧���E�����̍��i����100���߂����l�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł���B���̌��ʁA���w�u��҂̒�����I�������ɂ������I�ɍ��i�҂�I�l�ł��Ă���̂́A��v�ȓ������x�̒��ł́A��ʓ�������уZ���^�[�������p�����݂̂Ƃ������ƂɂȂ�B�������������x�ʂ�GPA�l������ƁA�������x�ɂ��傫�ȍ��ق��݂��Ȃ����Ƃ�����A���吧���E�����̎u��ґ������w��Z�I�萔�̒����ɂ�董���{��ɂ��Ă͐T�d�Ɉ����ׂ��ł��낤�B
�@�܂��e�w�Ȃ̖ړI����уA�h�~�b�V�����|���V�[�ւ̓K���������ۂ̊�Ƃ���A���吧���E��������ъe����ʑI�������ɂ����ẮA���w�҂̉ߔ����A�w�Ȃɂ���Ă�80���ȏオ4�N����w�ւ̕ғ��w����]���Ă���̉��Ŋe�w�Ȃ̖ړI����уA�h�~�b�V�����|���V�[�̑Ó����ɂ��Č������ׂ��i�K�ɂ��Ă���Ǝv����B
�y�����̉��P��z
�@�O���ŏq�ׂ��悤�ɁA�{�����i�ґI�����s����u��Ґ������邱�Ƃ��]�܂������吧���E�����ɂ����āA�w��ǑS�����i��Ԃɂ��邱�Ƃ́A���炩�̉��P�K�v�Ȏ��Ԃł���B���������w��̊w�Ɛ��тɂ����Ċe�������x�Ԃ̍��ق��F�߂��Ȃ�����l����Ƒ��}�ȑΉ����K�v�Ƃ͂����Ȃ��B����ɂ����Ă����吧���E�����ɂ����ẮA���w����(���ށA�ʐځA���_��)�̌��ʁA��b�w�́A�w�K�ӗ~����ъw�ȓ��e�̗���x�̖ʂ���A�w�ɑς����Ȃ��Ɣ��f�����ꍇ�͕s���i�Ƃ��Ă��邵�A�w��Z���E�����ɂ����ē��w�����҂ɏC�w��̖�肪����ꍇ�͎��N�x�̎w��Z�I��ɍۂ����O����[�u���u���Ă���̂ŁA�K���������ȓ��w�҂̑I���͂�����x�ێ��ł��Ă���Ɣ��f���Ă���B
�@�ނ��듖�ʎ��g�ނׂ��ۑ�́A�w�Z����@����ђZ����w�ݒu��ɒ�߂�ꂽ�ݒu�ړI�₱����Ė{�w����߂�����̖ړI����уA�h�~�b�V�����|���V�[�ƒZ����w�����ݒS���Ă���������قȂ��Ă��邱�Ƃɂ���B�������吧���E�����A�w��Z���E��������ъe����ʑI�������̎傽��I����ł���A�h�~�b�V�����|���V�[�ɂ��čČ������K�v�ƂȂ�ƍl���邪�A�䂪���ɂ�����Z����w�݂̍���ɌW��ۑ�ł��낤�B

|
|
|
|
|