| |
|
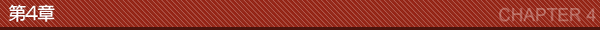
(1)学生の受け入れ方針および受け入れ方法
【入学者選抜の仕組み】
【現状の説明】
1.入学者選抜制度の概要
本学の入学者選抜制度は、大別して次の3制度からなっている。
<1> 一般入試(Ⅰ期、Ⅱ期)、大学入試センター利用入試(前期、後期)
一般入試は本学独自の入試問題、センター試験利用入試は大学入試センター試験の得点により合否を決定する入試制度であり、学力によって合否を判定する。
<2> 公募制推薦入試(Ⅰ期、Ⅱ期)、指定校推薦入試
本学の各学科が定めているアドミッションポリシーおよび大学案内や募集要項に記載された『推薦入学者の要件』に適合する者を、書類(調査書、推薦書)、小論文および面接により選抜する。なお指定校推薦については、制度の性格上適格者の選抜を当該指定校に委ねている。
<3> 特別選抜入試
特別選抜入試には「外国人入試・帰国子女入試」、「運動選手推薦入試」、「地域後継者推薦入試」、「卒業生子弟推薦入試」、「毎日農業記録賞推薦入試」、「社会人入試」、「併設高校優先入試」、「技術練習生優先入試」がある。これら特別選抜入試の内、特色のあるものについては以下のとおりである。
「地域後継者推薦入試」:本学(東京農業大学を含む。)の卒業生により都道府県単位に組織されている校友会支部から、将来地域社会のリーダーとなりうる人材として推薦された者について選考の上入学を許可している。
「卒業生子弟推薦入試」:地域または産業社会で実践的に活躍する本学卒業生の子弟で、将来、国際的かつ社会的に貢献が期待できる人材について選考の上入学を許可している。
「毎日農業記録賞推薦入試」:毎日新聞社が主催する毎日農業記録賞(高校生部門)に応募し優秀賞を受賞した者について選考の上入学を許可している。
「技術練習生優先入試」:本学および東京農業大学が設置する農場および演習林に所属する技術練習生の中から推薦された者について選考の上入学を許可している。
2.入学者選抜実施体制
入試センターにおいて各年度末に、次年度の入学者選抜の要項(入試日程、受験資格、選抜基準、募集人数等)を、各学科の要望をふまえて原案作成を行い、入試委員会(学長、副学長、短期大学部部長、入試問題調整委員長等で構成)、入試選考会議(入試委員会構成員に各学科長を加え構成) の議を経て最終的には教授会の承認を得ている。
入試センターは、この決定を受け大学案内の作成・配布、募集要項の作成・配布、ホームページ上への掲載等入試広報活動を行う。さらに定められた入学者選抜要項に従い、各種入試制度について志願表の受付処理、入学試験の実施、合格者の発表、入学手続き処理および入学者の確定等を行う。なお業務量の多い一般入試等については、他部署の職員から選抜された入試実行委員の協力を得て業務を遂行している。また必要に応じ厚木キャンパス入試課、オホーツクキャンパス入試課の協力を得ている。なお入学試験の監督業務については、各学科教員に依頼している。
一般入試Ⅰ期においては、全国6会場の地方試験会場を設定しており、この地方会場の試験運営については外部業者に委託し、本学職員2名を現地責任者として各地方会場に派遣し試験運営の管理にあたっている。
【点検・評価】
本学の入学者選抜試験の実施所管は入試センターであり、併設の東京農業大学の入学者選抜業務も併せて担当している。前項で述べたように多様な入試制度は併設大学においても実施されており、併設大学で実施している編入学試験を含めると、毎年9月中旬から翌年3月末まで入学者選抜業務に携わることになる。入試センターの業務としては入試広報についても担当業務としており、両業務のバランス配分に苦心するところであるが、入試広報と入試の実施の担当部署を分割することのデメリットもあり今後の課題であろう。現行の入学者選抜試験実施体制は、2006年度から実施されているが地方試験会場の外部委託を含めて遺漏なく運営されている。また世田谷キャンパス入試センターと厚木キャンパス入試課およびオホーツクキャンパス入試課との連携および任務分担も円滑に行われており試験実施体制として特に改善すべき課題はない。
【将来の改善策】
前項で述べたように、現行の入学試験制度を前提とすれば、試験実施体制としては大幅な改善は必要ないと判断している。ただし入学者選抜試験実施体制の中に入試広報も含まれるとすれば、現在併設大学と一体的に実施している本学の入試広報活動の在り方について検証することは無駄ではない。しかし現在の本学受験者の大半が卒業後4年制大学とりわけ併設の東京農業大学への3年次編入を希望している実態を考慮すれば、一概に本学独自の入試広報が有効とは言えないであろう。なお多様な入学試験制度の検証については次項で述べる。

|
|
|
|
|