| |
|
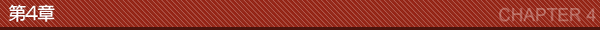
(1)学生の受け入れ方針および受け入れ方法
【入学生受け入れ方針等】
〔全体〕
【現状の説明】
本学は、生物生産技術学、環境緑地学、醸造学および栄養学に関する専門職業における技術者養成に重きを置く大学教育を施し良き社会人を育成することを目的としており、各学科のアドミッションポリシーもこの目的に基づいて定められている。しかしながら我が国の短期大学は、18歳人口の減少、経済不況の影響をうけて大幅な志願者減少を招いている。多数の短期大学が募集停止や4年制大学への改組を迫られる中で、本学は2011年度入試においても募集人数を大幅に上回る志願者を確保している。その大きな要因の一つは併設する東京農業大学への3年次編入学を視野に入れた併願受験者の存在である。併設の東京農業大学には本学の設置する4学科と同一分野および関連分野の学科が多数設置されており、編入学試験を経て卒業生の約35%が併設大学に進学している。また関連分野を有する他の4年制国公私立大学へ進学する者もおり、卒業後の進路の約半数が4年制大学への進学となっている。
【点検・評価】
入学者の約80%が4年制大学への編入学を希望しており卒業時に約50%が進学している現状をふまえ、本学も設置目的に沿った実験、実習,演習に重点を置いた専門教育を施すとともに過半数を超える編入学希望者に対し、編入学試験対策および編入学後の4年制大学の教育課程への円滑な移行を保証するカリキュラムが求められている。このことに対応するため、2010年度に教養科目および外国語科目を強化するカリキュラム改正を実施した。これにより編入学希望の学生に対する配慮についてはある程度対応できたが、一方で短期大学本来の目的である専門技術教育のプログラムを維持することが困難になっている。
【将来の改善策】
時代の変化により、既に短期大学の存在意義は薄れており、本学各学科の目的およびアドミッションポリシーと多くの入学者の志望理由はかけ離れたものになっている。現在本学は入学定員を一定程度の高いレベルで充足しているが、現行の4学科体制では将来、受験生の確保が難しい時期が来ると考えられる。併設大学とのすみわけを考慮しながら、新しい4年制大学の学科への改組や、短期大学で存続可能な学科の検討など長期的視野で改革を考えていく。
〔生物生産技術学科〕
【現状の説明】
生物生産技術学科は、動植物の生産について、環境との共生を図る持続的な生物生産体系を学べるように、講義と実験・実習を連動させた特色ある実学教育を行っている。2年間の実践的な教育により、専門知識と技術、教養を併せ持つ専門的な社会人として社会に貢献できる人材を養成することを目的としている。アドミッションポリシーにおいて、農業(畜産含む)または関連産業の経営者、技術者、指導者を目指そうとする者、さらに動植物に興味を有し、身につけた知識と社会に貢献しようとする意欲的な人材を求めている。
教育の目的、アドミッションポリシーに基づいた多様な人材を養成することから、入学者選抜方法も一般入試、公募制推薦入試、指定校推薦入試、センター試験利用入試、外国人・帰国子女入試、社会人入試、地域後継者推薦入試、卒業生子弟入試、農場技術練習生および併設高校からの優先入試等と、多様な選抜方法で行っている。
【点検・評価】
入学する学生の出身高校は、農業科等の専門高校が多いが、普通科や社会人経験者も毎年入学している。入学してくる学生は、動植物に関心が高く、生物生産技術学科の受け入れ方針をよく理解しており、2年間で目的を達成して社会に出る学生もいるが、近年は4年制大学への進学希望者が多くなっている。
推薦入試の受験者の多くは農業系専門高校出身で、当該高校から推薦された生物生産技術学科の理念・教育目標やアドミッションポリシーにふさわしい生徒であり、入学後も学習意欲がある学生が多いが、一部にふさわしくない者も見られる。社会人入試での受験者は少ないが、目的意識が高く、模範的な学習態度で他の学生に好影響を与えている。普通科出身者の場合は、実験、実習に馴染むのに時間を要する場合もあるが、比較的に基礎学力が高く、習熟度が早い傾向にある。基礎学力の面では、出身高等学校での教育課程が異なり学生間の差が大きいが、リメディアル教育科目の履修や専門科目を受講し指導を受ける中で、徐々に是正されている。
【将来の改善策】
専門知識と技術、教養を併せ持つ専門的な社会人として社会に貢献できる人材を養成することを目的としているが、4年制大学への進学者が漸増していることや、4年制大学卒業後に就農するケースも増えており、卒業後の進路は多岐にわたる。キャリア教育の充実とともに専門的知識と技術を高めることも重要である。2010年度からカリキュラム改正を実施し専門科目を少なくし、一般教養的科目を増やしたことから、教養を高めるのに好影響を与えている一方、専門科目が減少したことから学習意欲が低下している学生もおり、卒業後の進路に応じた柔軟な選択性に富んだカリキュラム運営を検討する。
〔環境緑地学科〕
【現状の説明】
環境緑地学科は、人間の生存に不可欠な自然との共生の場としての緑地について、総合的な機能との調和を図るための知識・技能の習得を通した全人的教育を行うことを目的としている。そのアドミッションポリシーにおいて、公園、庭園、里地・里山および自然植生などの緑地、植物・昆虫・動物、生物多様性などの自然環境分野ならびに環境問題に興味・関心を持ち、時代の要請に則した、緑豊かな生活環境の創造、自然との共生を実現するために努力を惜しまず、知識・技能を身につけようとする意欲を持つ人材を求めていることを明記している。
環境緑地学科は2年間の教育期間において、その教育目標や理念、アドミッションポリシーに基づいた人材教育を完結させることを目指しており、関連分野においては全国的にも少ない貴重な教育機関であると考える。したがって、入学者の選抜にあたっては、入学希望者の高等学校等での教育課程に拘わらず、均等に受験の機会が与えられるよう、「基礎学力」基準、「興味と目標」基準、「履歴と自覚」基準の3つの異なった入り口による入学者選抜を実施している。具体的には一般入試、推薦入試、社会人入試等である。このように、学力的に多様な学生が入学するために、学科の教育課程においては入学生全てに無理なく履修できるように科目およびその内容の検討が行われている。
【点検・評価】
環境緑地学科に入学してくる学生の出身高校は、農業系専門高校と普通科が中心であるが、商業科等や社会人経験者も毎年入学している。これらの学生は、環境緑地学科の受け入れ方針をよく理解しており、学科の教育目標、方針に従った学生生活を送っており、2年間の短期間で専門的な技能・資格を取得する学生も少なくない。
一般入試および公募制推薦入試では、教育課程の関係から普通科や総合学科出身の受験生が多く、農業系学科の出身者は少ない。それに対し、農業系学科の出身者に対しては指定校推薦制度で対応しており、当該高校から推薦された本学の理念・教育目標やアドミッションポリシーにふさわしい生徒を受け入れている。それらの農業系学科出身者は、入学後も専門分野で積極的に努力している学生が多い。社会人入試は一度社会に出た後、自分の将来を熟考して入学する学生が多く、しっかりとした目標意識を持っている。学生によって高等学校での教育課程が異なっていることが多いため、基礎学力の面では学生間の差が大きい傾向があるが、リメディアル教育科目の履修や専門科目を受講し指導を受ける中で、徐々に是正されている。
【将来の改善策】
環境緑地学科では、関連分野の4年制大学、特に併設の東京農業大学への編入希望者が全体の70〜80%に及んでおり、2年間で修得した知識・技能をすぐに社会で役立てたいと考える学生の割合は徐々に低下しているのが実情である。そのため短期大学本来の教育目標や受け入れ方針が適切であるかどうか、その判断が難しい側面を抱えている。このような現在の短大教育の置かれている状況を踏まえ、近い将来を見据えた改革を検討する。
〔醸造学科〕
【現状の説明】
醸造学科は、清酒、ワイン、ビールなどの「酒類」、味噌・醤油、ヨーグルト、パンなどの「調味食品」、生物工業に関する「微生物」、さらに醸造物および食品の成分分析等に関する「食品分析」についての科学的知識を基礎として、資源・バイオマスエネルギー・環境の分野においても、幅広い視野を持って活躍できる技術者の養成を行っている。アドミッションポリシーにおいて、実学主義をモットーに掲げ、実験・実習や演習を重視した教育を行い、問題解決能力の高い人材の育成を行っている。
2年間の教育期間において、その教育目標や理念、アドミッションポリシーに基づいた人材教育を完結させることを目指しており、関連分野においては全国的にも少ない貴重な教育機関であると考える。したがって、入学者の選抜にあたっては、入学希望者の高等学校等での教育課程に拘わらず、均等に受験の機会が与えられるよう、「基礎学力」基準、「興味と目標」基準、「履歴と自覚」基準の3つの異なった入り口による入学者選抜を実施している。具体的には一般入試、推薦入試、社会人入試等である。このように、学力的に多様な学生が入学するために、学科の教育課程においては入学生全てに無理なく履修できるように科目およびその内容の検討が行われている。
【点検・評価】
醸造学科に入学してくる学生の出身高校は、普通科が中心であるが、農業系専門高校や総合学科のほか社会人経験者も毎年入学している。これらの学生は、醸造学科の受け入れ方針をよく理解しており、学科の教育目標、方針に従った学生生活を送っており、2年間の短期間で専門的な技術を身につける学生も少なくない。
一般入試および公募制推薦入試では、教育課程の関係から普通高校や総合高校出身の受験生が多く、農業系専門高校の出身者は少ない。それに対し、農業科等専門高校の出身者に対しては指定校推薦制度で対応しており、当該高校から推薦された本学の理念・教育目標やアドミッションポリシーにふさわしい生徒を受け入れている。それらの農業系専門高校出身者は、入学後積極的に努力して勉学に励んでいる学生が多い。社会人入試は一度社会に出た後、自分の将来を熟考して入学する学生が多く、しっかりとした目標意識を持っている。学生によって高等学校での教育課程が異なっているため、基礎学力の面では学生間の差が大きいが、リメディアル教育科目の履修や専門科目を受講し指導を受ける中で、徐々に是正されている。
【将来の改善策】
醸造学科では、関連分野の4年制大学、特に併設大学への編入希望者が全体の75〜80%に及んでおり、2年間で修得した知識や技術をすぐに社会で役立てたいと考える学生の割合は、年々減少している傾向にある。卒業時約60%の進学と約40%の就職になっているのが現実である。そのため短期大学本来の教育目標や受け入れ方針が適切であるかどうか、その判断は難しい。このような現在の短大教育の置かれている状況を踏まえ、近い将来を見据えた改革を検討していく。
〔栄養学科〕
【現状の説明】
栄養学科は、建学の精神である実学と自治を根幹とし、食料の生産から加工・流通・消費および栄養までの幅広い知識を習得させ、国民一人ひとりが心身ともに健康で豊かな生涯を送れるように、食生活の改善や運動を通して、心と体の健康づくりに貢献する栄養士を養成することを目的としている。
アドミッションポリシーとして、食料の生産から消費までの流れの中で、特に食と健康の問題に対応できる専門的な技術者を目指すもの、さらにはこれらを科学的な視野で客観的に捉え、新たな時代の食生活と健康を創造できる意欲あふれる人材を求めている。
栄養学科は2年間の教育期間において、短期大学の教育目標や理念、アドミッションポリシーに基づいた人材教育を完結させることに加えて栄養士養成としての教育を目指している。近年、栄養士養成を行う短大が4年制の管理栄養士養成課程に移行する事例が多い中で、本学栄養学科は一定のレベルの学生を確保している。また栄養学科は卒業論文を必修とすることで短大の中では、高い水準での研究力を確保できる形になっている。このことは意欲のある入学希望者の確保にもつながっている。また卒業後3年間就労の後の管理栄養士国家試験の合格率が2011年度は30%を超え、他の栄養士養成施設の合格率と比較しても高水準である。しかしながら短大への入学希望者が徐々に減少していくのは社会全体の趨勢として抗しえない部分もあり、現状では質の確保と定員の確保の狭間で推薦入試と一般入試の募集人数比率の変更などを行い方向性の見極めを行っている。
入学者の選抜にあたっては、栄養士の職業意識の高いものを基準のひとつとして考えている。その上で入試の方式として、すべての入学希望者に均等に受験の機会が与えられるように、具体的には一般入試、推薦入試、社会人入試等が行われている。また今日、学力的に多様な学生が入学することが認められているのも事実であり、学科の教育課程においては入学生全てに無理なく履修できるように科目およびその内容の検討が行われると共にリメディアル教育を導入し基礎的な学力の底上げをめざしている。
【点検・評価】
栄養学科に入学してくる学生の出身高校は、普通科が中心であるが、農業科等専門高校出身者も毎年入学している。多くの学生は、栄養学科の受け入れ方針をよく理解しており、学科の教育目標、方針に従った学生生活を送っている。また栄養学科は社会人が毎年10名前後と、他の学科と比べると割合が高いのも特徴的であり、高学歴の者が多くみられる。再度学ぼうという強い姿勢がみられ、一般の学生にとってよい意味で刺激となっていることが多い。2年間の短期間で専門的な技能・資格を身につけることが出来ることから、目的を持った社会人の入学希望者は一定人数が見込まれる。また一般学生も進学と就職希望者がほぼ半数ずつとなっており偏った教育は出来ない。現時点ではほとんどの学生が栄養士資格を取得し卒業することを目指しているので大きな問題はない。
現状としての課題は、入学生の進路との関係である。完結型教育を目指すところであるが、就職が半数にとどまり、約半数は4年制大学への編入学を希望している。栄養学科の基本的な考えとしては栄養士免許取得、栄養士としての基本スキルの取得によって完結させることが重要と考えている。
多様な学力の学生が入学してくることを踏まえて少人数での授業展開、個別担任による指導、卒論指導など学生の状況を確認しながらのきめ細かい教育が進められていると評価している。
【将来の改善策】
栄養学科では、入学時調査で関連分野の4年制大学、特に併設されている東京農業大学栄養科学科食品栄養学専攻および管理栄養士専攻への編入希望者が多くを占めているが、編入学定員は2専攻合計で12名と少なく、積極的に併設大学栄養科学科への編入学を勧めることは適切ではない。しかし食品・栄養関連学科は、併設大学に生物応用化学科をはじめとして食品香粧学科などいくつか存在することや、栄養士資格はすでに取れることから異なったスキルを身につけるために、併設大学の国際農業開発学科、食料環境経済学科、国際バイオビジネス学科などへ幅広く編入を希望する者もみられる。ここ数年の実際の進路状況をみると、編入・進学と就職がほぼ半数ずつで推移している。栄養学科では栄養士として2年間で修得した知識・技能をすぐに社会で役立てたいと考える学生は、就職希望者の約半数であり、この割合の大きな変動は見られない。これらの結果から教育自体の大きな方針変更は考えられないが、短大志望の学生が減少する傾向にあることと、卒業後の進路の安定性を考えると定員変更など近い将来を見据えた改革を検討していく。
推薦入試等では面接により栄養士養成の特殊性に対する意識確認ができているが、一般入試等では志望者に対する説明を十分に行える広報活動にも工夫を行う。

|
|
|
|
|