| |
|
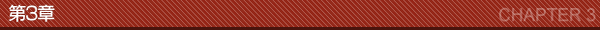
(2)教育方法等
【教育改善への組織的な取り組み】
【現状の説明】
入学後に行う学内外オリエンテーション、フレッシュマンセミナーおよびフレッシュマン演習の機会を利用して学生に学科の特徴、理念を理解させ2年間の学生生活を有意義に送るための目的意識を持たせるようにしている。教育効果を測定するために、学生による授業評価を行っている。フレッシュマンセミナーやフレッシュマン演習、食農体験実習やマイスターセミナーなどの学科横断的専門教育科目など学部共通科目については、教育支援委員会で検証、改善を行っている。また、全学FD・教育評価委員会から授業などの改善策や学生の対応情報などが配信されており、また、学生による授業評価やレポート内容、各種試験結果を参考に教育指導改善を試みている。
シラバスの作成は授業担当者がWeb上で行って、全科目がインターネット上に公開されている。毎年学生の理解度に合わせた講義をするため内容変更や順序の入れ替えが行われる。Webシラバス・授業コミュニティシステムを用い次回の授業の予習範囲を周知できるほか、試験問題例や試験解答などを直ちに学生に知らせることが可能である。
学生による授業評価の活用状況は、講義担当者全員が行っており、各教員は学生による授業評価の結果を把握し、常に自己点検をし、授業に反映している。また、学科によっては学年、学期の節目に開講科目に関して独自のアンケートを行い学科会議で評価し、授業に吸い上げている。また、卒業生の現場からの意見も取り込みカリキュラム、授業に反映している。
授業改善の取組として2002年4月に全学FD・教育評価委員会が発足し、教育活動の持続的改善の取組を多様性・自立性・公開性に置き活動を行っている。また、自己教育評価委員会も同時に発足し、教育評価項目の改善を行いながら全教員に対し、Webによる自己教育評価アンケートを実施し、この結果をもって自立的な改善を目指した。現在はこの評価が昇格、他機関兼務、留学などの基礎資料として用いられ、間接的に授業改善に寄与している。文部科学省で採択されたGPプログラムの一環で、授業方法や、学生の個別相談の方法について、全教員に対するFD研修を実施した。
教員の全学的な教育倫理向上を図るためには、教員全体での共通的な認識の醸成と具体性を持った教育倫理啓発施策の構築が必要である。
【点検・評価】
専任教員間では学科会議をはじめ協議の機会があるので指導方法についてのチェックは緊密に行われるが、非常勤講師との教育指導上での情報交換の機会が少ない。学科としてその科目の意義など打ち合わせそれに沿った授業を依頼する必要がある。各学科とも、非常勤講師について年に1回専任教員との懇談会を持ち、学生の学習態度や教育方針について討議し、意志疎通が図れるように努めている。
全教員のFD研修実施により、学生の対応能力の向上に努めるなど、概ね適切に運用されているが、今後もさらなる資質の向上に努める必要がある。
【将来の改善策】
学生による授業評価をどのように各教員が取り入れ指導法を改善したかについて、各教員間で客観的な評価を行うことを検討している。一方、学生による授業評価の精度を向上するため、授業評価への積極的に参加するよう指導を行っていく。

|
|
|
|
|