| |
|
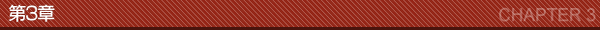
(1)教育内容等【臨床実習・学外実習等】
【現状の説明】
実学主義に基づく即戦力の技術者養成を謳っている各学科はインターンシップを通して、学内の実験実習や授業では経験できない現場における実習が行われ、キャリアデザインの構築に寄与している。栄養学科の学生は学外での病院実習を行っている。
【点検・評価】
各学科とも学外実習終了後は、学業やキャリアデザインに対する理解が向上する学生が多く見られ、有効に機能している。一方、2年間という短い教育期間内での実習であるため、それぞれの学生に適切な実習場所や時期の選定が難しい。実習前後の教育への教員の負担は大きく、トラブルが生じたときの負担はさらに大きくなる。
【将来の改善策】
学外実習は学生の社会性の涵養やキャリアデザイン構築に効果を上げている。一人ひとりが社会の一員であることを認識し、自己責任の意識を高めるなど入学時からの社会人教育がより必要である。フレッシュマンセミナー、共通演習等の活用および研究室活動を通じ社会性を高める教育を強化していく。
〔生物生産技術学科〕
【現状の説明】
学外実習は長年にわたり実施しており、現在は「生物産業インターンシップ」として農業および関連産業の生産、流通、販売までの分野で必修科目として行っている。事前学習としてガイダンスのほか、1年時に前年度実施の報告会に参加して職業意識を持たせ、希望分野を選択し、主として春休み期間に宿泊および通いで実施している。実習終了後に報告書を提出、報告会を開催している。
【点検・評価】
報告の内容を見ると、職業意識を高めるのに効果的であると考えられる。また、実習先に就職する場合もあり、学生の実習効果とともに受け入れ側にも学生の資質を見極めるのに有効である。
【将来の改善策】
学生の職業に対する意識の変化に対応するために徐々に実習分野を生産から流通、販売まで拡大してきているため、この点を配慮して実習分野、実習先の設定を行っていく。教員が実習先に2,3年に1回は訪問して受け入れ側との意思疎通を図っているが、訪問のみでなく、通信手段を生かし、より良い学習成果が得られるようにしていく。
〔環境緑地学科〕
【現状の説明】
学外実習は、学外施設やフィールド(屋外施設)を利用して、学内施設では体験できない作業、観察、調査を行う実学教育である。1年次の必修科目として、フィールド調査実習とフィールド観察実習がある。フィールド調査実習は、野外において景観および動植物の現地調査を行い、実習期間中にそれらの成果を班ごとにポスターにまとめ発表させるもので、2年次の環境緑地専攻演習におけるコース選択のための導入科目ともなっている。2年次のフィールドトリップでは、より専門性を高めた野外観察調査、施設研修を行っている。また、緑地工学実習では農村域において緑地施設の施工等の実践教育を行っている。
【点検・評価】
1年次と2年次との間の春季休暇中には緑化企業実習がある。この学外実習は学生全員が参加しているが、造園業、樹木・草花生産業、環境調査業、環境NGO等の各企業で活躍している専門家から直接、最新の技術や知識が教授され、教室における講義や農場での実習では得られないものを学ぶ機会となっている。
環境緑化および造園業の自営者や後継者、緑化・花卉関連産業の第一線で活躍する有為な人材を育成することを目標としている環境緑地学科において、この緑化企業実習に寄せる期待、評価は極めて大きい。
【将来の改善策】
現在、行われている学外実習は企業体験型の実習であり、実社会現場で活躍するのに十分な技術、仕事の作法を習得するまでには至っていない。長期的な学外実習の可能性を模索し、社会で活躍しうる技術者育成に向けて産学連携型の実習の実施を図っていく。
〔醸造学科〕
【現状の説明】
醸造特別実習(一)では工場実習を行い、醸造特別実習(二)では、企業(醸造・食品会社)での1週間の実習を行い、実際の製造工程を体得している。さらに官能検査演習という醸造製品や食品の官能検査の意義や試験方法を学ぶ実践的な演習科目を配している。
【点検・評価】
醸造特別実習(二)では、履修する学生の多くが日本酒の蔵元に泊まり込みでのインターンシップを行っており、他の大学のインターンシップとはやや異なる特徴あるカリキュラムとなっている。官能検査演習も実践的かつ特徴あるカリキュラムであると考えている。しかしこれらの科目は選択科目であり、卒業間際のやや忙しい時期に行われるため履修者は多いとは言えない。
【将来の改善策】
学生に実習の意義や必要性を理解させ、実施時期を調整するなどによって履修者を増やしていく。
〔栄養学科〕
【現状の説明】
栄養士資格を取得するために必要な「給食管理学外実習(2単位)」を、2年次の前学期に開講している。
【点検・評価】
栄養士法に則って適切に開講されている。実習受け入れ先とのトラブル防止のため、学外実習前に学生に対して学外実習における諸注意と指導を行っている。教員にとっては受け入れ先との調整に手間がかかっているが、実習に対する学生の満足度もは高くなる。
【将来の改善策】
学生が多様化する中、受け入れ先とのトラブルを防止するため、学生への事前指導とともに、受け入れ先との打ち合わせも密に行っていく。

|
|
|
|
|