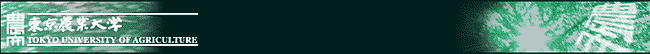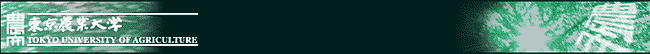| ※ |
注意 |
| ○ |
低学年(再履修)の必修科目はすべて自動登録をする。自分の学年の必修科目と重複するなど、受講が不可能な場合は必ず自分で削除すること。削除しない場合、再履修料が発生するので注意すること。 |
| ○ |
卒業論文は、6月30日(月)まで「卒業論文題目届」の提出により、自動登録します。いずれかの手続きに不備があった場合には単位を修得できない。「卒業論文題目届」は、5月中旬に担当教員へ配付するので担当教員より受け取ること。
|
| 【再履修科目について】 |
| (1) 再履修について |
| ・ |
再履修とは一度履修した授業科目のうち、不可(D)または未評価(F)になった授業科目を再度履修することをいいます(他学科・他学部聴講科目、教職課程の科目を再度履修する場合も同様)。 |
| (2) 再履修の登録について |
| ・ |
履修登録する科目が再履修科目であるかどうかは各自学生ポータルサイトの成績台帳で確認すること。 |
| ・ |
再履修の必修科目はすべて自動登録されます。自分の学年の必修科目と重複するなど、受講が不可能な場合は必ず自分で削除すること。削除しない場合、再履修料が発生します。 |
| ・ |
履修が確定した時点で再履修料の支払い義務が発生するので注意して登録すること。 |
| (3) 再履修料の納入について |
| ・ |
再履修登録料は1科目2,000円です。 |
| 再履修有料例外科目(無料) |
●特別講義(一)~(四) ●卒業論文 ●教育実習ⅠⅡ |
|
| ・ |
再履修有料例外科目を除く全授業科目について再履修料がかかります。
|
| 〔納入方法について〕 |
| ① |
履修確定後〔5月23日(金)〕、該当学生は「再履修料証紙貼付用紙」を学生ポータルサイトでダウンロードしてください。 |
| ② |
納付金額を確認した後、学生サービス課カウンター前「証紙券売機」で「再履修料2,000円」の証紙を納付金額分購入して「再履修料証紙貼付用紙」に貼付し、5月30日(金)午後5時までに学生サービス課カウンター下に設置されたレポート提出BOXに提出してください。 |
|
※ |
証紙は「再履修料2,000円」を購入してください。「再試験料」、「各種証明手数料」などとは間違えないよう注意してください。 |
|
※ |
在学中に納付金額の不足が発覚した場合には、その時点で納金することを義務づけます。 |
|
※ |
既に納金した後学期の有料科目を削除しても返金しません。
|
【履修登録上の注意事項】 |
| ◆ |
次のとおり1年間に履修できる単位数を制限する。 |
|
◎正規履修科目(他学科聴講を含む当該学年配当科目)は年間50単位までとし、
学期ごと30単位までが最大履修できる範囲である。
(例 前学期科目を30単位履修する場合、後学期科目は50-30で20単位まで履修で
きる)
●通年科目(実験、実習、演習など)は単位数を2分し、各学期の登録単位数としてカウ
ントし、年間の単位数としてもカウントする。
●単位数を超えて登録すると、システムが無作為に科目を選んで削除するので注意する
こと。
制限を超えて登録した場合はエラーとして表示されるので超過した単位数に応じて科
目を削除すること。
●登録した科目については履修確認・履修修正期間に必ず確認すること。 |
|
| 但し、下記の科目については年間の50単位の単位数制限から対象外とする |
|
●低学年次配当科目 ●教職・学術情報課程科目 ●レポート作成演習●基礎数学
●特別講義(一)~(四)(平成17年度入学生より適用)
●特別活動プログラム(詳細は6ページ参照のこと) |
|
| ◆ |
開講番号の登録を間違えるとエラーとなるか、またはまったく別の科目が登録されてしまうため、履修確認・履修修正期間に必ず確認すること(履修確定後の変更は認められません)。 |
| ◆ |
教職課程の履修については、ガイダンス・オリエンテーション等の中でアナウンスされる指導教員の指示に従うこと。 |
| ◆ |
時間割の区分に『教職』と表示のある科目はそれぞれ『教職課程』の科目のため、受講申込者(有料)以外は履修できない。 |
| ◆ |
同時限に開講している科目は、いずれかひとつを選んで開講番号を登録すること。 |
| ◆ |
同一時限に隔週で開講する科目を履修する場合は、同一時限に登録すること。 |
| ◆ |
2時限以上続けて開講する科目は授業開始時限にのみ開講番号を登録すること。 |
| ◆ |
集中授業科目は開講学期にあわせて、時間割外科目登録欄に開講番号を登録すること。
(別途掲示または学生ポータルサイトの「平成20年度集中授業スケジュール」を参照してください。) |
| ◆ |
通年科目は前学期授業開始時限にのみ開講番号を登録すること。 |
| ◆ |
高学年次配当科目は履修できない。(他学科・他学部聴講の場合も同様。) |
| ◆ |
他学科聴講履修登録単位は、在学中30単位を上限とする。
(合否にかかわらず、履修登録した時点〈同一科目を再履修した場合も含む〉で単位数をカウントする。) |
| ◆ |
他学部聴講履修登録単位は、在学中30単位を上限とする。
(合否にかかわらず、履修登録した時点〈同一科目を再履修した場合も含む〉で単位数をカウントする。) |
| ◆ |
前学期に履修登録した科目について単位を修得できなかった場合、後学期に同名科目を再度履修することはできない。 |
| ◆ |
生物産業学部共通授業科目「中国語(一)・(二)、ロシア語(一)・(二)」を履修する場合は、いずれかひとつの語学を選択すること。(履修が確定した時点で単位修得の有無にかかわらず、もう一方の語学科目は履修できなくなります。)
※中国語(三)・(四)は中国語(一)・(二)の単位を修得した者のみ履修できます。
※ロシア語(三)・(四)はロシア語(一)・(二)の単位を修得した者のみ履修できます。 |
| ◆ |
他学科・他学部聴講を希望する場合は、各学科の時間割を参照し、希望科目の開講番号を登録すること。 |
| ◆ |
必修科目でクラス分けのある科目は自動登録する。
(4ページ表1〔クラスが指定されている科目〕を参照。)なお、原則としてクラス変更は認めない。 |
| ◆ |
選択科目でクラス分けのある科目は、クラスを選んで開講番号を登録すること。クラスが指定されている科目は、指定されているクラスの開講番号を登録すること。
(4ページ表1〔クラスが指定されている科目〕を参照。)なお、クラス分けがある他学科・他学部の科目を履修する場合も同様とする。 |
| ◆ |
学部共通科目は他学科聴講を認めない。
(4ページ表2〔学部共通科目一覧表〕参照。) |
| ◆ |
実験・実習・演習科目は他学科・他学部聴講を認めない。
(5ページ表3〔各学科配当 実験・実習・演習科目一覧表〕参照。) |
| ◆ |
所属学科(配当学年を問わず)にある科目と同名の科目は他学科・他学部聴講を認めない。
(5ページ表4〔他学科配当の同名科目一覧表〕参照。) |
| ◆ |
表5に記載している授業科目は、短縮して表示することがあるので注意のこと。
(6ページ表5〔授業科目名の短縮表示について〕参照。) |
| ◆ |
本学では学科等の名称を短縮して表示することがあるので注意のこと。
(6ページ表6〔学科等の名称の短縮表示・表示順番について〕参照。) |
| ◆ |
産業経営学科4年のコース別授業科目について(平成14~17年度の入学生対象) |
|
① |
「産業経営学科共通基礎の科目」「総合化の科目(すべて必修)」は配属されたコースに関係なく全員が履修できる。産業経営学科の科目のコースによっては開講番号が違うので注意のこと。 |
|
② |
配属されたコース以外のコースの科目は配属された「コース指導選択科目」のみ選択履修できる(「コース指導選択科目」以外の他コースの科目は履修できません)。 |