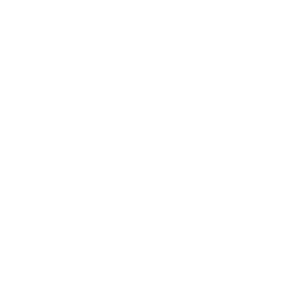果実を食べる哺乳類はどこにタネを運んでいる?
国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科の栃木香帆子大学院生(博士課程3年)、同大学院グローバルイノベーション研究院の小池伸介教授、長沼知子特任助教(当時、現 農研機構)、ノルウェーのノード大学のSam Steyaert准教授、東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科の山﨑晃司教授らの国際共同研究チームは、日本に生息し果実を食べることで被食型種子散布(注1;図1)を行う哺乳類5種の間で、その種子散布者としての役割がどのように異なるのかを検証しました。
その結果、種子が発芽や成長に適した環境に散布されるか否かは、運び手となる哺乳類の種や季節によって異なることがわかりました。また、一度に散布される種子の数は哺乳類の種によって異なるものの、共通して秋に多くなる傾向が見られました。さらに、種子が散布される場所の特徴も、哺乳類の種によって異なる傾向がありました。たとえば、夏にはツキノワグマは高木が多い環境に、ニホンザルは明るく開けた環境に、多く種子を散布する傾向がありました。これらのことから、哺乳類5種は同じ樹種の果実を食べたとしても、それぞれが異なる環境の場所に種子を散布するので、種子散布者として異なる役割を果たしていることが分かりました。また、果実の種子の運び手として異なる役割をもつ複数の哺乳類種が同じ場所に生息することは、植物にとっては様々な環境条件の場所に種子を散布される機会が確保されることにもつながります。
詳細は添付資料をご参照下さい。