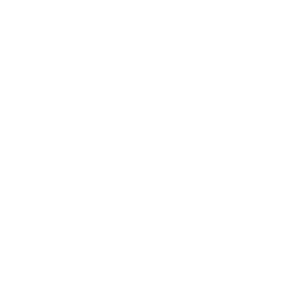理事長メッセージ
2023年7月16日に開催された理事会において,理事長職を拝命することとなりました。学校法人東京農業大学理事長と東京農業大学長を併任する重責となります。微力ではありますが,学校法人東京農業大学のさらなる発展のため,全力を尽くす所存でございます。皆様方のご支援・ご協力を賜りますよう,心よりお願い申し上げます。
2021年4月1日に学長に就任して以来,新型コロナウイルス感染症に対する最大限の感染対策を講じながら,東京農業大学の教育研究・課外活動,ガバナンスの推進,学校法人東京農業大学傘下にある大学部門としての中期計画の策定,大澤貫寿前理事長と髙野克己前学長が計画されたキャンパス整備の推進はもとより,新たな考えを取り入れたキャンパスとフィールド整備の実行やさらなる計画,入試・キャリア戦略および広報戦略の実施などに取り組んで参りました。 また,本法人の歴史を重んじつつも,新たな取り組みとしては,学校法人東京農業大学傘下の2大学,3つの高等学校と中学校,1つの小学校の機能を最大限発揮し,社会のニーズに合致した東京農業大学の運営を意識して参ります。
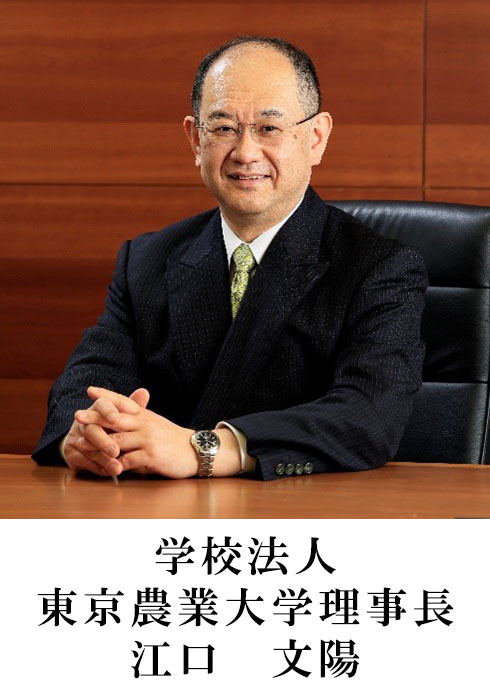
学校法人東京農業大学の歴史のはじまりは,明治24年(1891年)に箱館五稜郭で明治新政府軍に敗北はしたものの,幕末から明治への激動の中で活躍したその実績が高く評価され,駐ロシア全権公使,文部大臣,農商務大臣,外務大臣,逓信大臣などを歴任した榎本武揚公によって開設された私立育英黌農業科です。開設から2年を経て私立東京農学校と改称し,日本の博物館の父と称された田中芳男が東京高等農学校初代校長として,その後大日本農会の経営のもと私立東京農業大学となり,初代学長に横井時敬が着任しました。
東京農業大学の教育の理念は,実学主義を重んじて人物を育成し,農林水産業及びその関連産業界に有能な人材を輩出する精神,すなわち建学の精神である「人物を畑に還す」のもと,明治期以降の国内外の農学領域の研究や産業分野に多くの人財を輩出し,近代農業の発展と人々の生活に豊かさをもたらすことに大きく貢献してきました。
しかしながら,国内外の社会環境の変化はもとより,殊に教育研究機関を取り巻く環境の変化は厳しく,特に少子化による就学人口の減少は,学校法人経営に大きな影響を及ぼしています。このような時節において最も重要なことは,法人傘下の教職員が教職協働のもと一丸となり,学校法人東京農業大学を選んでくださった就学者が輝く人材となって広く社会で活躍できるよう取り組むことと考えます。
変化が激しくその予測が困難な現代社会であるからこそ,活躍できる知識と人間力を兼ね備えた人材とともに,デジタル情報化社会において求められる人材を育成することなど,社会の変化と要請に貢献できる質の高い教育・研究を推進しなくてはなりません。
そのために法人理事長としての責務は,多くの教職員,関係者との対話のもと意見を聞き,あらゆる情報をキャッチしてそれらを解析した後,冷静でありながら即時対応する決断力を持つことと確信しています。そうした行動力が安定した財政基盤を確立し,盤石な学校法人へとさらに発展させると考えます。
大澤前理事長は,「学生・生徒・児童の思いを実現する学校法人」をこれまで 3期(12 年間)に亘り,全力で推進されてきました。大澤前理事長のお考えや経営方針は,東京農業大学長として2年4か月しっかりと学ばせていただきました。
大澤前理事長が取り組まれた明確な中期計画と財務基盤強化を深く理解し,これからの時代に即した対応も取り入れつつ,理事・監事・評議員と教職員および社会の理解を得ながら,各部門における就学者の気持ちになって学校法人東京農業大学の運営に努めます。
特に学園化構想における東京農業大学,東京情報大学と東京農業大学併設校の教育力やブランド力の向上,それぞれの部門や地域における特色は活かしつつ,部門間交流と連携の強化を図り,「学生・生徒・児童が輝く」教育(研究)環境の整備を推進します。
理事長として「学校法人東京農業大学らしさ」を広めたいと考えています。それは,「みんなで元気に挨拶をしよう!」ということです。簡単なことのようですが,現代社会において如何に広まっているでしょう。“挨拶は何かが始まる魔法の言葉”なのです。すなわちコミュニケーションを大切にして明るい職場環境,教育・研究環境の整備をさらに推進します。
創立132年を迎えた学校法人東京農業大学が社会から信頼され,それぞれの部門の就学者から選ばれ続ける組織であるため,実学主義のもと有能な人材育成を目指して取り組んで参りたいと考えます。皆様には,重ねてご支援とご協力をお願い申し上げ,学校法人東京農業大学理事長就任のご挨拶とさせていただきます。