北海道と虫屋バイアス
博士前期課程2年 相馬 純
サンプル回収の関係で北海道に行く必要が出てきた。
とりあえず文献を読み、研究室の標本のラベルを見る。
ここであることに気付く。
南西諸島で採集した時と同じ感覚だ。
「この人達いつも同じ場所で採集しているな。」
例を挙げると、トム○ウシや釧○湿原である。
遠征へ行くと(行かなくても)見た目の環境が良い場所で採集したくなるのは虫屋の性か。
地図を広げると、広大な未調査地が姿を現した。
調査する環境は決まった。
ひたすら歩いて道路沿いの植物を片端から調べよう。
公園に植栽される植物は地域ごとに種構成が異なるので、それも面白そうだ。
そんなこんなで蝦夷地で1人旅をした。
結果から言うと、新知見の嵐だった。
以下、情報を隠匿しなくて良さそうな種を挙げながら振り返っていく。

飛行機で帯広に降り立ち、バスで駅に行く。
久し振りに北海道の空気を感じ気分が高まる。

遠くで電車に乗る時は駅の看板をつい撮ってしまう。

4年前に鈍行列車を乗り継いで北海道を1人旅したことを思い出す。
あの頃はまだマトモに虫を採ったことがなかった。
目的地の駅で降り、宿に荷物を置き、近場の山へ。
ここで茂みの向こうに動くヒグマから全力で逃亡する。
買った熊鈴が役に立たないことが1日も経たずに証明された。

それはさておき、足元を見ると良い感じにスゲが生えている。
葉をビーティングネットに打ち込む。
1.jpg)
ズグロナガグンバイが落ちてきた。
分かりにくいが、この個体は長翅型。
3.jpg)
ちなみにこちらが短翅型である。
長翅型よりも短翅型が圧倒的に個体数が多い。

さらにまた歩く。
上から眺める線路はいつでも良い。

ナナカマドを発見したのでビーティング。
1.jpg)
チャイログンバイが採れた。
ロシアで同属の植物から得られているので、得られた状況に疑問はない。
それはそうと、南関東ではなかなか出会えないカメムシだ。
たまに採れるけど。

歩く道はいつも真っ直ぐだ。
脇道に逸れると良いことがある。

ある場所で無尽蔵に湧いていたカバヒラタカメムシ。
この個体はオスである。

メスは腹端が尖って厳つい。
諸事情により、生息環境については触れないでおく。
ただ1つだけ言うならば、もはや普通種であるということだ。

ハイマツ群落を見に行くなど。
そこからまた登って下りて。
少しだけコケをお触りした。
1.jpg)
知る人ぞ知る、ヒラシママルグンバイ。
この個体はオス。
1.jpg)
メスはより丸みを帯びた体型となる。
今回の遠征の目的からすると「外れ」のグンバイムシである。
普通に採れて嬉しいのは変わらないが。

道路沿いのシロザを見る。

そして近づく。
1.jpg)
チビカメムシが得られた。
こちらの個体は長翅型である。
1.jpg)
短翅型の前翅はかなりグンバイムシっぽい。
やはり短翅型が長翅型よりも圧倒的に個体数が多い。
採集して気付いたが、明らかに普通種である。
記録が少ないのは誰も探していなかっただけの可能性が高い。

ツツジに怪しげな雰囲気を感じ取る。
1.jpg)
アザレアグンバイとの邂逅。
1.jpg)
終齢幼虫はこちらになる。
成虫と幼虫ともにかなりの個体数が見られた。
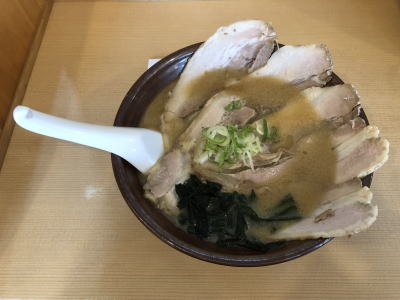
遠征前半は基本的に飯をあまり食わないが、後半になると食事量を増やす。
やはりラーメンは良い。

駅弁とかいうの、実は結構好きだ。

ゆり根のかき揚げが身に沁みる。

お約束のソフトクリーム。

3日半しか動けなかったが、収穫は大きかった。
蝦夷地には来年もまた行きたい。
一度で調査を完遂するにはあまりにも広すぎる。