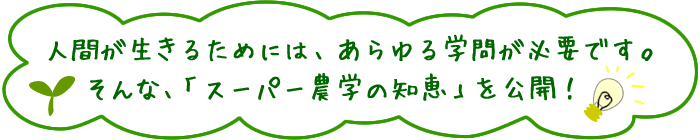
食べ物の機能性成分の変動を制御する
応用生物科学部食品安全健康学科 准教授 田村 倫子
食べることは受け入れること
温度、湿度、明るさ、匂い、酸素の濃度、ウイルスなど私たちが生活する上で対応しなければならない外的因子は多数存在する。「食べること」も体外から成分を取り入れるということであれば、対応しなければならない外的因子の一つといえる。思い起こせば、子どものころに読んだ「不思議の国のアリス」も、ボトルの液体を飲むことで穴の向こうの世界の環境に体を適応させていたのかもしれないし、アニメに出てくるヒーローが変身したときも、飴玉を口にしてパワー100倍になっていたように思う。
ところで外的因子のうち、温度や明暗、空気中の成分は地球の回転や地域に強く依存するため拒否するのが難しい一方で、「食べる」ことは、人それぞれの判断で取捨選択が可能な因子である。と同時に、その食品に含まれているすべての化合物の構造・機能・安全性を承知できなくても、摂取しなければならないともいえる。よって「食べる」ことは、生命活動のエネルギーを得る一方で、飲み込んだ食品中の成分に応答することなのかもしれない。
食べ物に求めるものは時代とともに変化
現代の日本において白米を摂取することは当たり前のようになっているが、玄米を精米して糠を除き、白米にする技術は明治時代に飛躍的に広まった。当時は少量の副食でたくさんの白米を摂取するのが普通であったため、栄養が偏り、脚気と呼ばれる病気が蔓延した。脚気の原因は米ぬかに含まれる成分が体内で不足したためであるが、後にこの成分は生命の維持に不可欠な栄養素であるビタミンB1と判明した。当時は食品を正しく摂取し、栄養失調を防ぐことが「食べる」行為に求められた。
しかしこれが満たされ、豊かな時代が到来すると、食べることに楽しみを求めるとともに、食感や嚥下しやすさはどうか、色や香りは適正か──といった“栄養素の充足”を越えた要因が求められるようになった。優れた保蔵技術や加工方法は新鮮で安全な食品を長期にそして遠くまで届けることを可能にした。グルメな食事が我々の生活に変化を与え、飢餓や栄養失調の代わりに、偏った食事や乱れた食事などに起因するメタボリックシンドロームといった病状を深刻化させた。
1990年代ごろ、生活習慣病が顕著になると、これを未然に防ぐための「成分」と、そのからだに対する「働き(機能)」が食品に求められた。食品は口から取り込まれたあと消化管に移行し、あるものは吸収されて各器官で機能し、あるものは消化管にとどまり機能する。今なお、食品中の機能性成分と、それが体内のどこでいつどのように機能するかのメカニズムの研究が盛んに行われている。この一方で、作物の有する機能性をどうすれば引き出すことができ、どうすれば高められるかの研究も、注目を集めている。
作物の機能性を高める方法
収穫前の育種時に機能性を高める方法として植物工場を利用した育種法が挙げられる。2月17日の植物工場研究部会の発足記念講演において、大成建設から、そのいくつかが紹介された。酸素濃度・寒冷暴露・水耕栽培・LEDを用いた光波長の変化により野菜の代謝すなわち機能性成分を変動させることができる。
この一方で、収穫後の作物においても、機能性成分を変動させることは可能である。例えば温度や湿度の管理、酸素濃度の制御などである。我々の研究室では、どの家庭にもある水に、大豆や小麦を一定時間浸すだけで種実内の代謝がドラスチックに変化し、機能性成分が高まった種実を得る研究をしてきた。発芽スプラウトではなく、発芽前の短時間吸水で機能性成分の変動が予測された。このことは食品加工をするうえで加工特性を失わず機能性は高まった製品を開発する基盤になると考えられる。
吸水による遺伝子群の発現変動
大豆を加工する際、伝統的に数時間の浸漬がほどこされている。吸水における栄養素の量的変動に関する研究はよくみられるが、食品の機能性に着目したオミクス解析は少なく、さらに短時間吸水における網羅的な遺伝子発現変動については報告例がない。しかし、生体に有益な成分に関わる遺伝子の発現変動と、その周辺の代謝変動を網羅的に解析することは、食品の二次・三次機能に関わる物質が増減するしくみを理解し、より機能性の高い食品を効率的に得るために重要である。
大豆に含まれるビタミンCは、吸水前は1.6mg/100g種子であり、吸水8時間後に2倍に増加しその後も増加し続けた。γ─アミノ酪酸(GABA)は乾燥種実に23.6mg/100g種子であり、吸水後32─40時間で35.8から98.3mg/100g種子に増加した。そこで、吸水0、8、16時間における大豆のDNAマイクロアレイ解析を行うと(図1)、炭水化物の代謝に関わる遺伝子群は吸水8─16時間に発現増加するクラスターに配属された一方、いずれの時間も発現増加した遺伝子は炭素固定や鉄代謝に関わる酵素をコードする遺伝子群であった。吸水8─16時間に発現が低下した遺伝子の多くは、水・温度・光・障害に応答するタンパク質をコードする遺伝子群であった。次に、タンパク質、脂質代謝に関わる酵素をコードする遺伝子や、二次代謝産物に関わる酵素の遺伝子に着目すると、プロテアーゼ、プロテアーゼインヒビターにおいては各種類によって異なる発現パターンを示した。
機能性成分の存在組織を知る
吸水によりどのような成分が変動するか予測することで、ある成分に着目し、その動態を明らかにすることに発展させることができる。今回は大豆が主要な植物性タンパク質源であることに注目し、タンパク質分解に関わるプロテアーゼやインヒビターに着目した。大豆には、Kunitz trypsin inhibitor (KTI)並びにBowman─Birk inhibitor (BBI)という、膵液に含まれるタンパク質分解酵素を阻害するプロテアーゼインヒビターが含まれている。この理由は、プロテアーゼインヒビターが病原菌や害虫の持つプロテアーゼを阻害して自らを防御するためである。この防御システムは人間に対しても有効である。BBIは抗がん作用遺伝子を刺激することで抗がん作用を、KTIはがん転移を促す遺伝子を抑制することでがん転移抑制作用を持つことが明らかになっている。
そこで、KTIとBBIがそれぞれ大豆中のどの組織に局在し機能するか調べた。BBIは病原菌や害虫からの攻撃に対する防御の役割を持つことが知られているためダイズの外側に存在すると予想した。結果は図2のように、BBIは表皮および外側から二層には存在せず、子葉細胞に局在し、KTIはいずれの組織にも存在することがわかった。BBIが今回染色された層に存在する理由は、BBIはシステインという含硫アミノ酸を多く有するタンパク質であるため、システインの貯蔵と供給のために吸水時は機能していると示唆した。一方、KTIはBBIが存在していない外側の層にも存在していたため、吸水時には外敵からの防御として機能しているのかもしれない。このように場所を特定することで、機能性成分を特定の組織から効率よく抽出できることはもちろん、植物体内における働きを予測でき、「どのような処理により目的成分を増加させることができるか」に、近道で迫ることができる。
植物工場は機能性強化作物の作出に最も適した施設と考えられる。現象をとらえ、網羅的手法でスクリーニングし、現象の原因となる因子をいくつか選出し、その実態をしらべ、目的の作物を作出するための条件を明らかにできる。さらにその条件で育種した作物を生産することができる。
また、機能性成分の増加に誘引される形で他のどのような成分が増減しているかに着目すれば、これからの食に求められる「安全」と「健康」に応える一助となるのではないかと考えている。
