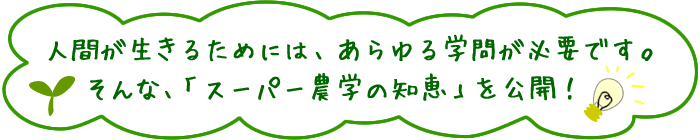
東京農大「先端研究プロジェクト」報告(下)
アジアに生きるヤギの遺伝子を追う
農学部畜産学科 准教授 野村 こう
ヤギはイヌに次いで古くに家畜化され、ヒトとの暮らしは1万年余に及ぶ。世界に最も広く分布する家畜で、特に住環境の厳しい辺境地には欠かせない家畜としてその過半数がアジアの発展途上国で飼養され、現在なお頭数を伸ばしている。平成18年度から3年間にわたった東京農業大学先端研究プロジェクト「遺伝子発現機構に基づく新たな家畜改良に関する研究」において、私たちの研究グループは、アジア在来ヤギの基礎的遺伝情報を蓄積し、その遺伝資源としての評価を行なうことを目的とした。またアジア諸国の在来ヤギ改良の指針を示すと共に、繁殖周期などの経済形質と関連する遺伝子の絞り込みを行い、DNAマーカーによる品種改良に着手した。
アジアのヤギは3系統
日本を始めとするアジア8カ国20地域集団470頭について50種のマイクロサテライトDNAマーカーを用いて遺伝的構成を探索したところ、各集団の遺伝的多様性を示す平均アレリックリッチネスおよび平均へテロ接合体率は(シバヤギ)および0.363(シバヤギ)〜5.38(モンゴル在来ヤギゴビ地域集団)および0.742(モンゴル在来ヤギエルチムブラック集団)の範囲であった。
これらの結果からアジア在来ヤギの遺伝的多様性は大陸部集団で高く、大陸周辺部や島嶼部で低い傾向が認められた。すなわちモンゴル在来ヤギ集団は遺伝的多様性が高く、日本のシバヤギ、韓国在来ヤギ、インドネシアのカンビンカチャンは多様性の低い集団であることが明らかになった。同一国内における集団間の分化程度を示すFST値はモンゴルが他国よりも低い値を示し、同国は呼称の異なるいくつもの地域集団を持つが、その遺伝的分化程度は低く、品種や系統としての確立には至っていないことを示した。
DA遺伝距離によるクラスタリングの結果、アジアの家畜ヤギはモンゴルのグループ、その他の東アジアのグループ、南・東南アジアのグループの3つに分けられた。(図)ヤギの家畜化はチグリス・ユーフラテスのいわゆる肥沃な三日月地帯で起きたとされ、その東方に広がるアジア地域への拡散は主に2つのルートが考えられている。すなわちイラン、アフガニスタンからトルキスタンを経て中国北部からモンゴルへ至る、後にシルクロードと呼ばれるルートと、カイバル峠を越えてインド亜大陸へ至るルートである。
今回の遺伝子解析結果によれば、現在のアジア在来ヤギの遺伝子構成はこの歴史的背景をよく残している。すなわち中東で家畜化されたヤギはシルクロードを通って北アジアへ入ったグループ、そこから中国を経て東方へ至ったグループ、そしてインド亜大陸へ広がったグループへと、家畜化の場所から遠ざかるに従い、その遺伝的多様性を失いながら分化したことが推察される。
母系系統と環境適応能力
細胞質にあるミトコンドリアDNAは母方からのみ遺伝し、塩基置換速度が速く、かつ解析が容易なことから系統分類の仕事によく利用される一方、その多型は運動能力や疾病、地域環境への適応とかかわりがあるとされている。
ミトコンドリアDNAの塩基配列情報によればアジアの家畜ヤギにはA〜Dの4グループの母系祖先が存在する。グループAは多くの集団に優占的に存在した。一方グループBはインドネシア、フィリピンおよびバングラデシュに見られたが、その比率は南下するに従い上昇し、インドネシアでは100パーセントを占めた。グループCおよびDはモンゴルに極少数存在した。A、C、Dの◯グループ間のアミノ酸配列の進化速度や置換のパターンに明確な違いは確認されず、頻度の違いは機会的遺伝浮動が主な要因となって生じた可能性が高いと考えられた。
一方、グループBは興味深いことに分子構造の大きく異なるアミノ酸への置換や、哺乳類間で保存性が高いCO2領域内のアミノ酸置換などの多くのアミノ酸置換を固定していた。すなわち、これらの置換は機能に影響しており、かつ東南アジアという環境に適応した結果である可能性が示唆された。
モンゴル在来ヤギの育種戦略
モンゴルにおいて調査した8集団はごく最近、集団ごとに毛色を単一にしてカシミヤ産業に利用され、モンゴルの輸出による収入の11%を占めるに至っている。そこで実際に各集団のカシミヤを比較したところ、集団間でカシミヤ繊維の太さと長さに有意差が生まれているという結果を得た。
同時に例えばザラージンストホワイト集団では太さが15〜25マイクロメートル、長さが50〜100ミリメートルと最小のものと最大のものの間に倍ほどの違いがあるなど、集団内のばらつきも大きいことが判明した。前述したモンゴル在来ヤギ集団の、遺伝的多様性は高いが集団間の分化が低いという遺伝的構造は、古くから行われている遊牧という飼養形態により絶えず集団間の遺伝子流動が起こったこと、さらに近代的育種を実施していないというモンゴルの歴史を反映した結果であると考えられた。これらのことからモンゴル在来ヤギのカシミヤは選抜を行なうことでさらに改良の余地があることが強く示唆された。
日本における乳用ヤギの育種改良
ヤギは牛に比較し小型で扱いやすく、今後は女性や高齢者による管理が容易な家畜として特に山間部農村で有力であると期待される。その乳は畜産先進国であるヨーロッパでは嗜好性の高いチーズなどの加工品の原材料としても珍重され、需要が高い。また最近では食物アレルギーが問題となっており、牛乳に対してアレルギーを持つ人も多いが、ヤギ乳にはそのような抗原性は無いとされ、注目されている。
日本におけるヤギ乳普及の第一のネックは、年間を通じた生産ができないという欠点である。すなわち乳用ヤギザーネン種は春季にしか仔を生まず(季節繁殖性)、泌乳期間は出産後10ヶ月であるので、冬季には乳の生産が無い。本グループではヤギ乳の安定生産を阻む乳用ヤギの季節繁殖性に着目し、日本におけるヤギ種畜生産の中枢である(独)家畜改良センター長野牧場との共同研究で乳用ヤギの育種改良に着手した。
乳用ヤギに年間を通じて出産できる特質(周年繁殖性)を付与するため、この形質をもつ日本の在来種シバヤギと乳用ヤギザーネン種を交配する実験家系を作出した。雄シバヤギ1頭、雌ザーネン6頭を用いてF1世代36頭を作出したところ、全ての雌個体が周年繁殖性を示し、この形質の乳用種への導入に成功した。ザーネン種に戻し交配した第2世代58頭のうち、現在までのところ雌の約80%が周年繁殖性を示している。以上のことからシバヤギの持つ周年繁殖性はザーネン種に対して優性であり、その発現には複数の遺伝子が関与している可能性が示された。
日本の遺伝子資源の世界的活用を
ザーネン種はヨーロッパで育種改良され、世界中で飼養される有名な乳用種である。このヤギの大きな欠点に日本の在来ヤギの周年繁殖性を導入できたことは、在来家畜遺伝子資源の活用の面からも大きな成果と考える。この技術を世界で活用させるためにも、周年繁殖性の分子遺伝学的解明を急ぎたい。
