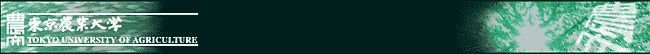 |
| �S���ƉȖڈꗗ |
| �w�@�N |
�w�@�� |
�K�@�C |
���@�@�@�Ɓ@�@�@�ȁ@�@�@�� |
�P�� |
�� |
���@�l |
| �������Y�w�Ȏ��ƉȖ� |
||||||
| �S |
�� |
�K�C |
�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�` |
�Q |
5 |
|
| �S |
�� |
�K�C |
�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�a |
�Q |
6 |
|
| �S |
�� |
�K�C |
�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�b |
�Q |
7 |
|
| �S |
�� |
�K�C |
�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�c�P |
�Q |
8 |
|
| �S |
�� |
�K�C |
�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�c�Q |
�Q |
9 |
|
| �H�i�Ȋw�Ȏ��ƉȖ� |
||||||
| �S |
�� |
�Ȋw�p��i��j |
�Q |
13 |
||
| �Y�ƌo�c�w�Ȏ��ƉȖځF���_�w���[�~ |
||||||
| �R�E�S |
�� |
�c���[�~ |
17 |
|||
| �R�E�S |
�� |
�i��[�~ |
17 |
|||
| �R�E�S |
�� |
��c�[�~ |
17 |
|||
| �R�E�S |
�� |
���ԃ[�~ |
18 |
|||
| �R�E�S |
�� |
�F�V�[�~ |
18 |
|||
| �R�E�S |
�� |
�|���[�~ |
18 |
|||
| �R�E�S |
�� |
���[�~ |
19 |
|||
| �R�E�S |
�� |
���G�[�~ |
19 |
|||
| �R�E�S |
�� |
���V�[�~ |
19 |
|||
| �R�E�S |
�� |
����[�~ |
20 |
|||
| �R�E�S |
�� |
���y�H�[�~ |
20 |
|||
| �R�E�S |
�� |
�e�n�[�~ |
20 |
|||
| �R�E�S |
�� |
�吼�[�~ |
21 |
|||
| �R�E�S |
�� |
����[�~ |
21 |
|||
| �R�E�S |
�� |
���[�~ |
21 |
|||
| �R�E�S |
�� |
���[�~ |
22 |
|||
| ���E�ے����ƉȖځF���E�Ɋւ���Ȗ� |
||||||
| �S |
�O |
���瑊�k�_ |
�Q |
25 |
||
| �R�E�S |
�ʔN |
������K�T |
�R |
26 |
||
| �R�E�S |
�ʔN |
������K�U |
�Q |
27 |
||
| �������Y�w�Ȏ��ƉȖ� |
| �i�K�j�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�k�A�������w�������l �S�N���@�ʔN�@�Q�P�ʁ@�S�������F�����P�s�E��ؒ�i�E��W�씪�E�g�c��ρE�ɓ����� |
| ����ړI �S�N���͑��_���������S�ƂȂ�̂ŁA�Ƃ�܂Ƃ߁E���\�܂łɕK�v�Ȏ����E���K�Ɏ��������i�앨���Y�w�`����j |
| �� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
�� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
| �P |
�K�C�_���X |
���_�쐬�܂ł̃X�P�W���[�� |
16 |
���@��@�@ |
�X�ё��� |
| �Q |
�����v��@ |
�v |
17 |
�V |
�іؕ��z�}�쐬 |
| �R |
�V |
�����@ |
18 |
�y���� |
pH �EC,CEC |
| �S |
�V |
�f�[�^���� |
19 |
�u���_�xy1 |
|
| �T |
�R���s���[�^���K |
���� |
20 |
�V |
���������� |
| �U |
�V |
���K |
21 |
�V |
�����_�z���W�� |
| �V |
�앨�͔|�@ |
�������K |
22 |
�V |
���A�|�b�E�m |
| �W |
�V |
���K |
23 |
�V |
���������� |
| �X |
���@��@�@ |
�������ƋC�E�J�x |
24 |
���@��@�@ |
�n�����ʌv�ƃe���V�I���[�^ |
| 10 |
�V |
�t�ʐ� |
25 |
�ʁ@�@�@�^ |
���\�p�X���C�h�̂���� |
| 11 |
�V |
������� |
26 |
���@�@�@�_ |
�_���쐬�w�� |
| 12 |
�V |
���莎�� |
27 |
�V |
���@�@�@�\ |
| 13 |
�V |
���n���� |
28 |
�V |
�V |
| 14 |
�\�@���@�� |
29 |
�\�@���@�� |
||
| 15 |
�V |
30 |
�V |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�i���s���j |
|
| ���@�ȁ@�� |
|
| �Q�@�l�@�� |
|
| �]���̕��@ |
�o�ȉɐϋɓI�Q���ԓx���������ĕ]������B |
| ��u��� ���ӓ_�� |
�����E���K�̓s�x�A�v�����g��z�z |
| �i�K�j�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�k���������w�������l �S�N���@�ʔN�@�Q�P�ʁ@�S�������F�Γ��F�Y�E���_�����E���q�F�`�E�T�R�S�� |
| ����ړI �{�����E���K�ł́A�a����i�������B�w�j���U�����S�N���w����ΏۂƂ��āA�L�p���������̊J���E���Y�ɌW�����Z�p���C��������ړI�ŁA�ƒ{�ɐB�w�A�����H�w�A�ƒ{���w�A������`�w�A�ƒ{�h�{�w����щƒ{�Ǘ��w����ՂƂ������p��������̂Ɏ��{����B�֘A�Ȗڂ͏�L�̉Ȗڂ��x�[�X�ɂȂ�A�w���ŊJ�u����Ă���Ȗڂł́i��j�Ŏ��������̂̑��A��`�q�H�w�A�����Ɖu�w�A�ƒ{�l�H�����_�A�ƒ{���ڐA�_�Ȃǂ��֘A����B |
| �� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
�� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
| �P |
�K�C�_���X |
�u�`���e�̐��� |
16 |
���������̎��� |
���ݓ��̏����̋@�� |
| �Q |
�����H�w |
�X���C�h���� |
17 |
���������̎��� |
���ݓ��e���̕��́ipH �A�u�e�` �j |
| �R |
�����H�w |
�E�V�̑̊O�i�r�f�I�j |
18 |
���������̎��� |
���ݓ��e���̕��́i�A�����j�A�|�m�j |
| �S |
�����H�w |
�������������̑̊O�̎��K |
19 |
�T�C���[�W�̔��y�i�� |
�T�C���[�W�̔��y���_ |
| �T |
�����H�w |
�E�V�̎��ڐA�i�r�f�I�j |
20 |
�T�C���[�W�̔��y�i�� |
�T�C���[�W�̗L�@�_���́i���_�j |
| �U |
�����H�w |
������̓����ۑ��̎��K |
21 |
�T�C���[�W�̔��y�i�� |
�T�C���[�W�̗L�@�_���́i�u�e�` �j |
| �V |
�d�C�j���@ |
�e����@�ɂ��ĉ�� |
22 |
�T�C���[�W�̔��y�i�� |
�T�C���[�W�̗L�@�_���́ipH �VBN �j |
| �W |
�j�_�̕��� |
�c�m�`�̕����@ |
23 |
�f�[�^�̂܂Ƃߕ� |
���Ƙ_���̏����� |
| �X |
�j�_�̕��� |
�c�m�`�^�̌��o�@ |
24 |
�f�[�^�̂܂Ƃߕ� |
���Ƙ_���̏����� |
| 10 |
�`�����̕��͖@ |
�`���������̕����i�����j |
25 |
���_�̒��ԕ� |
�����f�[�^�̂܂Ƃ߂̎��� |
| 11 |
�`�����̕��͖@ |
�`���������̕����i�������j |
26 |
���_�̒��ԕ� |
�i�e��U�������\�j |
| 12 |
�`�����̕��͖@ |
�`�����^�̉�͖@�ƕ��q�ʂ̐���@ |
27 |
���_�̒��ԕ� |
|
| 13 |
��`���� |
��`�q�p�x����ш�`�l������@ |
28 |
���_�̒��ԕ� |
|
| 14 |
29 |
||||
| 15 |
30 |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�i���s���j |
|
| ���@�ȁ@�� |
|
| �Q�@�l�@�� |
|
| �]���̕��@ |
�o�Ȑ�����ђ�o���|�[�g�̓��e�ɂ��]������B |
| ��u��� ���ӓ_�� |
�����͍u�`���ɔz�z�B |
| �i�K�j�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�k���������w�������l �S�N���@�ʔN�@�Q�P�ʁ@�S�������F�K���A�E������ |
| ����ړI |
| �� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
�� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
| �P |
�K�C�_���X |
�{�����E���K�̐��� |
16 |
�����u�� |
�C�m�w�p�����ȏ��u�� |
| �Q |
���Ƙ_���쐬�w�� |
�Ƙ_���̏������P |
17 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| �R |
�V |
�V�@�@�@�Q |
18 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| �S |
�V |
�����f�[�^�܂Ƃ߂̎��� |
19 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| �T |
�V |
�V�@�@�@ |
20 |
�@�@�V |
�Ώ��w�p�����ȏ��u�� |
| �U |
���Y��������E�Ǘ��̎��� |
���琅���̐����E�Ǘ� |
21 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| �V |
�V |
�V�@�@�@ |
22 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| �W |
�V |
���琅���̐����i������ ��j |
23 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| �X |
���������������@ |
�v�����N�g���A�ꐶ�����E���� |
24 |
���_���ԕ� |
�w�����\ |
| 10 |
�V |
�V�@�@�@ |
25 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| 11 |
�����i���������j��b�����@ |
���������̎戵���@�i�Œ�ۑ��j |
26 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| 12 |
�V |
�������ʐ^�B�e�Z�p |
27 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| 13 |
�V |
�V�@�@�@ |
28 |
�@�@�V |
�V�@�@�@ |
| 14 |
29 |
||||
| 15 |
30 |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�i���s���j |
|
| ���@�ȁ@�� |
|
| �Q�@�l�@�� |
|
| �]���̕��@ |
�o�ȁi50���j�ƃ��|�[�g�i50���j�ŕ]�������B |
| ��u��� ���ӓ_�� |
�����͍u�`���ɔz�z�B |
| �i�K�j�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�k�����o�C�I�e�N�m���W�[�������l �S�N���@�ʔN�@�Q�P�ʁ@�S�������F�ɓ���v�E���l�Lj�E��؏~�u |
| ����ړI |
| �� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
�� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
| �P |
�K�C�_���X |
�{�����E���K�i��j�̊T�v |
16 |
�c�m�`�̐ؒf |
�����y�f�ɂ��v���X�~�h�̐ؒf |
| �Q |
�����͈͂̐��� |
�����ݔ��A���ނ̑���@ |
17 |
�c�m�`�̐ؒf |
���K�[�[�ɂ��g�����c�m�`�̍�o |
| �R |
�g�����c�m�`���� |
�����菇�̐��� |
18 |
�`���]�� |
�g�������� |
| �S |
�V |
�|�n�̒��� |
19 |
�@�@�V |
�`���]���̊m�F�B�R���[�j�[���𐔂��� |
| �T |
�V |
����̒��� |
20 |
�����f�[�^�̂܂Ƃ� |
�����f�[�^�̂܂Ƃ߁B�e��������ڂ��� |
| �U |
�V |
�A�ۑ��� |
21 |
�@�@�V |
��`�q�n�}�̍쐬�� |
| �V |
�V |
�咰�ې���Ȑ��̍쐬 |
22 |
�g�����c�m�`�ɂ��Ă̕]�� |
�e�ǂ��Ƃ̃f�[�^���� |
| �W |
�V |
�v���X�~�h�̒��o�i�P�j |
23 |
�f�[�^�̂܂Ƃߕ� |
���_�̏������i�P�j |
| �X |
�V |
�v���X�~�h�̒��o�i�Q�j |
24 |
�f�[�^�̂܂Ƃߕ� |
�V�@�@�i�Q�j |
| 10 |
�V |
�c�m�`�̒��o |
25 |
�f�[�^�̂܂Ƃߕ� |
�����f�[�^�܂Ƃ߂̎��� |
| 11 |
�V �d�C�j���@ |
�A�K���[�X�d�C�j���@�ɂ�� |
26 |
���_���ԕ� |
�V�@�@�@ |
| 12 |
�V |
�c�m�`�̕]�� |
27 |
���_���ԕ� |
�V�@�@�@ |
| 13 |
�����y�f�̘A���y�f |
�����y�f�iH ind�V�DDra�P���j �A���y�f�i���K�[�[�j�̐��� |
28 |
���_���ԕ� |
�V�@�@�@ |
| 14 |
29 |
||||
| 15 |
30 |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�@�@�i���s���j |
|||
| ���@�ȁ@�� |
|||
| �o�C�e�N�u���E��`�q�H�w���� ��`�q�N���[�j���O���� ��`�q����̌��� |
�r�㐳�l�� T .A .Brown�����c�Ė� R.W .�I�[���h�CS.B�v�������[�Y���� |
���H�}�� �I�[���� �|���� |
|
| �Q�@�l�@�� |
|||
| �]���̕��@ |
�]���͏o�ȓ�������ю������Ƃ̃��|�[�g�ɂ��s���B �Q�^�R�ȏ�o�Ȃ̂Ȃ��҂͐��ѕ]���̑Ώۂɂ��Ȃ��B |
||
| ��u��� ���ӓ_�� |
�������@�A����̒������@���ɂ��Ă̓}�j���A���i�����j��z�z�B�e�������Ƃɂ��A�����̔z�z���s���B |
||
| �i�K�j�������Y�w���ʎ����E���K�i��j�k�A�����Y�H�w�������l �S�N���@�ʔN�@�Q�P�ʁ@�S�������F�㑺�p�Y�E���ؖF�}�E���I�G |
| ����ړI |
| �� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
�� |
���@�@�� |
�u�`���e�E��@ |
| �P |
�K�C�_���X |
�{�����E���K�i��j�̊T�v |
16 |
�y�f�w���� |
�A���y�f�̐��� |
| �Q |
�����ݔ��E�@�푀��@ |
17 |
�y�f�̉��w���� |
||
| �R |
�g�D�������w |
�זE�������̌��o |
18 |
�y�f�̊���ِ� |
|
| �S |
�y�f�זE���w |
19 |
�������x��� |
||
| �T |
�Ɖu�זE���w |
20 |
���q�����w���� |
�A���Q�m���̒P�� |
|
| �U |
�t�H���Q�����F�@�E�v���[�u�@ |
21 |
�ړI��`�q�̃N���[�j���O |
||
| �V |
in situ���G��`�� |
22 |
�T�U������ |
||
| �W |
�זE����T |
�~�g�R���h���A |
23 |
��`�q�̔z���� |
|
| �X |
�g�D�|�{����̒P���E���� |
24 |
��`�q�̔��� |
||
| 10 |
�זE����U |
�t�Α� |
25 |
�f�[�^�̂܂Ƃߕ� |
�����f�[�^�܂Ƃ߂̎��K |
| 11 |
�P���E�����in vitro���� |
26 |
���Ƙ_���̏����� |
||
| 12 |
�t�Α̂̕���E���� |
27 |
���Ƙ_���̂܂Ƃߕ� |
||
| 13 |
�זE����V |
�t�E |
28 |
���_���ԕ� |
�e��U���\ |
| 14 |
�g�D�E�v���g�v���X�g����̒P�� |
29 |
���_���ԕ� |
�V |
|
| 15 |
�t�E�����E�̒��� |
30 |
���_���ԕ� |
�@�@�V |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�@�i���s���j |
|
| ���@�ȁ@�� |
�o�C�I�e�N�m���W�[�ւ̊�b�����@�@�@�@ ���ؖF�}���@�@�@�@�@�@�@�@�O���o�� |
| �Q�@�l�@�� |
���������w�u���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ї��G�Y���@�@�@�@�@�@�@�@�ہ@�@�P |
| �]���̕��@ |
�o�ȓ�������ђ�o���|�[�g�ɂ��]���A�o�Ȃ��d�����A�Q�^�R�ȏ�̏o�Ȃ̂Ȃ��҂͐��ѕ]���̑Ώۂɂ��Ȃ��B |
| ��u��� ���ӓ_�� |
�������͍u�`���ɔz�z�B |
| �H�i�Ȋw�Ȏ��ƉȖ� |
| �Ȋw�p��i��j �S�N���@��w���@�Q�P�ʁ@�S�������F�w�ȑS���� |
| ����ړI |
| �� |
���@�@�@�@�� |
�u�@�@�`�@�@���@�@�e�@�@�E�@�@��@�@�@ |
| �P |
���e�͊e�������̎w�������̎w���ɏ]���B |
|
| �Q |
||
| �R |
||
| �S |
||
| �T |
||
| �U |
||
| �V |
||
| �W |
||
| �X |
||
| 10 |
||
| 11 |
||
| 12 |
||
| 13 |
||
| 14 |
||
| 15 |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�@�i���s���j |
|
| ���@�ȁ@�� |
|
| �Q�@�l�@�� |
|
| �]���̕��@ | �ŏ��̎��Ǝ��Ɋe�w����������w��������B |
| ��u��� ���ӓ_�� |
���ȏ��y�юQ�l���ɂ��Ă͊e�w����������w��������B �u�`���e�E��@�ɂ��Ă��ŏ��̎��Ǝ��Ɏw��������B |
| �Y�ƌo�c�w�Ȏ��ƉȖ� |
| ���_�w���[�~ |
| |
| �c���[�~ �R�E�S�N�@���ʔN�@�W�P�ʁ@�S�������F�c���r�� ���[�~�i�[���ł́A��{�I�ɂ͍L�͂Ȍo�ς̏�����ΏۂƂ��ĕ��́A�������s���B�����ŁA���_�I�ȃA�v���[�`���A���_�A���j�A����i����j�̑����I�Ȏ��_����s���B���A�o�ς̏����͂��邽�߂̊�b�Ƃ��āA���Y�W�̂���l�𗝉����邱�Ƃ͓��ɏd�v�Ȃ��Ƃł���B���ׁ̈A���{�ƘJ���̊W�y�т��̕ϗe�ɂ��ĕ��͂�����B�R�N���ɂ́A�[�~�����ꂼ�ꂪ����̓I�Ȓn���ݒ肵�A��̓I�ȃe�[�}��݂��āi�Ⴆ�A�n��J�����A�n���ƁA�n��U�����X�j����Ɋ�Â��Ď�X�̎�@��p���Ē����A���͂��s���B�܂�A����̓I�Ɍ����̒n��Ɏ�̓I�Ɋւ��������āA�n��̖��_��ۑ�A�W�]��͍�����B���̍ہA�e�n��̈ψ����g�D���ɂ���̓I�ɉ��炩�̌`�Łi�ψ��y�уI�u�U�[�o�[�A���������j��̓I�Ɋւ�邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃɂ���āA��茻���̒n��̉ۑ肪��̓I�Ɍ�����悤�ɂȂ�B�S�N���́A���Ƙ_���쐬�̋�̓I��Ƃɓ���B�쐬�ɂ������ẮA�ʓr���Ԃ�݂��ČX�̃e�[�}�ɂ��������Ďw������B���A�_�����\�ׂ̈̃v���[���e�[�V�����\�͂����߂�P�����s���\��ł���B |
| |
| �i��[�~ �R�E�S�N���@�ʔN�@�W�P�ʁ@�S�������F�i��`�� ���Ƙ_���̌����̈���u�o�c�j�v�Ƃ̂��肹���A���u�o�c�j�v�ɐڋ߂����͈͓��ŁA���j�I�A�����̊ϓ_����A��r���͓I���@�̏d�v����F�����Ďw���B�����I���Ȃ���������N���ɓK�������āA��发���ǂ��ǂ݉������A�����̏W�A�_���̏������̊�{��O��I�Ɏw���B�e�L�X�g�g�p�B�O�w���͏A�E�����̂��߂̌l�I�A�E���k�A�i�w���u���w���ɂ͊w�⌤���̃A�h�o�C�X�B���Ƙ_���̊�����ڎw���ď�����i�߂Ă����w���ɂ́A10���������M�쐬�̌o�ߕA������A�Y��B�Ō�̔��\��ւƎw���B |
| |
| ��c�[�~ �R�E�S�N���@�ʔN�@�W�P�ʁ@�S�������F��c�\�q �{�[�~�ł́A��Ƃ̌o�c���͂܂��͉�v�w���̈�̌������s���B���������������s���A���Ƙ_���ɂ܂Ƃ߂�����܂łɂ́A��X����芪�������q�ϓI�ɔc�����A�܂�����̎葫�Ŋ�Ƃ̏������W�E�������A����ɂ��̖��_�𒊏o���A�����̓W�]�ɂ��čl����ȂǁA�����̎菇���K�v�ł���B�{�[�~�ł͕��͑ΏۂƂȂ�ƊE�E��Ƃ̑I����͂��߂Ƃ��Ď����̎��W���Ɋւ��Ă��A��������������̂ł͂Ȃ��A�����܂ł��[�~���̎��含�d���Ȃ���w�����s���B���������āA����s�����A�l����ϋɓI�Ȋw�������}����B |
| |
| ���ԃ[�~ |
| |
| �F�V�[�~ |
| |
| �|���[�~ �P�D�C���^�[�l�b�g�𗘗p�������i�̔� |
| |
| ���[�~ |
| |
| ���G�[�~ �L�[���[�h �q���摜�����A�������[�g�Z���V���O�A��C�G�A���]���A�_�ƃ����[�g�Z���V���O�A�_�Ɛ��Y�Ǘ� |
| |
| ���V�[�~ |
| |
| ����[�~ |
| |
| ���y�H�[�~ |
| |
| �e�n�[�~ |
| |
| �吼�[�~ |
| |
| ����[�~ |
| |
| ���[�~ |
| |
| ���[�~ |
| ���E�ے����ƉȖ� |
| �i���j���瑊�k�_ |
| �S�N���@�O�w���@�Q�P�ʁ@�S�������F���ˌ���
����ړI |
| �� |
���@�@�@�@�� |
�u�@�@�`�@�@���@�@�e�@�@�E�@�@��@�@�@ |
| �P |
���瑊�k�̈Ӌ`�ƖړI |
���瑊�k�̈Ӌ`�ƖړI�ɂ��Ċw�K���� |
| �Q |
���k�̕�����Y�݂ɂ��āi1�j |
�ꎟ�I�����j�[�Y�i���ׂĂ̎q�ǂ��A�w�K�A�ΐl�W�Ȃǁj |
| �R |
���k�̕�����Y�݂ɂ��āi2�j |
�I�����j�[�Y�i�ꕔ�̎q�ǂ��A�w�K�A�ΐl�W�Ȃǁj |
| �S |
���k�̕�����Y�݂ɂ��āi3�j |
�O���I�����j�[�Y�i����̎q�ǂ��A�s�o�Z�A�����߁A��s�Ȃǁj |
| �T |
�w�Z�J�E���Z�����O�̗��_�i1�j |
���k�Ғ��S�Ö@�̗��_�Ɖ��K |
| �U |
�w�Z�J�E���Z�����O�̗��_�i2�j |
�s���Ö@�̗��_�Ɖ��K |
| �V |
�w�Z�J�E���Z�����O�̗��_�i3�j |
�u���[�t�Z���s�[�̗��_�Ɖ��K |
| �W |
�w�Z�ɂ����鋳�瑊�k�̎��� |
��̓I�ȋ��瑊�k�̎����ʂ��ċ��t�̑Ή����l���� |
| �X |
���瑊�k�������w�Z�o�c |
����I�Ȋw�Z�o�c�ɂ����Ăǂ����瑊�k���������w�� |
| 10 |
���瑊�k�������w�K�w�� |
����I�Ȋw�K�w���ɂ����Ăǂ����瑊�k���������w�� |
| 11 |
���瑊�k���������犈�� |
����I�ȋ��犈���S�ʂɂ��ċ��瑊�k���ǂ����������w�� |
| 12 |
���t�̑Ή��̌��E�ƍZ���A�g |
���t�̑Ή��̌��E����ی����A�g��Z���A�g�̏d�v�����w�� |
| 13 |
�ƒ�E�n��Ƃ̘A�g |
����I�ȉƒ�E�n��Ƃ̘A�g�̕K�v�����w�� |
| 14 |
�O�����@�ւƂ̘A�g |
���a�@�E�������k���E�x�@�ȂǂƂ̘A�g�ɂ��čl���� |
| 15 |
������ |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�@�i���s���j |
|
| ���@�ȁ@�� |
�Ȃ� |
| �Q�@�l�@�� |
|
| �]���̕��@ |
������{������K�E���|�[�g�쐬��50���A�ŏI��̎�����50���A�������o�Ȃ�80���ȏ� �Ƃ���B |
| ��u��� ���ӓ_�� |
�@���O�Ɏ����ŊY�������ǂ�ł��邱�ƁB�A���ƒ��̗l�X�Ȏ��K�ɂ́A�ϋɓI�ɎQ�����邱�ƁB�B����̂���w���͂ł��������ƒ��A���邢�͎��ƌ�ɂ��邱�ƁB�C��L�ȊO�̎���͊w����p���[��k-seto��bioindustry.nodai.ac.jp�Ɏ��⎖�����������ނ��ƁB |
| �i���j������K�T |
| �R�E�S�N���@�ʔN�@�R�P�ʁ@�S�������F��㐳���E���ˌ��� ����ړI �S�N���Ɏ��{����u������K�v�͒��w�Z�E�����w�Z�Ɉϑ����čs�����̂ŁA���E�ے��̊w�K�̑��d�グ�I�ȈӖ��������A��Ϗd�v�Ȏ��K�ł��B������K�Z�͓��X�̋��犈�����s���Ă��錻��Ȃ̂Ő^���ȋC�����Ŏ��K�ɗՂނ��Ƃ���ł���B���̂��߂ɂR�N�����珀���Ǝ��O�w�K���K�v�ł���B�S�N���łQ�`�S�T�ԁA���K�Z�ŋΖ��i���K�j���邱�Ƃ͒Z���Ԃł��邪������̌�����M�d�Ȏ��K�ł���A���̌��ʂ͌v��m��Ȃ��B����܂łɊw�K���Ă��������͂���������ł���A���ɋ����Ƃ��Ă̎�����������ł�����B���K�Z�̎w���ɏ]��������K���Ƃ��Ă̎��o�ƐӔC�̂��ƂɁA�L�Ӌ`�Ő��ʂ̂�����K���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �� |
���@�@�@�@�� |
�u�@�@�`�@�@���@�@�e�@�@�E�@�@��@�@�@ |
| �R�N |
||
| �P |
��P��I���G���e�[�V�����A�S�� |
������K�̈Ӌ`�A���{�T�v�A���K�\��Z�̑I��Ǝ����葱�����A���K���|�[�g�u���z�̋��t���v |
| �Q |
��Q��I���G���e�[�V�����A�U�� |
������K�������z�z�A���K���|�[�g�u�w�Z�����v�ɂ��� |
| �R |
��R��I���G���e�[�V�����A10�� |
������K�̐S�\���A�w�Z�̈���A������K��������o�Y�A�˗����A�i������K�Z����j |
| �S |
��S��I���G���e�[�V�����A�P�� |
�w�K�w���Ă̍쐬�ɂ��āA���Ƃ̐i�ߕ� |
| �T |
��T��I���G���e�[�V�����A�P�� |
���E�����ɂ��u����i���w�Z���A���͍����w�Z����\��j |
| �S�N |
||
| �U |
��U��I���G���e�[�V�����A�S�� |
���K���O�w���A�����ӁA�e���ނ̔z�z |
| �V |
������K���{�A�T���`11�� |
���K�Z�ւ̔h���A������K�A�K��w�� |
| �W |
������K��i�P�j |
���K���|�[�g�A�i�e���̕j |
| �X |
������K��i�Q�j |
�� |
| 10 |
��V��I���G���e�[�V�����A12�� |
������K������o�A���E�Ɋւ���A���P�[�g�L�� |
| 11 |
�\���� |
|
| 12 |
�\���� |
|
| 13 |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�@�i���s���j |
|
| ���@�ȁ@�� |
�u������K�̎�����v�@�@�@�@�@�@�@�{�w�A���E�E�w�p���Z���^�[ |
| �Q�@�l�@�� |
|
| �]���̕��@ |
���|�[�g�A���K�Z�ł̕]���A�o�ȏA��u�ԓx���ōs���B�S�N���̎��K�I����ɒʎZ�]������B |
| ��u��� ���ӓ_�� |
(1)�R�N���S���ɗ��C�o�^��K���s�����ƁB���o�^�҂͋�����K���ł��Ȃ��B (2)�I���G���e�[�V�����͂R�w�Ȗ��ͤ�w�Ȗ��Ɏ��{����̂Ōf���¤�w�������m�F���邱�ƁB |
| �i���j������K�U |
| �R�E�S�N���@�ʔN�@�Q�P�ʁ@�S�������F��㐳���E���ˌ��� ����ړI �S�N���Ɏ��{����u������K�v�͒��w�Z�E�����w�Z�Ɉϑ����čs�����̂ŁA���E�ے��̊w�K�̑��d�グ�I�ȈӖ��������A��Ϗd�v�Ȏ��K�ł��B������K�Z�͓��X�̋��犈�����s���Ă��錻��Ȃ̂Ő^���ȋC�����Ŏ��K�ɗՂނ��Ƃ���ł���B���̂��߂ɂR�N�����珀���Ǝ��O�w�K���K�v�ł���B�S�N���łQ�`�S�T�ԁA���K�Z�ŋΖ��i���K�j���邱�Ƃ͒Z���Ԃł��邪������̌�����M�d�Ȏ��K�ł���A���̌��ʂ͌v��m��Ȃ��B����܂łɊw�K���Ă��������͂���������ł���A���ɋ����Ƃ��Ă̎�����������ł�����B���K�Z�̎w���ɏ]��������K���Ƃ��Ă̎��o�ƐӔC�̂��ƂɁA�L�Ӌ`�Ő��ʂ̂�����K���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �� |
���@�@�@�@�� |
�u�@�@�`�@�@���@�@�e�@�@�E�@�@��@�@�@ |
| �R�N |
||
| �P |
��P��I���G���e�[�V�����A�S�� |
������K�̈Ӌ`�A���{�T�v�A���K�\��Z�̑I��Ǝ����葱�����A���K���|�[�g�u���z�̋��t���v |
| �Q |
��Q��I���G���e�[�V�����A�U�� |
������K�������̐����z�z�A���K���|�[�g�u�w�Z�����v�ɂ��� |
| �R |
��R��I���G���e�[�V�����A10�� |
������K�̐S�\���A�w�Z�̂P���A������K��������o�Y�A�˗����A�i������K�Z����j |
| �S |
��S��I���G���e�[�V�����A�P�� |
�w�K�w���Ă̍쐬�ɂ��āA���Ƃ̐i�ߕ� |
| �T |
�]�܂��������Ƃɂ��� |
���̏������A�g���� |
| �U |
���Ǝ��K�̓W�J |
���Ƃ̋�̗� |
| �V |
�r�g�q���̍u�b�̘b���� |
�r�g�q�̍u�b�̉��K |
| �W |
��T��I���G���e�[�V�����A������K�ɗՂނɓ������ĂP�� |
���E�����ɂ��u����i���w�Z���A���͍����w�Z����\��j |
| �S�N |
||
| �X |
��U��I���G���e�[�V�����A�S�� |
���K���O�w���A�����ӁA�e���ނ̔z�z |
| 10 |
������K���{�A�T���`11�� |
���K�Z�ւ̔h���A������K�A�K��w�� |
| 11 |
������K�� |
���K���|�[�g�A�i�e���̕j |
| 12 |
��V��I���G���e�[�V�����A12�� |
������K������o�A���E�Ɋւ���A���P�[�g�L�� |
| 13 |
�\���� |
| �i�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ҁE�Ҏҁj �@�@�@�@�@�i���s���j |
|
| ���@�ȁ@�� |
�u������K�̎�����v�@�@�@�@�@�{�w�A���E�E�w�p���Z���^�[ |
| �Q�@�l�@�� |
|
| �]���̕��@ |
���|�[�g�A���K�Z�ł̕]���A�o�ȏA��u�ԓx���ōs���B�S�N���̎��K�I����ɒʎZ�]������B |
| ��u��� ���ӓ_�� |
(1)�R�N���S���ɗ��C�o�^��K���s�����ƁB���o�^�҂͋�����K���ł��Ȃ��B (2)�I���G���e�[�V�����͂R�w�Ȗ��́A�w�Ȗ��Ɏ��{����̂Ōf���A�w�������m�F���� |