第4回 留学報告書
(タイ王国・カセサート大学)
国際食料情報学部 国際農業開発学科
4年
水谷 優理
留学中の最後の報告書となりました。カセサート大学では、2nd Semesterの期末試験が2月27日〜3月10日まであり、その後は約2ヶ月半の長い夏休みに入ります。今回は、期末試験、夏休み中、新学期の生活について報告します。夏休みは、実習に行ったり実家に帰ったりという学生もいますが、学内に残り普段と変わらず授業を受ける学生も多くいます。
<Final Exam>
期末試験もタイ人学生と同じように私も受けました。『Quality of Fresh Fruits and Vegetables』は前回と同様、授業内容を理解しているか、先生と学生の1対1で質疑応答を30分、そして期末試験では『Overview in Agriculture』も受けました。こちらの授業は中間試験がなく、授業後に出す毎回のレポートと出席、期末試験で授業評価されます。『Overview〜』の授業は、先生がパワーポイントを使って授業を進めていきます。私はそのパワーポイントをノートに書き写す事だけで精一杯で、授業中や授業後に辞書を引きながら授業についていくといった感じでした。授業の時にいつも不思議に思っていた事は、殆どの学生はノートを取らないという事。ノートに書くよりもとにかく先生の話を聞くほうが大事なのかと勝手に思っていましたが、試験前にそのパワーポイントはコピー屋で売られていて、それを知っていた皆はだからメモを取らなかったのだと後で気づきました。授業のプリント等は授業中に配られたり、毎回授業の前にコピー屋で買い準備したり、試験前に各課がいっきに並ばれたりと各授業によって違います。私は毎回パワーポイントを写しては単語の意味を理解する等復習をしていました。これは、試験前にいっきにやらずに済んだので自分の為に良かったと思います。私もタイ人の学生と同じように試験に挑む事になりました。筆記試験はタイに来てから初めての事で、試験前は不安と焦りで落ち着いていられませんでした。何せ、問題がタイ語ですから。この授業は農業を学んでいる学生には簡単で、「普通に勉強すればAは取れるよ。」と言われていますが、私にとっては簡単ではなく、辛い辛い試験になりました。試験時間はタイ人学生でも2時間でしたが、私はもっと時間がかかると察した担当の先生が、私だけ先生の部屋で受けさせてもらい、更に辞書の持ち込みを許可し、時間の延長までして下さいました。これは本当にありがたい事でした。しかし、問題数を見てビックリ、全部で150問ありました。日本語でも150問の試験はきついと思いますが、それがタイ語なので一瞬目が点になってしまったぐらいです。気を引き締め試験を受けましたが当然2時間では終わらず、何時間もかかってやっと終わらせる事が出来ました。スラスラと問題を読めれば問題は一つ減るのですが、私の場合は問題を理解する事からしなければなりません。結果はと言うと、やっぱり…と言った感じで努力の足りなさを感じ中間試験と同様反省点が多く悔しい思いをしました。
<Farm Practice>
期末試験後すぐに、学科の実習がありました。Horticulture3年生は、この実習が必修授業で10月か3月に行かなければなりません。私は前回も行きましたがアドバイザーの先生、実習担当の先生、実習先の先生にお願いし、今回も参加させて頂きました。少しでも熱帯農業に触れ実習を多くしたかったから、実習を通しての友達との共同生活で得られるものは普段の生活では得られないと思ったからです。せっかくの機会を自分でつかまなければそのままで終わってしまうと思います。第2回報告書にも書きましたが実習先はコラート県・パクチョン農場です。
前回の実習は、急遽参加させて頂くことになったのでただ混ぜてもらえたという感じでしたが、今回は正規履修をし、単位も貰えるとの事なので、実習前にオリエンテーションに参加し実習の中での係りの当番も与えられました。実習内容・時間は、前回とだいたい同じでしたが作業内容は、前回とはあまりかぶらず幅広い作業ができたと思います。実習の最後には、バラ農園、観葉植物園、トウモロコシ農場、ブドウ農園等の見学にも行きました。皆ともすぐに仲良くなり実習はあっという間に終わってしまったと感じました。後々この実習に行って本当に良かったと思えることも多々あり、前回の実習にも行ったのでHorticultureの3年生(今は4年生になりましたが)とは全員友達になれて良かったです。Horticultureの学科は他学科に比べ人数が多いです。卒業した4年生は、私を含め86人いました。




<ソンクラーンフェスティバル>
別名「水掛祭り」とも呼ばれているこのフェスティバルは、タイにおいて最も注目を集め、盛大に行われる行事です。と言うのも、4月のこの時期(今年は4月13日〜16日でした)、タイは旧正月になります。前回の報告書でも書きましたが、タイには計3回のお正月があり、タイ正月は4月になります。13日に新年となり、水を掛け合って新年を祝います。北部の習慣で特にチェンマイ県の水掛祭りはタイの中で一番有名で、多くの観光客や、地元の人で賑わいます。ソンクラーンとは、タイ語で「移動、場所を変える」という意味で太陽の位置から双魚宮(魚座)から白羊宮(牡牛座)に移る日の事だそうです。水は徳を運んでくると言われ、徳を積んだ仏像や、僧侶、王などに水をかける事によってその徳を分け与えてもらえると言われています。水掛のもう一つの意味は、水を掛け合う事で昨年一年間の嫌な事・悪い行いなどを洗い流し、良い状態で新年を迎えましょう、という意味もあるそうです。最初で最後かもしれないこの行事をチェンマイで体験してみたいと思い、チェンマイまで行ってきました。本当に、誰彼構わず皆水を掛けます。水鉄砲で人に水をかけるなんてものは可愛らしく観光客のやる事で、タイの人はバケツやホースでそのまま水をかけてきたり、トラックの荷台にドラム缶を用意し掛けてきたりするので、外を歩けば1分もしない内にずぶ濡れ状態。信号待ちのバイクは逃げ場がないので良いターゲットとなっていました。そんな日が4日間続くと流石に疲れるので2日間くらい体験してやめましたが、とにかく皆で祝えるとても楽しい正月のお祭りです。
<Special Problems>
今までアドバイザーの先生と話し合っていました『special problems』の授業は農大の卒論にあたる授業です。夏休み中から本格的に始まり、夏休み・1st semesterはこれ1本で絞っています。私のテーマは、マイナーな熱帯果樹に含まれるantioxidant、vitamin
C、その他基本成分と貯蔵との関係についてです。試供果実は、pummelo、wax apple、salak、duku。普段日本にいると見慣れない果物です。アドバイザーの先生と何度も話し合い決めました。しかし、自分の計画性の悪さとタイの連休がこの時期に多いことから実験を始めるのが遅くなり、帰国までに終わらせる事が出来るのか心配です。各学科とも、学科棟があるのですが、Horticultureは農学部の中にあるので何かと便利です。今は毎日朝から学部の中の実験室に籠もりっぱなしで実験をしています。私の研究室で実験をしている人が少なく、学生や先生方、事務の方も夕方になると帰ってしまい、暗い農学部の中で作業している事も多々あります。夕方になると農学部の棟は閉まってしまうのです。閉まる前に中に居れば良いのですが、17:00を過ぎると特別な人以外は外から中に入ることができません。今はもう慣れましたが、静か過ぎて怖いくらいです。土日・祝日も学部が閉まり、平日しか出来ない不便さも感じています。図書館にも行きたいのですが、夏休み中は16時半で閉ってしまう点と、16時半と言ってもだいたい16時前には図書館を閉める準備をしているので早く出て行ってくださいオーラを感じ、なかなか長居できません。




<プミポン国王即位60周年記念式典>
6月9日。今年でプミポン国王陛下の即位60周年を迎えられた事から、タイでは多くの慶祝行事や式典が開かれ、この式典の為各25カ国から国王・王妃または皇太子がお見えになり在位60周年を祝いました。日本からも天皇・皇后両陛下がご出席されました。今、タイの街は、国王一色=黄色のシャツを着た国民で染まっています。黄色は国王陛下の誕生日である月曜日の色を表します。式典は旧・国会議事堂で行われ国王を祝おうとその広場には数十万人のタイ国民が集まりました。私もせっかくなので行って見てみたいと思ったのですが、人・人・人で大変だと思い、テレビでその様子を見ていました。また、タイではRoyal project(王室による社会開発事業)に力を入れており、プミポン国王は即位後、貧困な地域に足を運び視察をし、問題点を出してきました。北部・チェンマイ県では、それまで山岳民族が貧しい生活をし、焼き畑農業をしながら移住地を転々としていたり、アヘン栽培、不法森林伐採を行っていたりして、タイ国に大きな損害を与えている状況を目にし、カセサート大学に植林調査の依頼をされました。それから、数種類の果樹が栽培された事でこのRoyal projectが始まりました。その他に、人口的に雨を降らせる計画、教育・医療支援、治水整備など行われました。記念行事の中で、即位60周年にちなんだ展示会も行われ、国王のご活躍を見に行ってきましたが、タイ国は農業で成り立っている事、プミポン国王が偉大であり、タイ国民誰もが敬愛していると実感しました。
KPSでも、国王に敬意を表す式典が行われ、農学部の先生・学生が出席しました。今や街中が黄色のシャツを着ていますが、農学部でも、「農学部・キャンペンセン」の国王の黄色の服の販売が始まり、先生や学生は皆購買します。今年の終わりまで毎週月曜日はそのシャツを着る事を義務付けられました。すぐに売り切れた為、私は追加注文で買うことが出来ました。

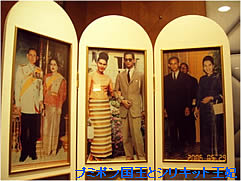

<ラップノーン>
5月下旬に新学期となったタイの大学も、新入生が沢山入学してきました。第2回報告書にもラップノーンの事を載せましたが、一年の始まりのラップノーンが6月に行われます。2年生だったルームメイトの一人も3年生になり、1,2年生に命令する側になり見ていて変な感じでした。今回感じたのは、前よりも先輩の命令がきつくなった気がします。6月は、毎週月・木曜日の夕方から夜まで1ヶ月間行われ、最後の土日に大きなラップノーンがありました。夜中の3時から夕方まで、土砂降りでずぶ濡れになろうが構わず一日中行われました。水田の中に入り、顔をつけさせられたり、正座や立ちっぱなしが続いたり、先輩の命令に素早く対応しなければなりません。とにかく見ていて残酷だと感じる時もしょっちゅうです。他大学にもラップノーンはありますが、農業大学のしかも農学部の様な少し変わったものはないらしいです。カセの中でも学部によって少し違います。




<プーケット国際マラソン>
インド洋大津波の被害があったプーケット島にて6月18日、第一回プーケット国際マラソンが開かれました。津波の被害から1年半、被害のあった所はもうキレイに元通りになったと聞きますが、観光客が戻らないなどの地元の人の声から今年から国際マラソンが開かれました。この大会の参加費用が津波被害の復興支援にも繋がると聞き、留学中の勉学とは関係ないのですが、私も参加してきました。各国からランナーが集まり、国際色豊かな大会になりました。この大会を通して津波被害から復興したプーケットを世界に伝えられたらと思っています。
<おわりに>
留学期間も残り2ヶ月となり残りのタイ生活を考える一方、日本に帰国してからの事も考えるようになりました。最後の1ヶ月になると、やりたい事が沢山出てきて大変だから計画はしっかりするように言われてきましたが、本当にそうだと思います。あれをやれば良かった、これをやりたい、とこの時期になって思うこともあり、帰国まで忙しくなりそうです。ここの生活は、時間に縛られていた東京の生活とは全く違い、これをしなさいというものは特になく、自分のペースで生活できます。逆にそのペースをコントロールするものが何もないと、ただ時間だけが過ぎていき、残るものが少なくなってしまうので、今日1日何をするか計画持って過ごす事はとても大事だと実感しました。留学生活で手に入れたものを何かしらの形で自分の将来に繋げていけたらと思っています。1日1日を大切に、残りの生活を悔いのない様に過ごしたいと思います。