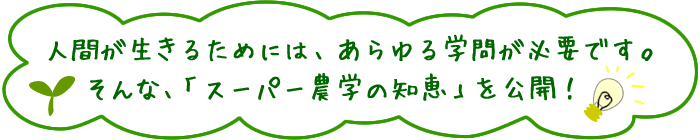
農地復興に研究者の総力を
甚大な塩害と放射能汚染
応用生物科学部生物応用化学科 教授 後藤 逸男
3月29日の農水省発表によれば、東日本大震災の津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の推定面積は水田20,151ha、畑3,449ha、合計23,600haで被災6県の耕地面積の2.6%に達する。特に、宮城県では県内耕地面積の11%にもおよぶ。また、4月12日の農水大臣の記者会見では、福島第一原発の周囲20〜30km範囲内での農地では放射能汚染により作付け許可は困難という見方を示した。
まさに、日本農業にとってはこれまでに経験したことのない試練の時を迎え、今こそ農業技術者・研究者が復興に向けて総力を注ぎ込まなければならない。その先駆けとして、東京農業大学が果たすべき役割は大きい。
筆者の専門分野である土壌肥料学から、今後の塩害と放射能汚染農地対策について考えてみたい。
干拓や高波被害などを参考に
海水には塩化ナトリウムを主成分とする塩類が約3%含まれている。一方、植物が正常に生育できる塩分濃度は0.3%程度であるので、津波を被った農地での作物の作付けは当然できない。しかし、日本農業の歴史を約半世紀遡れば、戦後の食料難対策のひとつとして児島湾や八郎潟などの干拓事業が行われた。遠浅の海に堤防を築き、その中の海水を排水して海底を新たな農地にする国家プロジェクトであった。海底の土には当然のこととして、ナトリウムや塩素イオンが大量に残存していたが、これらの成分は土壌に吸着されにくいので、真水で洗い流せば比較的速やかに地下に流出して、優良な農地として利用できるようになった。また、干拓地を含めた全国各地の海浜地域の農地では台風などの高波による塩害を被ってきた。熊本県八代海沿岸の宇城市や八代市では1999年9月の台風18号による高潮で、水田や畑計約1,400haが浸水被害を受けたが、農地に堆積したヘドロを除去した後、石灰資材の施用と湛水・代掻きによる除塩対策を行い、当初数年かかるとみられていた復興が早く進み、露地野菜は半年後に収穫でき、稲作も翌年の田植えに間に合った。熊本県はいち早く塩害対策の技術提供を申し出ている。
真水を用いた脱塩処理
3月29日には、JA全農でも具体的な水田での塩害対策の手順について提案し、がれきやヘドロを取り除いた後、作土の電気伝導率(EC)を測定する。そして、その値が0.3〜0.6mS/cm以下であれば対策は不要としている。この値は塩分濃度として0.1〜0.2%に相当することから、妥当な判断である。作土の電気伝導率がそれ以上の場合には、八代海沿岸でも行われたような湛水と代掻きを行い、塩分を下層に流す。この際、消石灰や炭酸カルシウムなどの石灰資材を併用することが推奨されている。その理由は、土壌に吸着されているナトリウムイオンをカルシウムイオンと入れ替える(交換する)ことで、土壌から塩分を溶出させ水に流れやすくするためである。また、ナトリウムイオンが吸着された土壌は分散しやすく、土壌粒子が流されることを防ぐためでもある。このような方法で除塩された後には、土壌の肥沃度を高めるためのケイ酸やリン酸肥料の施用を勧めている。
以上のように、津波による農地の塩害は真水を用いた脱塩処理が有効な対策となるであろう。なお、そのための対策資材として、カルシウム、ケイ酸の他に数%には過ぎないがリン酸を含んだ製鋼スラグの活用が考えられる。製鋼スラグとは、全国各地の製鉄所で鋼を製造する過程で年間約一千万トン生産される副産物で、その一部に過ぎないが肥料として農業利用されている。
農業者にとって塩分といえば、マイナスイメージの強い物質であるが、高潮や風による塩害を受けた農地で栽培されたトマトやネギの糖度や品質が高まったことから、海水をかけて作物を栽培する塩水農法なども行われている。野菜栽培などでは、農地に残った塩分をうまく活用することを考えることも一案かもしれない。
チェルノブイリ事故に学ぶ
放射能汚染の主な原因核種はヨウ素(133I)とセシウム137(137Cs)であるが、対策を必要とするのは半減期が30年と長いセシウムである。土壌や植物中でのセシウムの挙動については、(社)日本土壌肥料学会の土壌・農作物等への原発事故影響WGから詳細な情報が提供されている(http://jssspn.jp/info/index.html)。過去の原水爆実験時やチェルノブイリ原発事故などに関連する国内外の研究文献などをとりまとめた最も信頼できる情報である。
それらを要約し、さらに筆者のコメントを加えると次のとおりである。
農地に降り注いだ放射性セシウムは、土壌中に存在するカリウムイオンと同じようにセシウムイオンとして挙動する。土壌には陽イオンを吸着する能力があるため、セシウムイオンは容易に下層には移動しない。特に、チェルノブイリ一帯のチェルノーゼムと呼ばれる土壌中の主要粘土鉱物であるモンモリロナイトには特異的に吸着され、その吸着力はカリウムやアンモニウムイオンより強い。土壌中のセシウムは作物の根から吸収されるが、その程度はカリウム濃度に影響され、多量のカリウムがあれば、セシウムは吸収されにくい。
4月13日の朝日新聞夕刊には、「地表の放射能拡散せず」「田畑の土 入れ替え有効」と報道されたが、日本の土壌はチェルノーゼムとは根本的に異なりハロイサイトやアロフェンという粘土鉱物が主体であるので、おそらくセシウムの吸着力はチェルノーゼムより弱い、さらに日本の雨量はウクライナ地域の約3倍以上であるので、セシウムが土層を移動する速度はウクライナより速いと思われる。ただし、過去のわが国でのデータによれば、作土から容易に移動することは認められていない。作土を入れ替えても放射能そのものがなくなるわけではないので、田畑の土の入れ替えを行うことなく、その場所での対策を施すべきである。
ゼオライト利用の研究に着手
また、4月14日の毎日新聞朝刊には、ウクライナでの事例を基に「ナタネで土壌改良」「フクシマも早期に対策を」と報じられた。政府は一定レベル以上に放射能汚染された農地での作物作付けは困難としているが、裸地にすれば浸食や風食により汚染土壌が拡散する。そこで、ナタネを作付け、その種子からディーゼル油を生産することは合理的であるが、ウクライナと日本では気候や立地条件が異なる。水田では窒素がアンモニウムイオンとして存在するため、陸稲より水稲の方がセシウムを吸収しやすいとの過去のデータもある。そこで、汚染された水田には飼料米、畑にはやソルゴーあるいはデントコーンのようにカリウム吸収量の多い(セシウムを吸収しやすい)作物を作付ける。これらはいずれも飼料作物であるが、もちろん家畜のえさにはせず、バイオガスやエタノール原料とする。発酵残査や汚泥は焼却してその灰を適正処分する。飼料作物の他にも、すでに広く報道されているようなヒマワリの作付けも有効で、このようないわゆるファイトレメディエーションにより農地の作土から放射性セシウムを吸収して、放射能レベルを下げることが現実的な対策と考えられる。
4月15日のNHKテレビニュースによると、天然ゼオライトを入れた土嚢袋を原発近くの海に沈め、セシウムを吸収させる試みを始めた。ゼオライトとは、土壌の10倍くらいの陽イオン交換能を持つ天然鉱物で、東北地方は世界一の良質産地である。筆者はこのゼオライトの土壌改良資材効果を長年研究しているが、アンモニウムやカリウムイオン吸着力がずば抜けて高い。その性質を利用した今回の試行であろうが、海水中には多量の陽イオンが含まれているので、ゼオライトの効果を十分発揮できない。それよりも海に流れ出しているあるいはその可能性が高い高レベル汚染水の処理に用いるべきである。
また、地震発生直後からインターネット上には様々なゼオライトに関する情報が流れている。セシウム汚染土壌にこのゼオライトを施用すると、間違いなくセシウムはアンモニウムやカリウムイオンのようにゼオライトに特異吸着される。ただし、ゼオライトに吸着されたセシウムが植物に吸収されるのかあるいは、吸収が抑制されるのかは定かではない。上記のようなファイトレメディエーションによる対策を実行する場合、ゼオライトに吸着されたセシウムが植物に移行しにくいのであれば、ゼオライトを施用すべきではない。
天然ゼオライトは正しく使えばすばらしい水質浄化・土壌改良資材であるが、かつての農業界では「魔法の石」あるいは「いんちき・いかさま資材」の代表格であった。
数少ない国産天然資源で、その埋蔵量は無尽蔵ともいわれるゼオライトや農業界では未利用資源といえる製鋼スラグなどの土壌改良資材が今回の大震災で被災した農耕地の復興の一助となり得るかを検討すべく研究を開始した。
