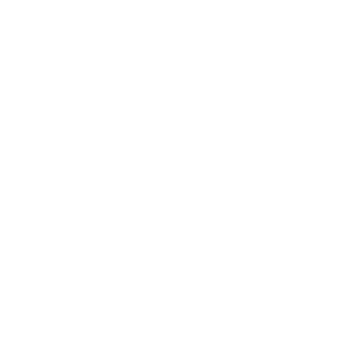オホーツクのスローフードと「食・農」の地域ビジネス
2014年11月1日
生物産業学部地域産業経営学科 教授 美土路 知之
はじめに〜秋を迎えて実りのオホーツク
北海道は豊穣のときを迎えている。大型のハーベスターから勢いよくバレイショが舞い、累々と圃場の片隅に積み上げられていく。これらは主にデンプン用の原料として出荷されていたが、輸入デンプンのコーンスターチとの競合にさらされ、冷凍食品やポテトチップスへの食品加工原料としてそれぞれのメーカーに納入されている。これも輸入品との競争が厳しく、食用の生食イモとして市場拡大のチャンスをうかがっている。以前であれば北海道産のバレイショは男爵とメークイーンが代表格であったが、いまでは多様化が進み耳慣れぬ名のものがスーパーの店頭をにぎわすようになった。
バレイショの掘りとりが終わると、次は砂糖だいこんのビートの収穫期を迎えるが、道内主産地はおおむね3大糖業が原料を受け入れている。しかし、これも近年では甘味原料として2次加工部門のクライアントであった飲料や菓子・パンメーカーが、内外のコスト競争が厳しさを増す中、異性化糖などの廉価な甘味料へと調達先を変えつつある。
北海道というと、広大な畑地に広がる農作物の圃場や牧草地のイメージが定着しているが、その内実は国際競争や出荷価格の低落傾向など、まことに厳しいものがある。しかも規模が大きい分、資材類への投入コストや施設設備の固定資本の償却などは経営を圧迫している。
一方、海の豊穣は「アキアジ」ともいわれているサケ漁が最盛期(11月まで)で、オホーツクの浜には定置網の仕掛けとオレンジ色のブイが沖に向かって延々並ぶ。これらに加えてホタテやシラウオやシジミ(網走湖)なども旬の時季を迎えている。しかし、気候変動(海水温の上昇傾向と爆弾低気圧といわれる台風並みの強い風雨が来襲)から生態系の変化やサケの回帰率低下への懸念など、漁業者らの不安材料が増しているのも事実である。
こうした中で、従来のような穫(獲)ってそれを大消費地や業務需要として大口クライアントに販売するだけでは、地域の産業や経済にとって先細りとなるのではとの漠たる不安も醸成されている。そうした意味からも、加工やサービング(一口サイズや調理済みなど、消費者の食卓に寄り添ったサービス性重視など)の強化を図った付加価値化や地域ビジネス志向が強まっている。
いわゆる「6次産業化」や「農商工連携」など、地域を拠点にして最終消費との密接な関係が模索されている。これらは、TPP交渉への対応と成長戦略を進める政府の重点施策ともされているが、それにもまして、地域の側からも所得向上と雇用創出による経済と社会の活性化は死活問題にもなっている。
地域活性に取り組む地域産業経営学
ところで、東京農業大学生物産業学部(オホーツクキャンパス)では平成元年の創設以来、地域の一次資源を基点にした「生産、加工、流通・ビジネス」を基本命題に、現場に則した教育と研究を進めてきた。端的にいえば、「水と空気と食べ物がおいしい」、質の高さに磨きをかけつつ商品開発を進め、情報発信やマーケティングによって「買ってもらえる」商品の価値実現を追求してきた。
農畜産物や生乳類、漁獲物をはじめとした海産物、さらには未利用だった資源や、“目からウロコ”の素材の発見や開発など、生産活動の現場である「圃場」から最終消費の「食卓」に至るプロセスを価値連鎖(バリューチェーン)で結んで、生産と生活を豊かにするための教育研究を目指してきた。筆者の所属する地域産業経営学科は、地域の活性を創出する担い手育成と実践的なコーディネート活動や地域イベントへの参画などの貢献を積み上げてきた。
それらの成果としては、(1)企業や農林漁業の経営者や後継者をビジネス活動の現場に送り出してきたこと (2)地域や一次産業に係わる機関や諸団体で、身を挺して服務する人材を送り出してきたこと (3)現場密着で素材のもつ本質を理解し、それに創造性のある付加価値をつけて情報発信をするスキルも身につけさせてきたことが挙げられる。本年度で満25周年を迎え、2000人(学部では7000人)以上の卒業生がそれぞれの「畑に還って」活躍している。その原動力がオホーツクでの学生生活の中にあったし、近い将来に日本の農と食を地域から支える力を持ち始めている。
さらにいえば、スローフードやスローライフの営みを、流行コトバとしてでなく、オホーツクでの日常生活の中で理解し、その審美眼やアイデアを培ってきた意味は大きい。
ファストなやり方からスローにギアチェンジすることの意味
右肩上がりの経済成長を念頭においた農林漁業政策の近代化促進が見直される昨今、そのやり方を「ファスト」から「スロー」へと転換させる意味が問われている。そこではイタリアのスローフード協会の会長・C.ペトリーニがいった「おいしい、きれい、ただしい」の視点に沿って地域活性の意義について再認識されるべきであろう(*1)。
つまり、「おいしい」ことは地場の新鮮で安心できる食料や食材を質的に担保する適正。「きれい」は環境や水・資源に対して過剰な負荷を与えないやり方をする適正。「ただしい」は、生産者や調理人に対して低コストや加温ハウスなどによって季節外利用を強要することなく、公正な価格で取引する適正。これらの相互理解と実践を家族や集落だけで完結させるのではなく、コミューネ(地域社会)として合意し、融通し合うことも含意されている。
さらにイタリアでは、(1)規模は小さくても質の高い食料を提供してくれる、地域の生産者や調理人の経営と暮らしを守る。(2)地域に根付いている伝統的な品種や食材、調理レシピなど「マンマ(お母さん)」の味や伝統を伝える。それらを守るために、エコグルメ(環境共生を優先した食生活)や食味教育を地域単位で実践し、「地域固有性」や「多様性」を維持して食文化と生活文化を紡いできた。これらを縦横に結びつけながら、アグリツーリズモを取り入れたマチ作りに連動させ「スローシティ(*2)」の運動へと発展させている。
これらをわが国の地域興しや活性化への実践に直ちに取り入れることは難しいが、少なくともオホーツクキャンパスでの生活を経験した学生は、個々の要素を直接間接に身につけて学舎から巣立っている。
首都圏出身者が全体の6割強を占める学生達のなかには、ファストな「都会」生活よりもオホーツクでの暮らしにかけがいのない価値とスローライフの悦びを発見しているものも少なくない。
地産「3消」の付加価値で地域をおいしく元気に
そうした問題意識から、オホーツクのスローフードについて食材から最終消費の場面である食卓をつないで、地域オリエンテッドのバリューチェーンを展開し、もともと質の高い素材に適正な加工の手を加えて結びつけることで、地域活性への重要視点が見えてくる。北海道やオホーツク地域のもっている豊かな自然と一次資源にひとヒネリを加えて、地産地消・地産他消・地産来消の「3消」を組み合わせれば、目指すべき将来図を描くことができよう。
こうして、すでに成立している農や漁の自給圏と、他地域や国内を基本にグローバルな視点をもつマーケット展開、加えて観光やツーリズムと一体となった「生活体験」や「食体験」で他地域から来訪者の取り込み(*3)といった、3方向への展開を視野に入れることで地域活性を増進していくことは可能である。これらは、政策「目線」としてではなく、地域の意思決定と創造性の発揮によってこそ客観的な意義を持つ。
以上が地域産業経営学科および研究室の研究課題であるが、引き続き、オホーツクのさまざまな素材とビジネスへの取り組み事例を考察して、その発展経路やビジネスモデルについて掘り下げる作業を(「オホーツク フーズ・フー(foods who)」の地域食物紳士録として)進めているところである。
(*1) C.ペトリーニ「スローフードの奇跡〜おいしい、きれい、ただしい」(石田雅芳訳、三修社2009.11)
(*2) 島村菜津「スローシティ〜世界の均質化と闘うイタリアの小さな町」(光文社新書、2013.3)、宗田好史「なぜイタリアの村は美しく元気なのか〜市民のスロー志向に応えた農村の選択」(学芸出版社、2012.8)などを参照。
(*3) フランスのジビエレストランや、イタリアのスローフード協会発行の冊子に掲載されたオステリアなどには、その店(多くはオーナーシェフ)の味を求めて世界各地から集客している。昨今の「日本食」や「日本産食材」への関心が高まる中で、こうした「来消」も非現実とは言い切れないと見てよいだろう。
オホーツクのおもな農水酪の生産物と素材連関(模式図)